
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
裁判年月日 平成24年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)368号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA03238008
要旨
◆不法残留に当たるとされたネパール連邦民主共和国の国籍を有する原告が、難民不認定処分を受けたため、同処分には原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して、その取消しを求めた事案において、原告は、仲間とともに結成したグループでの政治的活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがある旨主張するが、同グループは名称さえなく、構成員は5名にすぎず、実際の活動も就労のあっせんなどといったものにとどまっていること、当時の原告は16歳と若年であり、年長者の指示に従い補助的な活動に従事していただけであること、原告が正規の手続を経て本国を出国していることなどからすれば、本国政府が原告の政治的活動を理由に個別に関心を寄せていたとは認め難く、また、原告の上陸後の行動などからすれば、本件処分当時、原告に難民の要件を満たすような事情が存在したとは認められず、本件処分は適法であるとして、請求を棄却した事例
評釈
杉谷達哉・戸籍 877号1頁
杉谷達哉・民月 67巻6号7頁
参照条文
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成24年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)368号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA03238008
東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 松本成
池田宏
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 長澤範幸ほか別紙指定代理人目録記載のとおり
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
法務大臣が原告に対して平成22年1月5日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けたことから,同処分には原告が難民であることを看過した違法がある等と主張して,その取消しを求めた事案である。
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)原告の身分事項,入国及び在留状況等
ア 原告は,1992年(平成4年)○月○日,ネパールにおいて出生した同国の国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,2009年(平成21年)4月27日,ネパールにおいて旅券の発給を受けた。
ウ 原告は,平成21年9月3日,成田空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「観光」とし滞在予定期間を「09年9月15日」までとして上陸の申請をし,同審査官から,在留資格を「短期滞在」とし在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,在留期間の末日である同月18日を超えて本邦に残留した。
(2)退去強制の手続に関する経緯
ア 原告は,平成21年11月7日,警視庁戸塚警察署警察官によって,入管法違反(不法残留)の罪を犯した疑いにより現行犯人として逮捕された。
イ 東京家庭裁判所は,平成21年11月20日,原告の前記アの非行事実について審判を開始しない旨の決定をし,東京入国管理局入国警備官は,同日,収容令書に基づき原告を東京入国管理局収容場に収容した上で,原告を入管法違反(不法残留)の退去強制事由に係る容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した。
原告については,同法所定の手続を経た上で,平成22年1月8日,東京入国管理局長により同法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決がされ,同月14日,東京入国管理局主任審査官により退去強制令書の発付処分がされるに至った。
ウ 東京入国管理局入国警備官は,平成22年2月25日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収し,東日本センター所長は,同年5月27日,原告を仮放免した。
(3)難民の認定の手続に関する経緯
ア 原告は,平成21年11月30日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,平成22年1月5日,原告について難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)をし,同月14日,原告にその旨を通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成22年1月8日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月14日,原告にその旨を通知した。
ウ 原告は,平成22年1月14日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,同年4月22日,この異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月27日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成22年5月7日,2回目の難民の認定の申請をした。
(4)本件訴えの提起等
原告は,平成22年7月14日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,本件難民不認定処分が違法か否かであり,具体的には原告が難民に当たるか否かである。
(原告の主張の要旨)
(1)難民該当性の立証の在り方
ア 難民該当性の立証責任と供述の信用性の判断について
難民は自己の難民該当性について証明手段を持たないのが通常であるから,難民該当性の主張立証責任が難民の認定の申請者本人にあるとしても,その供述を主たる材料として,恐怖体験や時間の経過に伴う記憶の変容,希薄化の可能性等も十分に考慮した上で,その基本的内容が不合理でないか等を吟味し,難民であることを基礎付ける根幹的な主張が肯認できるか否かに基づいて,最終的な判断を下すべきである。
また,その供述等を評価し吟味するに当たっては,表面的,形式的な検討の結果,矛盾点や疑問点が生じた場合には,もはやその供述等は信用できないものとして排斥すれば足りるという態度で臨むべきではなく,矛盾や疑問を感じる点が,通訳の過程で生じた可能性はないか,言語感覚や常識の違いから生じたものである可能性はないか,難民に特有の心理的混乱や記憶の混乱によって生じたものではないか等といった観点をも考慮した上で,慎重な検討を行うべきである。
さらに,難民の認定の手続における職権による調査は,難民の認定の申請者の利益のためにも運用されるべきであるから,当該申請者が難民であるとの証明責任の全てを果たさなければ,必ず不利益に認定される手続となっていないことも考慮されるべきである。
イ 立証基準
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)には,立証の程度についての規定がないが,これが高く設定されては,真の難民が保護されないおそれがある。すなわち,救済されるべき難民を確実に救済するため,所属する社会的集団や政治的意見を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の立証においては,たとえ客観的な迫害の可能性が相当程度に高いものではなく,50パーセント以下と推測されるようなものであっても,申請者の立場に立って合理的に判断した際に,迫害を受けるかもしれないと感じ,帰国をちゅうちょするような状況である場合には,その恐怖に十分な理由があると認定するべきである。
(2)原告の難民該当性
ア ネパールの一般事情
(ア)ネパールでは,1990年(平成2年)の民主化運動を経て,国王親政体制から立憲君主制へ移行したが,1996年(平成8年)以降,マオイスト(共産党毛沢東派。以下単に「マオイスト」という。)がネパール政府との間で武装闘争を開始し,国内の広い地域を勢力下に収めていった。ネパール政府とマオイストは,2006年(平成18年),約10年に及んだ紛争の終結を含む包括的和平協定に署名したが,マオイストは様々な条件闘争を継続し,その下部組織である青年共産主義者連盟(以下「YCL」という。)による暴力行為は収まりを見せず,国内の混乱は続いた。こうした中,2008年(平成20年)に制憲議会選挙が実施され,マオイストが第1党となり,同年,連邦民主共和制への移行が宣言されて,王政が廃止されることになるとともに,新憲法の制定に関する計画が発表されたが,議論の対立により作業は遅延しており,和平プロセスについても,マオイスト兵の国軍への統合に関する問題をめぐって対立が続いている。2010年(平成22年)には,王政復古のゼネストやマオイストの大規模デモ等があり,国内は不安定なままであり,また,上記デモの期間には,YCLによる青年男性の拉致事件も発生したが,マオイストの報復を恐れる警察の非協力もあって,いまだ解決されていない。
(イ)①アムネスティ・インターナショナルの2009年(平成21年)版報告(甲9)では,警察によるデモ参加者等への迫害や,警察による保護の欠如を示す事例が多数報告されており,②ヒューマンライツウォッチの同年の報告(甲10)では,2002年(平成14年)から2006年(平成18年)にかけて発生した暗殺等の事件について,被害者の遺族等が詳細な告発状を提出する等したにもかかわらず,ネパールの司法制度は全く対応できていないこと等が報告されている。また,③米国国務省が発表した2009年(平成21年)のネパールの人権状況に関する報告書(甲11)では,治安部隊のメンバーやYCL等が刑事免責の下に人権侵害行為等に携わっていることや,行方不明事件が相当数発生しており深刻な状況であるにもかかわらず,事件の解決にネパール政府が積極的ではないこと,マオイスト等の団体による闘争がしばしば発生しているが,警察による捜査は期待できない状況であること等が報告されている。このほか,④英国国境庁が2008年(平成20年)に発表した報告書(甲12)でも,上記③の報告書と同様に,ネパールの人権状況が深刻な状態であることが指摘されている。
イ 原告の個別事情
(ア)原告は,2009年(平成21年)春頃,ネパールの貧困状況を改善すること等を目標として,仲間の4人と政治活動をするグループを結成し,当初は就労センターを作って職業のあっせんを行い,徐々に,世論を喚起するための調査や,公共の場でのグループの考え方の普及へと活動を拡大した。原告らのグループのリーダーであったBは,ネパールの王族とのコネクションを持っており,ある王子による水面下の支援を得て,活動規模を拡大し,支援者はカトマンズで500人程度,全国では1万人を超えるほどとなった。なお,この頃から,原告らのグループは,現政府を否定して王政への回帰を指向するようになり,原告の意識もそのように変わっていった。
また,Bは,政府寄りのマオイストの活動を問題視していたため,マオイスト内部の信頼関係に亀裂を入れるとともに一般市民にマオイストの実態を知らせることを企図して,マオイストの会合に潜入してその様子をビデオで撮影し,これを公にする活動を行った。
さらに,原告らのグループは,王と親交のある退役将校や,マオイストによる内戦の被害者である退役軍人等と面会し,陸軍からの支援も取り付けるに至った。
(イ)前記(ア)のような活動により,王政を是とする原告らのグループは,自ずと政府及びマオイストに敵対するグループとなったが,2009年(平成21年)8月半ばころ,原告らが,翌月に行う反政府ストライキの計画を立てるために公園で話し合っていた際,15人ないし20人程度の集団に襲撃された。その場を逃れた原告は,数日後,グループの設立時のメンバーの1人であり,原告の友人でもあるCが行方不明になったことを知らされ,警察に対応を求めたが,警察は真剣に取り合わず,これを機に,原告らは切迫した危険を実感するようになった。
そして,原告は,Cの失踪からわずか数日後に,他のメンバーから,ヨーロッパに逃げるよう強く誘われ,その時点では出国を決意できずにネパールにとどまったものの,その翌日の登校中,複数人に尾行されていることに気付き,強い恐怖を抱いて校舎に駆け込んで逃げた。恐怖心が一気に強まった原告は,数日間,自宅に閉じこもっていたが,その際,日本への空手の遠征試合の話があったため,この機に日本に逃亡することを決意し,一時の危険はやむを得ないものと考えて自らビザを取得する手続をした上で,ネパールを出国した。
ウ 被告の主張について
(ア)被告は,原告らのグループと王族等とのつながりについては,原告の難民の認定の手続の段階では一切説明ないし供述されておらず,本件訴えの提起の後のしかも平成23年1月18日付け第1準備書面において初めて明らかにされた事情であり,その他原告の供述等の内容にも照らすと,これを信用することはできない旨を主張する。
しかし,原告は,本件訴えの提起前は,ネパールを危険と感じた根拠として,より直接的である仲間の失踪や自身への尾行を主張していたにすぎず,また,グループの活動内容等がネパール政府や政府寄りのグループに発覚して自己の属するグループのメンバーが迫害を受けることをおそれ,ネパールのコミュニティにより近いネパール語の通訳を警戒し,グループの全ての活動を当初からは説明できなかったものである(なお,原告は,退去強制の手続において,英語による通訳からネパール語による通訳への変更を申し出ているが,これは,ネパール語の通訳人を警戒はしつつも,自身が難民であることをより強く訴える必要性の方が高いと考えたからである。)。
そもそも,原告は,不法残留の事実を自ら出頭して申告し,本邦での保護を期待していたにもかかわらず,予想外に犯罪の被疑者として逮捕及び勾留され,このままネパールに帰されてしまうのではないかという恐怖と絶望から自殺を試みるほどの状態にあったもので,その精神的苦痛は病的なレベルにまで達しており,極限状態にあった。17歳にして単身で外国にあり,身体を拘束されていた原告の供述に,通常の成人が落ち着いて記憶に基づいて正確に話を組み立てるのと同等の合理性を求めるのは酷というべきである。
むしろ,ネパールに戻ると迫害され,政府による保護も期待できないという原告の説明を信用しなければ,いきなり母国での全てを捨てて,言葉もできず見通しの全く立たない他国で暮らすという原告の行動を合理的に説明することは困難であるから,原告の供述等には十分な信用性があるというべきである。
(イ)また,被告は,原告の難民該当性を否定する事情として,①原告は,ネパール政府から旅券の発給を受け,正規の手続で出国した,②原告は,本邦入国後,積極的に難民としての保護を求めなかった,③ネパールにいる原告の家族は平穏な生活を送っていると推認される旨を,それぞれ主張する。
しかし,①原告が旅券の発給を受けたのは,原告の政治的活動が本格化する前の2009年(平成21年)4月であるから,このことは,ネパール政府が原告を迫害の対象としていないことの証左にはならないし,迫害の直接の主体がネパール政府ではない場合には,原告が同政府から迫害を受ける恐怖心を抱かず,また,同政府も原告に格別の興味を抱かなかったとしても不自然ではなく,政府内の担当部門の違いから原告の旅券の発給の申請や出国が見逃された可能性もある。また,②原告は,来日の当時,いまだ17歳でしかなく,ネパールを出国することだけを考えて来日したもので,本邦の難民認定制度や申請の方法を正確には認識していなかった。原告は,不法残留となる前に早々に出頭してはネパールに帰される等と誤解し,滞在が安定するまで難民であることを隠そうとしたもので,現に,滞在が安定した頃を見計らって,自ら警察署に出頭している。このほか,③原告の家族について,原告がネパールを出国した当初は両親との連絡が取れていたものの,ほどなくして連絡が取れなくなったもので,平穏な生活を送っていると推認することはできない。仮に,原告の家族が平穏な生活を送っているとしても,それは原告個人が迫害を受ける可能性があることを否定する根拠とはならない。
なお,原告は,平成23年1月27日に出家し,a宗の僧侶となり,肩書住所地において本格的な修行をしている。これは,原告の人格が評価されてのことであり,このような原告が虚偽の供述を積み重ねるとは考え難いところである。
エ 小括
以上に述べたところのほか,原告が日本にこだわらず一貫してネパールには帰りたくないと訴えてきたこと,ネパールの家族と音信不通になっていること,当時17歳であった原告が母国の全てを捨てて日本に残留するという選択をしたこと等からすれば,原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者であることは明らかである。
また,前記アで述べたところのほか,原告らのグループが王政復古を目指すものであり,現政府にとっては目障りな存在であることや,実際にもCの行方不明について警察が取り合わなかったこと等からすれば,政府寄りと目されるグループからの迫害について,ネパール政府には,当該迫害を知りつつ放置,助長しているといった特別の事情があるというべきである。そして,たとえ,ネパール政府が原告らのグループや原告自身に殊更に関心を寄せ危険視するといったことがなかったとしても,原告を迫害する政府寄りのグループの活動が黙認されている状況にあることからすれば,原告が国家の保護を受けることは不可能であり,仮にこれが可能であるとしても,政府の黙認が疑われる状況において国家の保護を望まないことは自然な発想である。
したがって,原告は難民に該当するというべきであるから,本件難民不認定処分は違法である。
また,本件難民不認定処分には,補充調査を含めた慎重な検討を経ずにされた点で調査義務違反の違法があり,仮に,補充調査等がされていたのであれば,通知書(乙24)にそれらの記載がない点で理由の提示が不十分である違法があるというべきである。
(被告の主張の要点)
(1)難民の意義等
ア 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」といえるためには,難民の認定の申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。すなわち,上記の客観的事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解するのが相当である。
また,難民の本質は,国籍国による保護を受けられない者に対して,国籍国に代わって条約締結国が条約に定められた限度で保護を与えることにあるから,国籍国が現に保護している者は難民となり得ない。難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は,迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定しているのであり,難民の認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りつつ放置,助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しない。
イ 次に,いかなる手続を経て難民の認定がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項は,法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨定め,難民認定申請者に対し申請資料として「難民に該当することを証する資料」の提出を求めている(出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項)。また,難民の認定をする処分は,当該申請者が難民条約所定の「難民」であるか否かを申請者から提出された資料に基づいて確認し,処分時において難民であることを認定する行為であり,本質的には事実の確認であるが,法務大臣により難民認定を受けていることが,他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件となっており,難民の認定をする処分自体が申請者に対して直ちに何らかの権利を付与するものではないものの,授益処分とみるべきであり,授益処分は一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されているので,難民の認定の資料は申請者が提出すべきものである。さらに,難民該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,外国でしかも秘密裡にされたものであることが多く,そのような事情の有無及びその内容等は,それを直接体験した申請者こそが最もよく知ることができ,これを正確に申告することは容易である。
これらの事情に鑑みれば,申請者である原告が,自らが難民に該当することについて立証責任を負うことは明らかである。
そして,難民認定手続やその後の訴訟手続について立証責任を緩和する規定が存しない以上,難民と認定されるための立証の程度については,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,申請者は,自己が難民であることについて,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
(2)原告の難民該当性
ア ネパールの一般情勢
ネパールでは,1996年(平成8年)から約10年もの間,反政府武装組織であったマオイストによる全国的なテロ活動が行われてきたが,2006年(平成18年)11月21日にマオイストと政府との間に包括的和平協定が締結された。その後,2007年(平成19年)1月には暫定憲法が公布され,同年4月には暫定政府が発足,2008年(平成20年)4月10日に実施された制憲議会選挙ではマオイストが大勝し,マオイストの政党が主導する連立政権が誕生するに至った。しかし,和平プロセスの課題であるマオイスト兵の国軍への統合問題や新憲法の制定作業等をめぐり,各政党や国軍の間で意見の相違があり,2009年(平成21年)5月3日にはマオイストのダハール(プラチャンダ)首相がカトワル陸軍参謀長を解任したことをきっかけとして連立政権が実質的に崩壊し,同月4日にはダハール首相が辞任,マオイストが与党を離脱する等,政府と議会は不安定な状況が続いている。
イ 原告の主張する個別事情について
(ア)原告は,4人の仲間とともに王政復古に向けた反政府活動を行うグループを結成し,その一員として活動していた旨を主張する。
しかし,反政府活動をするグループを結成し,その一員として活動していたとの原告の主張はもとより,同グループ又は同グループにおける原告の活動状況についても,これを裏付ける的確な証拠は全くない上,原告の供述等にも不自然かつ不合理な点が多々認められるから,原告の主張の真偽は非常に疑わしいというほかない。
すなわち,原告らのグループの存在を裏付ける客観的な証拠はなく,原告の供述等があるのみであるところ,原告の供述は,Bと出会った状況といった重要な場面についてすら,総じて不自然であり,しかも曖昧というほかないものであって,原告らが設立したとする反政府グループが実際にネパールに存在していたかは,極めて疑わしいといわざるを得ない。その余の点を検討しても,原告らのグループには名称すらない上,その理由についても,原告は,何ら合理的な説明をしていないし,2年もの準備期間を経てもわずか5名のメンバーしか募れなかったグループが,設立後4か月で,しかもカトマンズの中だけで500人もの新規加入者を集めたというのも,明らかに不自然であり,他にも原告の供述には一貫性を欠く点等がみられる。
原告らが結成したとするグループについて,他にも不自然・不合理な点が散見されることも併せれば,グループの設立の経緯,新規参加者の増加やグループと王族との関係等に関する原告の供述は,総じて信用できず,自己の難民該当性を基礎付けるためにあえて誇張して述べられたものと解するのが相当である。
(イ)このように,原告らのグループが存在していたかは非常に疑わしいというべきであるが,その点をおくとしても,同グループにおける原告の活動状況等として原告が主張する事情は,いずれも事実として認めるに足りないか,あるいは原告の難民該当性を基礎付ける事情たり得ないというべきである。
すなわち,原告の主張する個別事情についても,これらを裏付ける的確な証拠はない。その上,原告らが結成したグループが,就労センターの設立から活動を開始して相当な規模のものになったであるとか,マオイストの会合に潜入し,撮影したビデオの内容を公にしたであるとか,退役将校や退役軍人らからの支援を取りつけ,また,王子と面会する等して王族と強固なパイプを有していたとすることについては,本件訴えの提起後のしかも平成23年1月18日付け第1準備書面において初めて主張された事情である。
さらに,本人尋問の結果を踏まえてみても,原告は,2009年(平成21年)8月半ばころのネパール政府が「マオイストの政府だった」と供述するが,実際にはマオイストは野党であったのであり,真に反政府的活動を行っていたというのであれば,およそ間違えるはずのないネパールの基本的な政治状況についてすら,原告は正確に把握していない。
原告が,上記の事情を難民の認定の手続の段階で供述できなかったことについて,後記ウのとおり,合理的な説明をしていないことからすれば,上記の事情に関する原告の主張ないし供述が真実であるかは甚だ疑わしいというほかない。
また,その余の事情についてみても,原告の供述は,曖昧かつ抽象的なものにとどまるというほかないから,その真偽は明らかではないというべきである。
さらに,仮に上記の点をおくとしても,グループにおける原告の活動については,原告の供述を前提としたとしても,その関与の度合いは極めて限定的,従属的なものにすぎないし,原告の供述からも,原告が迫害を受けるおそれはもちろん,その兆候すらなかったことが端的に表れているといえる。したがって,原告が主張ないし供述する程度の活動をもって,難民該当性を基礎付ける事情に当たるとは認められない。
ウ 原告の供述の信用性について
原告は,その供述等の信用性に係る前記イの被告の主張に対し,ネパールのコミュニティに近いネパール語の通訳人を警戒していたことから,全ての事情を本件訴えの提起より前に説明することができなかった旨を主張する。
しかし,原告は,退去強制の手続においては,通訳を英語からネパール語に変更することを積極的に希望し,難民の認定の手続においては,難民調査官に対して自筆の陳述書(乙23)を提出する等していたのであって,原告の上記の主張には理由がない。
また,原告は,収容により精神的苦痛を病的なレベルまで感じるようになり,自傷行為や自殺を試みたこともあったにもかかわらず,医師の診察を受けることができなかった等として,その供述に成人が落ち着いて話をするときと同程度のものを求めるのは酷である旨を主張する。
しかし,原告は,東京入国管理局収容場及び東日本センターでの収容中,自らが申し出た症状について庁内診療を受診することが可能な環境にあったところ,実際に原告が申し出たのは,歯痛のみであって,医師等に対し精神的な苦痛を申し出たことはなかったし,自傷行為や自殺を試みた事実も確認できない。仮に,原告が多少精神的な問題を抱えていたとしても,原告が記憶に基づいて難民調査に応じることが困難になるほどに精神的な苦痛を感じていたとはいえない(なお,原告は,収容中に叫ぶ等した際に,罰として独房に移された旨も主張するが,これは原告の体調に配慮してされた措置であって,懲罰としてされたものではない。)。
エ 小括
以上に述べたところのほか,原告については,正規の手続で自己名義の旅券を取得した上でネパールを出国していることや,本邦への入国後,警察に逮捕されて東京入国管理局に収容されて初めて本件難民認定申請をしたものであること,ネパールに居住する原告の家族が平穏な生活をしていると推認されることといった難民該当性を否定する事情が存在する。
また,ネパール政府がマオイスト派による虐待行為等を故意に容認し,又は効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはできないということは認められず,ネパール政府が原告に対する迫害を知りつつ,これを放置,助長するような特別な事情があるともいえない。
したがって,原告を難民と認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法である。
第3 争点に対する判断
1 難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(難民条約33条1項参照),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
本件において,原告は,政治的意見を理由にネパール政府又はマオイストから迫害を受けるおそれがある旨を主張しているものと解されるところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
2 認定事実
前提事実,括弧内掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)ネパールの一般的状況について
ア ネパールは,1990年(平成2年)の民主化運動を経て,国王親政体制から立憲君主制へ移行し,総選挙が実施される等していたが,1996年(平成8年)以降,王制の打倒や世俗国家の実現を掲げるマオイストが武装闘争を開始した。
その後,2002年(平成14年)5月に下院が解散され,以降,国王の指名により組閣がされていたものの,党派間の対立やマオイスト問題への対応の失敗により,いずれの政権も短命に終わり,国王は,2005年(平成17年)2月,首相を解任して自ら政権を掌握した。
政党は,国王の政権掌握を非難して国王との溝を深める一方,マオイストとの連携を模索するようになり,両者は,2006年(平成18年)4月,連携して全国規模での抗議集会等を展開し,国王により下院の復活が宣言されるに至った。
そして,同年5月18日には,復活した下院の宣告を通じ,国王の政治や軍事に関する諸権限が廃止され,同年11月21日には,政府とマオイストは,約10年に及んだ紛争の終結を含む包括的和平協定に署名した。
その後,2007年(平成19年)1月に暫定憲法が公布され,同年4月にはマオイストを含む暫定政府が発足し,2008年(平成20年)4月10日には制憲議会選挙が実施され,マオイストが大勝した。そして,同年5月28日,制憲議会の初会合が開催され,連邦民主共和制への移行が宣言され,約240年続いた王制が廃止されることとなり,同年8月には,マオイストを含む連立政権が発足した。
しかし,新憲法制定に向けた作業における大統領制や連邦制の在り方をめぐる議論の対立や,和平プロセスの最大の課題であるマオイスト兵の国軍への統合問題をめぐる対立があり,2009年(平成21年)5月3日の陸軍参謀長の解任をきっかけに連立政権は実質的に崩壊した。制憲議会の第1党であるマオイストも与党を離脱して野党に下り,政府と議会は不安定な状況が続いている。(甲12,乙31ないし34)
イ アメリカ合衆国国務省の報告書(2010年〔平成22年〕3月)では,2009年(平成21年)のネパールの人権状況について,①治安部隊のコントロールには,おおむね文民統制が機能しているが,治安部隊の独断的な行動を表す事例もしばしば見られること,②マオイスト民兵は,致命傷を与えるような武力行使をし意的かつ不法に行っており,マオイスト又はその下部組織であるYCLは,政治的に対立するグループに対し,銃撃や拉致,暴行といった攻撃を加えていること,③2006年(平成18年)の包括的和平協定は,警察等が全国的に法令を執行することを求めており,違法行為をしたマオイストやYCLの幹部が警察に拘束されることは多いものの,政治指導により釈放されることが多いこと,④政府にとらわれた政治囚及び政治的拘束者の報告は一つもなかったこと,⑤法は集会の自由や結社の自由を認めており,これらの自由はおおむね尊重されていること,⑥ネパール内外の人権擁護グループは,一般に,政府の制約を受けることなく活動しており,人権問題に関する調査や調査結果の発表をすることができ,ネパール政府は,国際的人権監視団を歓迎し,正常にビザを発行していること等が,それぞれ報告されている(甲11,12)。
また,英国内務省の報告書(2008〔平成20年〕5月)では,上記のほか,①停戦後,人権状況は改善したものの,マオイストによる脅迫や誘拐,強奪が横行しており,人権侵害の大半はマオイストにより行われているとする報告や,②包括的和平協定の実行により,人権の面では大きな進展が見られた一方で,ネパール政府には,過去及び現在の人権侵害に対する責任に取り組む政治的姿勢がいまだ欠如しているとする報告が,それぞれ紹介されている(甲12)。
(2)原告に関する個別事情について
ア 原告は,1992年(平成4年)○月○日,ネパールのカトマンズにおいて出生し,同国の小学校及び中学校を経て,2009年(平成21年)6月,高等学校の卒業試験に合格した(乙21,乙22,原告本人)。
イ 原告は,2007年(平成19年)頃,後に原告らが結成するグループのリーダーとなるBと知り合い,ネパールの政治状況に関心を持つようになり,2009年(平成21年)4月半ば頃,B等の3名の年長者(いずれも45歳前後)及び友人であるC(20歳前後)とともに,ネパールの貧困状況を改善することを目的として,政府の私利私欲による統治を肯定しないことを理念とするグループを結成した。
なお,原告らのグループは,後に王制への回帰を指向するようになったが,グループに特段の名称が付されることはなかった。(甲17〔枝番を省略する。以下同じ。〕,乙8,21,22,23,29,原告本人)
ウ 原告らのグループは,就労のあっせんから活動を開始し,その後,一般の人々に対するアンケート調査をするとともに宣伝活動をする等して,相応の支援者及び資金を得るに至った。また,原告らのグループは,ネパール政府に対する抗議活動として,凶悪事件の解決を求めるデモを呼びかける等し,そのデモの際には,参加者の中に建物を損壊する等の暴力的な行動に出たものがいたが,逮捕等の当局による取締りはなかった。
なお,原告は,グループ内で特に何らかの役職に就くといったことはなく,Bら年長者の指示に従い,その補助をしていた。(甲17,乙8,10,21ないし23,28,29,原告本人)
エ 原告らは,2009年(平成21年)8月半ば頃,政府に対する抗議活動としてストライキの実施を計画し,カトマンズの公園において,5人で話し合いをしていたが,その際,話し合いをやめるよう警告してきた正体不明の15人ないし20人の集団と口論となり,乱闘となった。
原告は,その場から逃走したが,数日後,Bから,Cが行方不明になったと告げられ,その数日後には,Bらからヨーロッパにともに逃げるよう誘われた。(甲17,乙8,10,21ないし23,28,29,原告本人)
オ 原告は,Bらとは異なり,自身がいまだ学生にすぎず,ネパールには家族も居住していて,ネパールに残ってもさほどたいしたことはないだろうと考え,ネパールにとどまることとしたが,Bらから逃亡の誘いを受けた翌日の学校への登校中(なお,原告は,当時,高等学校を卒業し,上級高等学校に入学していた。),何者かに尾行されていると感じた。
恐怖心を抱いた原告は,折しも,本邦で開かれる空手の大会への参加の誘いを受けたことから,それへの参加を機にネパールを出国することとし,2009年(平成21年)8月27日,本邦の査証を取得し,同年9月3日,正規の手続を経てネパールのトリブバン国際空港から出国し,成田空港に到着して本邦に上陸した。(甲17,乙2,8,10,11,21ないし23,28,29,原告本人)
カ 原告は,本邦で空手の大会に参加した後,帰国せず,本邦で知り合ったネパール人の世話を受けて生活していたが,平成21年11月7日,警察に出頭して自らの不法残留の事実を申告し,同日,警視庁戸塚警察署警察官によって現行犯人として逮捕された(甲17,乙8,22)。
3 検討
(1)原告は,仲間とともに結成したグループでの政治的な活動を理由に,ネパール政府から迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかし,原告らのグループについては,前記2(2)イ及びウで認定した事実(以下,前記2で認定した事実を「認定事実」という。)のとおり,名称さえなく,中心となる構成員は原告を含めて5名にとどまり,その実際の活動も,原告が出国する前のわずか4か月間のもので,対外的なものとしては,就労のあっせんや一般の市民に対するアンケートでの意識調査,凶悪事件の犯人の検挙を求めるデモの呼びかけないし参加,支援者の勧誘及び資金調達,ストライキの企画といったものにとどまっている。そして,認定事実(1)イのとおり,2009年(平成21年)のネパールにおいていわゆる政治犯の報告がなく,集会の自由や結社の自由もおおむね尊重されていたとされていることに加え,認定事実(2)ウのとおり,原告らのグループが関わったデモにおいて,参加者の中に暴力的な行動に出た者がいたにもかかわらず,特段取締りがされる等したことがなかったこと,原告が,当時はいまだ16歳と若年であり,Bらの年長者の指示に従い,補助的な活動に従事していたにすぎないこと,認定事実(2)オのとおり,原告は,その後,正規の手続を経てネパールを出国していることも併せ考慮すれば,ネパール政府が原告に対してその政治的な活動を理由に個別に関心を寄せていたと認めるには疑問が残るというべきであり,このことは,認定事実(2)エのとおり,原告らがカトマンズの公園という公共の場で反政府ストライキの計画に係る話し合いをする等,原告ら自身,ネパール政府による迫害のおそれを感じていたとは考え難いことや,認定事実(2)エ及びオのとおり,原告は,Cが行方不明になりBらがネパールから脱出することを誘われた際にも,切迫した危機感を抱くことなくネパールにとどまることとしたことからも裏付けられるものということができる。
(2)また,原告は,マオイストから迫害を受けるおそれがあり,ネパール政府もマオイストによる迫害を放置,助長している旨を主張しているところ,認定事実(1)イのとおり,マオイスト又はYCLは,2006年(平成18年)の包括的和平協定の後も,政治的に対立する立場にある者に対し,銃撃や拉致,暴行といった攻撃を加えている等とされているものである。
しかし,既に述べたとおり,原告らのグループには名称さえなく,その実際の活動も認定事実(2)イ及びウのとおりで,殊更にマオイスト又はYCLとの対立を生じさせるようなものであったとまでは考え難く,前記(1)でも述べたとおり,原告が,当時はいまだ16歳と若年であり,Bらの年長者の指示に従い,補助的な活動に従事していたにすぎないこと等も考慮すれば,マオイスト又はYCLが原告に対してその政治的な活動を理由として個別の関心を寄せていたと認めるについても,やはり疑問を差し挟まざるを得ない。
また,この点をおき,仮に,原告らのグループ又は原告がマオイスト又はYCLから相応に関心を寄せられていたものであるとしても,警察等が違法行為をしたマオイストやYCLの幹部を多数拘束する等していることは,認定事実(1)イのとおりであって,ネパール政府が立場を異にするマオイスト又はYCLによるその政治的主張に基づく迫害の発生を認識しつつ,これを放置,助長するような特別な事情があるということも困難というほかなく,他に上記特別な事情が存在することをうかがわせる事情ないし証拠は見当たらない。
(3)ア この点,原告は,迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情として,①原告らのグループが,王政への回帰を指向して,ネパールの王族や退役軍人,陸軍の支援を取り付けていたこと,②原告らのグループが,政府寄りであるマオイストの会合に潜入してその様子を撮影し,これを一般に公にする活動をしたこと,③原告らのグループが,マオイスト又はYCLと思われる集団からの襲撃を受けたこと,④マオイスト又はYCLの関与の下でCが行方不明となり,警察に対応を求めたにもかかわらず,取り合ってもらえなかったこと,⑤原告自身,何者かに尾行され,強い恐怖を抱いたことをそれぞれ主張する。
イ しかし,①原告は,本件訴えの提起の後になって初めて原告らのグループが王族等の支援を取り付けていた旨の主張をし,これに沿う供述等(甲17,原告本人)をするに至ったものであって,こうした経緯は,その主張や供述等の信用性を低下させる事情といい得る。また,この点をひとまずおくとしても,その供述等をするところは,大要,「2009年(平成21年)6月に王子と面会し,その際,他のグループの代表を集めて会議をすることが決まった。そして,同年7月に会議が行われ,王子の主導の下,各グループが王族の関与を隠して活動することを確認し,王も各グループを訪問することになった。同じころ,王と親交のある退役将校と会い,支援の約束を取り付け,また,陸軍からも支援を取り付けた。」(甲17)というもので,そこでいう「活動」や「支援」の具体的な内容は明らかではない上,同年4月半ばに結成された原告らのグループは,その当時いまだ結成から間がなく,名称さえもなかったこと(認定事実(2)イ)を踏まえると,上記のような原告の供述等は,具体性,迫真性を欠いているというほかない。
また,同様に,②原告らのグループが,マオイストの会合の様子をひそかに撮影し,これを一般に公にする活動をしたとする点についても,本件訴えの提起の後になって初めて明らかにされたものであり,また,この点をひとまずおいても,原告の供述等をするところは,マオイストの会合の内容やこれを公にした手段,これに対する市民又はマオイストの反応といった当然に言及されるべき点についての具体的な説明がなく,やはり,具体性,迫真性を欠いているというほかない。
このように,原告の前記アの①及び②の各主張に沿う原告の供述等については,原告のその余の主張を考慮したとしても,疑問を差し挟まざるを得ないというべきであり,他にこれらの主張に係る事実の存在を認めるに足りる証拠はない。
ウ 次いで,③原告らのグループが,公園で反政府ストライキの計画について話し合いをしていた際に襲撃を受けたとする点については,認定事実(2)エのとおり,これに一部沿う事実が認められるが,それらの集団がマオイスト等であったとすることについては,本件全証拠によっても,原告の推測を超えるものとは認め難く,的確な裏付けを欠いているというほかない。
④Cが行方不明となったとする点についても,原告はBからその旨を告げられたというにとどまり,Cの失踪を裏付けるような証拠ないし事情は見当たらないし,仮に,Cが失踪したものであるとしても,これがマオイスト又はYCLによる拉致等であったとすることについては,やはり,的確な裏付けを欠いているといわざるを得ない。⑤このことは,原告が尾行されたとすることについても同様であり,仮に,原告が何者かに尾行されたことがあったとしても,それがマオイスト又はYCLによるものであったかは本件全証拠によっても明らかではないというほかない。
結局,原告の前記アの③ないし⑤の主張は,いずれも採用することができないものというべきである。
エ さらに,そもそも,ネパール政府においてマオイスト又はYCLによるその政治的主張に基づく迫害の発生を認識しつつ,これを放置,助長するような特別な事情も認め難いことは,既に述べたとおりである。
4 小括
以上に検討したところのほか,原告は,生命の危険を感じてネパールを出国した旨主張しながら,前提事実(1)ウ及び同(3)アのとおり,本邦への上陸後3か月近くが経過し不法残留の事実による退去強制の手続が開始されてから本件難民認定申請をするに至っており,このことについての原告の供述等を参照しても,首肯するに足りる合理性を有するものとはいい難いことや,ネパールに居住する原告の家族が迫害を受けていることをうかがわせる事情ないし証拠が見当たらないこと等も考慮すると,原告については,本件全証拠によっても,本件難民不認定処分がされた当時において,前記1に述べた難民の要件を満たすような事情が存在したとは認めるに足りないというべきである。
したがって,原告が入管法上の難民であると認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法であるというべきである。
なお,以上のほか,原告は,本件難民不認定処分について,当時の原告はネパール語の通訳人に対する不信感や心身の状態から十分な供述等をすることができなかったとした上で,①法務大臣が原告の難民該当性に係る補充調査を怠った違法がある,②仮に,補充調査等をしていた場合は,これに係る検討結果が本件難民不認定処分に係る通知書に記載されていない点で,理由の提示が十分ではない違法がある旨を,それぞれ主張する。しかし,難民の認定の申請をする者が難民該当性に係る各要件を立証すべきであることは,前記1に述べたとおりであり,また,原告は,本件難民認定申請に際し難民調査官によるインタヴューにつきネパール語の通訳を希望し(乙21),先行して進められた退去強制の手続における違反審査及び口頭審理において,自己が不法残留の退去強制事由に該当することを認めるとともに,自己が難民に当たることについては後に難民の認定の手続において述べる旨を供述しており(乙11,13),さらに,これらの後にされた難民調査官によるネパール語の通訳人を介しての事実の調査の際には,同調査官から,原告が経験したことは原告が一番よく知っており,原告でなければ分からないこともあるので,原告が難民であるかどうかを正しく判断するためには,本当のことを説明してもらう必要がある,通訳人は中立の立場で通訳し,知り得た情報を外部に漏らしたり他の目的に使用したりすることはない等の説明を受けた上で供述をしていたもので,その時点で健康状態は良好で何も問題はない旨供述していたこと(乙22),原告は,その後,本件難民不認定処分がされるまでの間に,自筆の陳述書も提出していること(乙23),原告が自己が難民に該当するとして主張するところは,その内容に照らし,本邦内の第三者による補充調査等になじむものとは認め難いこと等を考慮すると,原告の上記の主張は,いずれも採用することはできないというべきである。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 田中一彦 裁判官 塚原洋一)
別紙
指定代理人目録 省略
*******
政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
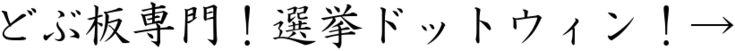




この記事へのコメントはありません。