
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
裁判年月日 平成19年12月11日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(う)2754号
事件名 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
裁判結果 破棄自判 上訴等 上告 文献番号 2007WLJPCA12117001
要旨
◆分譲マンションの共用部分が刑法130条前段の「住居」に当たるとされた事例
◆政治ビラの配布を目的とする上記共用部分への立入りにつき刑法130条前段の住居侵入罪が成立するとされた事例
新判例体系
刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第一二章 住居を侵す… > 第一三〇条 > ○住居侵入罪 > (三)客体 > A 人の住居 > (1)意義、範囲 > (チ)共同住宅の共用部分
◆分譲住宅の玄関ホール、通路、エレベーター等の共用部分は、刑法第一三〇条前段の住居に当たる。
裁判経過
上告審 平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 判決 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
第一審 平成18年 8月28日 東京地裁 判決 平17(刑わ)61号 住居侵入被告事件 〔政党ビラ配布事件・第一審〕
出典
東高刑時報 58巻1~12号119頁
判タ 1271号331頁
評釈
関口新太郎・ひろば 61巻5号60頁
荒川庸生・法と民主主義 436号26頁
山田健太・月刊民放 38巻2号38頁
加藤経将・警察公論 63巻4号89頁
中村欧介・週刊法律新聞 1748号2頁
永山茂樹・法セ 640号133頁
杉本吉史・民主法律 272号165頁
西田穣・法と民主主義 443号62頁
参照条文
刑法130条前段
裁判年月日 平成19年12月11日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(う)2754号
事件名 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
裁判結果 破棄自判 上訴等 上告 文献番号 2007WLJPCA12117001
主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金5万円に処する。
未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分を,その刑に算入する。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
本件控訴の趣意は,検察官岩村修二作成の控訴趣意書に記載されたとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人中村欧介作成の答弁書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。
論旨は,要するに,原判決は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成16年12月23日午後2時20分ころ,春野一郎ら多数名が居住する東京都葛飾区亀有〈番地略〉所在の7階建て分譲マンション『メゾン亀有』(以下「本件マンション」ともいう。)内に侵入した。」との公訴事実に対し,被告人が本件マンションの共用部分に立ち入ったことや,立ち入った共用部分が住居侵入罪の「住居」に当たること,その立入り行為が本件マンションの管理権者の意思に反していることを認定しながら,その意思が明確に表示されていなかったから,被告人の立入り行為は「正当な理由がない」ものとはいえず,住居侵入罪を構成する違法な行為とは認められないとして,被告人に無罪を言い渡したが,原判決は,刑法130条前段の「正当な理由」の有無について事実を誤認した上,同条前段の解釈,適用を誤ったものであり,これらの誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるというのである。
そこで,原審で取り調べた関係証拠に加えて,当審で取り調べた証拠を併せ検討すると,被告人の上記立入り行為が刑法130条前段の「正当な理由」がないものとはいえないとの理由により被告人に無罪を言い渡した原判決は,同条前段の解釈,適用を誤ったものといわざるを得ず,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決は破棄を免れない。以下,説明する。
1 事案の概要
(1) 本件マンションの構造,管理及び利用の状況
本件マンションは,東京都葛飾区亀有*丁目所在の地上7階,地下1階建ての鉄筋コンクリート造りの分譲マンションであり,1階部分は4戸の店舗・事務所として,2階以上は40戸の住宅として分譲されている。本件マンションの西側部分は,環状7号線東側歩道に面しているが,敷地の南側部分は隣接する店舗との間に塀及び金網フェンスが,東側部分は隣接する民家との間に塀が,北側部分は砂利の敷かれた道路との間に塀がそれぞれ設置されている。1階の店舗は,それぞれ歩道に面した西側に出入口があり,2階以上の住戸への出入口としては,本件マンション西側の北端に設置されたガラス製両開きドアである玄関出入口と,敷地北側部分に設置された鉄製両開き門扉である西側敷地内出入口とがある。玄関出入口付近の壁面には警察官立寄所のプレートが,玄関出入口ドアには「防犯カメラ設置録画中」のステッカーが貼付されている。玄関出入口から本件マンションに入ると,玄関ホールがあり,右手(南側)には掲示板と集合ポストが,左手(北側)には管理人室がある。管理人室の窓口からは,玄関ホールを通行する者を監視することができ,本件マンションの管理組合(以下「管理組合」ともいう。)から管理業務の委託を受けた会社が派遣した管理員が,水曜日を除く平日の午前8時から午後5時まで,水曜日と土曜日は午前8時から正午までの間,勤務している。管理人室窓口の上部壁面には,緊急連絡先や上記会社の電話番号が記載されたプレートと本件マンションに勤務している管理員名が記載されたプレートがそれぞれ貼付されている。玄関ホールの東側には両開きガラス製ドアである玄関内東側ドアがあり,これを開けて,1階廊下を進み,突き当たりを右手(西側)に折れるとエレベーターがあって,内部には防犯カメラが設置されている。また,上記の突き当たりを左手(東側)に進むと,鉄製片開きドアである東側出入口があり,東側出入口から本件マンションの外側(敷地内)に出ると左手に北側外階段が,更に右手に本件マンションの外壁に沿って進むと中央外階段がそれぞれ設置されていて,2階以上に続いている。他方,西側敷地内出入口から本件マンションの敷地内に入り,本件マンション北側に設置された自転車置き場に沿って東側に進み,更に本件マンションの外壁に沿って南側に進むと,上記東側出入口に至る。
(2) 本件マンションへの部外者の立入りについて
管理組合理事会は,かねてチラシ,ビラ,パンフレット類の配布のための立入りについて,葛飾区の公報に限って集合ポストへの投函を認める一方,その余については,集合ポストへの投函を含めて禁止する旨決定しており,管理員夏川二郎にもその旨指示していた。
本件マンション玄関ホール南側の掲示板には,管理組合名義のA4版大の白地の紙に「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます。」と黒色の文字で記載されたはり紙(以下「はり紙A」ともいう。)や,管理組合名義のB4版大の黄色地の紙に「当マンションの敷地内に立ち入り,パンフレットの投函,物品販売などを行うことは厳禁です。工事施行,集金などのために訪問先が特定している業者の方は,必ず管理人室で『入退館記録簿』に記帳の上,入館(退館)願います。」と黒色の文字で記載されたはり紙(以下「はり紙B」ともいう。)等が掲示されている。
弁護人の所論は,原判決は,管理組合理事会において,ビラの投函を目的とする部外者の立入りを禁止できるとの判断の下に,実際に理事会がその旨決定したと認定しているが,①政治ビラの配布が憲法21条1項によって保障された政治的表現の自由に基づくものであり,個々の居住者の情報受領権や知る権利の対象にもなることに照らせば,ビラの投函の禁止は,住民の総意や少なくとも管理組合総会によって決定されることが必要であり,②管理組合理事会で上記決定がなされたことを示す証拠も存しない旨主張している。
しかし,①についてみると,本件マンションにおいて,専有部分は,住戸番号を付した住戸のみとされ,玄関ホール,廊下,階段,エレベーターホール,エレベーター室等はすべて共用部分とされている(管理組合規約7条,8条)ところ,敷地及び共用部分等の管理は,本件マンションの区分所有者全員により構成されている管理組合がその責任と負担においてこれを行うとされ(19条),敷地及び共用部分等の保安,保全,保守,変更,処分,運営等の業務も,管理組合の業務として定められている(30条1号,5号)。また,管理組合の役員として総会で選任された理事は,理事会を構成し,理事会の定めるところに従って,管理組合の業務を担当する(37条)と定められている。そうすると,ビラの配布を目的とするものを含めて,部外者の本件マンションの共用部分等への立入りを禁止するか否かは,区分所有者全員により構成されている管理組合の規約によって,敷地及び共用部分等の保安,保全等に関する業務の一環として,理事会がこれを決定すると予定されているものと解される。所論は,政治ビラの配布が憲法21条1項の保障する政治的表現の自由に基づくものであり,個々の居住者の情報受領権や知る権利の対象にもなることを理由として,政治ビラを配布,投函するための部外者の立入りを禁止するには,区分所有者全員の総意又は管理組合総会の議決が必要である旨を主張するものと解されるが,民間の分譲マンションであれば,区分所有者らがその点につき決定の手続を含め自由に決定する権利を有することは明らかであるし,本件では,管理組合の理事会がこれを決定し,掲示板にその旨を掲示していたところ,これについて住民から異論や苦情が出された事実はないのであるから,その理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。所論①は採用できない。
次に,②について検討すると,上記のとおり,管理組合理事会が葛飾区の公報を除き,集合ポストへの投函を含め,ビラの配布を目的とした部外者の立入りを禁止する旨決定していたとの夏川証言は,具体的な内容であって,不自然な点はない。マンション住民らが,治安,防犯等の見地から共用部分への部外者の立入りを禁止するのが不合理といえないことは明らかであり,ビラの配布を目的とした部外者の立入りについて,区の公報を除いてはビラの内容を問わず一律に禁止するのも,実効性等を考慮すれば,不合理な点はない。しかも,夏川の上記証言は,本件マンション玄関ホール南側の掲示板に,ビラの投函を禁止し,パンフレットの配布等の目的による部外者の立入りを禁止する内容の管理組合名義の貼り紙A,Bが貼られていることや,平成14年3月17日に,「関係者以外立入禁止,御用の方は管理事務室へ」という内容の看板を設置すべきことを決議した旨の理事会議事録の記載とも整合的である。そうすると,夏川の上記証言は,十分に信用することができ,所論②も採用できない。
(3) 被告人による本件マンションへの立入りの状況について
被告人は,平成16年12月23日午後2時20分ころ,日本共産党のビラを配布するために,本件マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り,更に玄関内東側ドアを開け,1階廊下を経て,エレベーターに乗って7階に上がり,各住戸のドアポストにビラを投函しながら7階から3階までの各階廊下と外階段を通って3階に至ったところを,春野に声をかけられて,ビラの投函を中止し,1階出入口付近に移動した。
2 被告人の立入り行為と住居侵入罪の成否について
(1) 構成要件該当性について
原判決は,①本件マンションの共用部分が刑法130条前段の住居に当たることを前提とした上で,②被告人の立入り行為を「正当な理由」のないものと認めることはできない旨説示し,その根拠として,(ア)一般的に,本件マンションのようなマンション内へのビラの配布を目的とする立入り行為が当然に刑罰をもって禁じられているとの社会通念は未だ確立しているといえないし,(イ)本件マンションについても,(a)はり紙Aは,商業ビラの投函を禁止する趣旨にも読むことができ,政治ビラも含めた一切のビラの投函を禁止する趣旨であることは明らかでなく,その位置も玄関ホール内に立ち入った者が立ち止まらないで通過すれば目に入らない箇所であり,現に被告人が本件マンション内に立ち入った際にこれを読んだという事実も認められないほか,はり紙Bも,同様に営業活動を禁止する趣旨にも読むことができる上,入退館記録簿は本件当時存在せず,記録簿による入退館の管理は形骸化しており,(b)本件マンションには,いわゆるオートロックシステムが設置されておらず,管理員が滞在していない時間帯も多く,2階以上へは外階段で上り下りができる構造になっているから,外観上,部外者の立入りが禁止されていることが明らかな外部と隔絶した構造とはいえず,(c)被告人が事前に管理者等から立入りについて注意や警告を受けた事実もないことから,管理組合の部外者立入り禁止の意思表示が来訪者に伝わるように実効的な措置が執られていたとはいえないことを指摘している。
ア 住居について
前記のような本件マンションの構造,利用,管理等の状況に照らすと,その共用部分は,分譲された住戸部分に付随しており,その住民らが区分所有者として構成する管理組合を通じて共同して利用,管理することが当然に予定されていて,住民らの生活の平穏に配慮する必要が強く認められる空間であるといえるから,各住戸と一体をなして刑法130条前段の「住居」に当たると解される。この点につき,弁護人の所論は,本件マンションの上記共用部分は刑法130条前段の「建造物」にすぎず,「住居」に該当しない旨主張するが,上記の点に照らし,採用できない。
イ 正当な理由について
この点に関する原判決の(ア)の判断の当否はしばらく措くとしても,(イ)の判断は是認することができない。すなわち,(a)の点についてみると,はり紙Aは,その文面上,特に商業用のものに限定することなく「チラシ・パンフレット等広告」の投函を禁止しており,政治ビラも「チラシ・パンフレット等広告」に含まれることは明らかであるところ,ビラが商業用のものであるか否かを問わずその投函を禁止することも,その実効性を確保するなどの観点から不合理とはいえないから,それらを商業的なものに限定して解釈する余地があるとする原判断は相当でない。また,はり紙Bは,文面上,本件マンションに立ち入って,パンフレットの投函等を行うことを厳に禁止しており,営業活動の禁止に限定したものでないことは明らかであるところ,はり紙Aによって投函自体が禁止されている「チラシ・パンフレット等広告」の投函を目的として敷地内に立ち入ることが許容されるはずはないから,はり紙A,Bを併せ読めば,政治ビラの投函を目的とする敷地内への立入りも禁止されているものと認められる。確かに,原判決が指摘するように,入退館記録簿は存在しないが,はり紙Bの後段は,訪問先が特定されている部外者に対して,管理員に用件を告げて立ち入ることを求めることにその趣旨があることは明らかであるから,入退館記録簿が存在しないからといって,はり紙Aとはり紙Bの前段で禁止された立入りが自由になると解釈する余地はない。
そして,はり紙A,Bの貼付されている位置は,玄関ホールに入ってすぐの右側壁面の掲示板であり,その左手には集合ポストが設置されているのであって,ビラの配布を目的として玄関ホールに立ち入った者には,よく目立つ位置であると認められる。したがって,はり紙A,Bの貼付されている位置等に照らし,それが読める場所まで立ち入ったにすぎない場合(例えば,集合ポストにビラを配布する目的で玄関ホールに立ち入ったが,はり紙A,Bを見て退出した場合等)は更に検討すべき余地があるとしても,少なくともそれより先である玄関内東側ドアの内部まで部外者が立ち入ってビラを配布するのを禁止していることは明らかである。また,本件マンションのような集合住宅で用件のない部外者の立入りが広く認められているような社会情勢にあるとはいえないところ,被告人自身,同じようなはり紙が貼付されているマンションを知っていた(558丁)し,本件マンションには本件時を含め3回も立ち入っており(539丁),春野の110番通報により臨場した警察官から上記はり紙を指摘されて,その存在を知っていた旨述べていた(一色昭雄証言,60丁)というのであるから,本件時に確認したことはなかったとしても,これを認識していたと認めるのが相当であり,これに反する被告人の供述(544丁)は信用できない。
次に,(b)の点についてみると,前記のとおり,本件マンションは,1階の店舗・事務所と2階以上の住戸とで出入口を異にしており,玄関出入口からは住戸にしか出入りできない。玄関出入口から玄関ホールに入ると,右手には掲示板と集合ポストが,左手には管理人室がそれぞれ設置されており,掲示板には部外者の立入り等を禁止する上記はり紙A,Bが掲示され,管理人室には平日の日中(水曜日と土曜日の午後を除く。)に管理員が滞在しており,管理人室窓口付近の壁面には管理会社の連絡先等を記載した各プレートが貼付されている。玄関出入口から住戸に行くには,玄関出入口を開けて玄関ホールに入り,これらの掲示板,集合ポスト,管理人室の前を経て,更に玄関内東側ドアを開けて1階廊下を通り,防犯カメラの設置されたエレベーターで2階以上に上がることが主に想定されている。このような本件マンションの構造,管理及び利用の状況等に照らせば,玄関出入口と玄関内東側ドアに挟まれた空間である玄関ホールには,郵便等の配達や管理員に立入りの許否を確認しようなどとする部外者の立入りを許容する一方で,玄関内東側ドアより先は,工事の施工や集金等のために訪問先が特定している者を除き,部外者の立入りは予定されておらず,各住戸のドアポストへのビラの配布を目的とする者がこれらの立入りを予定された者に含まれないことは明らかである。確かに,本件マンションがオートロック方式を採用しておらず,管理員が管理人室に常駐していないことや,外階段による2階以上への出入りが可能であることは,原判決の指摘するとおりである。しかし,オートロック方式を採用したり,管理人室に管理員を常駐させたりすることは,当該集合住宅の建設時期,構造変更の容易性,必要となる管理費の金額等とも関連するのであるから,それらの方式によらない限り部外者の立入りを禁止できないというのは,居住者である区分所有者の権限を不当に制約するものである。また,エレベーター以外に外階段を通じて出入りする余地を残すことは,自転車を利用する住民の便宜や,火災,停電等の際の住民の安全等のために必要なことであるから,その点を理由として部外者の立入りを禁止できないというのも不当であって,これらの点は,住民らの意思を前記1(2)のように認めることの妨げとはならない。
また,(c)の点は,前記のとおり,集合住宅で用件のない部外者の立入りが広く認められているような社会情勢にあるとはいえず,本件マンションにおいても玄関ホールにはり紙A,Bが貼られており,管理人室の前を経て玄関内東側ドアを開けて進まなければ住戸部分に至らない構造となっているのであるから,少なくとも玄関内東側ドアより先への立入りが禁止されていることを来訪者に伝えるための実効的措置が執られていなかったとはいえない。
ウ 小括
以上のような本件マンションの構造等に加え,本件マンションがビラ配布のための部外者の立入りを許容していないことを被告人が知っていたと認められることなどを併せ考慮すると,被告人がビラを配布するために,本件マンションの共用部分である玄関ホールを経て,1階通路,エレベーター,7階から3階の各階廊下及び外階段に立ち入った行為は,玄関内東側ドアより先の共用部分への立入りはもちろんのこと,その立入りのための玄関ホールへの立入りを含め,刑法130条前段の住居侵入罪を構成すると認めるのが相当である。
(2) 違法性阻却事由及び可罰的違法性について
弁護人の所論は,被告人の本件立入り行為は,正当行為として違法性を阻却されるか,可罰的違法性を欠いていると主張している。
確かに,被告人は,政治ビラを配布する目的で本件立入り行為に及んでおり,その目的自体に不当な点はない。政治ビラ,特に少数者の意見を伝えるためのビラの配布等による表現の自由は,尊重されなければならない。他方,住民らは住居の平穏を守るため,政治ビラの配布目的を含め,マンション内に部外者が立ち入ることを禁止することができるのであり,上記のとおり,本件マンションにおいては,管理組合によりそのような決定が行われ,これが住民の総意に沿うものであったと認められるのであるから,この住民の意思に反してまで,本件マンション内への立入りが正当化されるものではない。しかも,このように部外者の立入りが禁止された本件マンションに立ち入ることなくビラを配布したり,ビラに記載された情報や意見をビラの配布以外の方法で伝達することもできるのであり,被告人が行った各住戸のドアポストへの配布が必要不可欠な伝達方法とはいえない。前記のような本件マンションの構造,管理及び利用の状況等に照らせば,ビラの配布を目的として,住民らの許諾を得ることなく本件マンション内に立ち入り,7階から3階までの多くの住戸のドアポストにビラを投函しながら滞留した行為が相当性を欠くことは明らかであり,被告人のこの立入り行為につき違法性が阻却されるとか,可罰的違法性を欠くと解することはできない。所論は採用できない。
(3) 憲法21条1項との適合性について
弁護人の所論は,被告人の行為が住居侵入罪に該当するとして処罰することは,憲法21条1項に違反すると主張している。
確かに,憲法21条1項が保障する表現の自由は,民主的過程の維持等のために必要欠くべからざる基本的人権であり,最大限尊重されることが憲法上要請されている。しかし,憲法21条1項は,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の財産権,管理権等を不当に害することは許されないといわなければならない。そして,上記のとおり,本件マンションは,その共用部分といえども私人の財産権,管理権等の及ぶ領域であって,住民らはその意思に反する立入りを受認すべき地位にはないのであるから,住民らの委託を受けた管理員又は個別の住民の許諾を受けないで,本件マンションに侵入した本件の所為について刑法130条前段の規定を適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反するものではない(最大判昭和45年6月17日刑集24巻6号280頁,最三小判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁)。なお,このように解しても,立入りの禁止された本件マンションに立ち入って行うドアポストへの投函以外の方法によってビラを配布することは可能であるし,ビラを配布する者が,個別の住民の許諾を得た上で,そのドアポストにビラを投函するために本件マンションに立ち入ることは禁止されておらず,住民らが管理組合の決議等を通じてビラ配布のための立入り規制を緩和することができないわけでもないのであるから,本件マンションの住民の情報受領権や知る権利を不当に侵害しているわけでもない。
3 結論(破棄自判)
以上の次第で,被告人に対する住居侵入罪の成立を否定した原判決は法令の適用を誤っており,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は,この限度で理由がある。
よって,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法400条ただし書を適用して,当裁判所において更に判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は,正当な理由がないのに,平成16年12月23日午後2時20分ころ,春野一郎ら多数名が居住する東京都葛飾区亀有〈番地略〉所在の7階建て分譲マンション「メゾン亀有」内に侵入した。
(証拠の標目)〈省略〉
(公訴棄却の主張について)
弁護人の所論は,①被告人に対する適法な逮捕は存せず,検察官が主張する私人による現行犯逮捕は事後的にねつ造されたものであるし,②被告人は,司法警察員に引致された後も,被疑事実,弁護人選任権及び黙秘権を直ちに告知されないまま,当初の取調べを受けるなど適法な弁解録取手続を受けておらず,③単にマンションの住戸のドアポストにビラを投函しただけの軽微な本件事案に対して,捜査比例の原則に反した著しく過大な捜査が行われるなど,本件の捜査やそれに引き続く本件公訴の提起は,日本共産党をねらい打ちしたものであって,本件の捜査手続や本件公訴の提起には,憲法31条,34条,38条1項等の規定に違反する重大な違法があるから,本件公訴は棄却されるべきであると主張している。
(1) 被告人が亀有警察署で取り調べられた経緯及び状況について
平成16年12月23日午後2時25分ころ,被告人が本件マンションの3階で各住戸のドアポストにビラを投函していると,春野が被告人に対してドアポストにビラを入れたのは被告人かと尋ねたので,被告人はこれを認めた。春野が共産党のビラを投函することや本件マンションへの立入りについて強く苦情を述べたので,被告人は,正当な政治活動である旨を主張し,口論となった。被告人が今後の春野とのトラブルを避けるため,同人の居室に投函しないで済むよう,同人の部屋番号を尋ねると,春野は,被告人に対して,自室に近づかないよう求めるとともに,午後2時27分ころ,持っていた携帯電話で110番通報して,本件マンションに立ち入ってビラを投函した者がいるとか,その者の「ガラを押さえた。」「PCで来い。」などと告げた。被告人は,春野から1階に下りて待つように言われたので,玄関出入口付近に行き,後から下りてきた春野と共に同所付近で警察官の到着を待った。午後2時40分ころ,亀有警察署亀有駅南口交番に勤務している一色昭雄警察官及び二宮和夫警察官が本件マンションに到着すると,春野は,「この人が勝手にマンションに入って玄関ドアポストにチラシを配りました。被害届を出します。訴えますから,早く警察に連れて行ってください。」などと強い口調で述べた。一色は,亀有警察署に「亀有*丁目で住居侵入の常人逮捕事案を取扱中」などと連絡し,しばらくすると,同署刑事組織犯罪対策課の三井課長,四谷課長代理,五木警察官らの乗った捜査用車両が到着した。一色が,三井らの指示を受けて,被告人を捜査用車両に乗せ,パトカーの到着を待っていると,しばらくしてパトカーが到着したので,その後部座席中央に被告人を乗せ,その右側に五木が,左側に一色がそれぞれ乗り込んで,被告人を亀有警察署に連行し,同署2階取調室に入室させ,午後3時15分ころ,六田正男警察官に被告人を引き継いだ。その後,被告人は,複数の警察官から本件の経緯等について事情を聴取された後,午後3時55分ころ,六田から被疑事実の要旨と弁護人が選任できる旨を告げられ,弁解を聴取された。その際,被告人は,私人に逮捕されたことを知らされて興奮し,六田と口論になったが,その後,岡田弘隆弁護士を弁護人に選任したい旨申し出た。六田は,岡田の事務所に時間を置いて数回にわたり電話をかけたが,岡田と連絡がとれなかったので,被告人にその旨告げたところ,被告人から岡田の自宅を知らされたので,その情報を基に,岡田方の電話番号を調べて,午後5時5分ころ,岡田に対し,被告人が岡田を弁護人に選任することを希望している旨電話で通知した。同日夜,五木警察官が被告人に対する取調べを開始し,その際,黙秘権を告知した。
以上の事実は,一色,春野及び六田の各原審公判証言,110番聴取状況報告書(甲2),携帯電話時刻誤差確認結果報告書(甲37),弁解録取書(甲51),弁護人選任通知簿(甲52)等により認められる。
弁護人の所論は,被告人の供述に依拠して,被告人は,午後5時ころまで事情聴取を受けた後,帰宅したい旨を告げたところ,その時点で始めて逮捕されている旨を告げられ,弁護人を選任したい旨伝えたものであり,これと相反する六田証言等は信用できないなどと主張している。しかし,六田証言のうち弁解録取書(甲51)や弁護人選任通知簿(甲52)等の客観的証拠に裏付けられている点については信用することができるから,これに反する被告人の供述に基づく所論は採用できない。
(2) 現行犯逮捕について
上記認定のとおり,本件マンションの3階廊下において,春野が被告人を発見した時点では,被告人を住居侵入罪の現行犯として逮捕する要件が充たされていたと認められるし,一色が本件マンションに到着した時点においても,現行犯逮捕の要件は失われていない。確かに,春野は,自ら被告人の身体に直接的な支配を設定していないが,110番通報の際の「ガラは押さえた。」「PCで来い。」という発言や,一色が到着した際の「早く警察に連れて行ってください。」等の発言内容に照らすと,逮捕の意思があったことが推認できる。そして,一色らが到着した以降も,手錠をかけるなどの直接的な支配は設定されていないが,一色らの臨場により被告人はその場を離脱することが困難になったのであるから,この時点で,被告人は実質的に春野と一色らの支配下に入り,現行犯逮捕されたものと認められる。実際,一色は,現行犯逮捕された犯人の引渡しを受けたことを前提とした報告を行い,その後も逮捕状の請求がされた形跡はなく,この前提に基づいて捜査が続行されたものと認められ,このように解しても,逮捕の要件を無制限に拡大するとはいえないから,所論①は採用できない。なお,所論は,被告人が現行犯逮捕されて連行されるのか任意に同行するのかを警察官から告げられることは刑事手続における被疑者の防御の根本に関わり,憲法31条の適正手続の中核をなすから,上記逮捕手続は違法であると主張する。確かに,被告人は,亀有警察署に連行される当時,その身体に直接的な支配の設定を受けておらず,現行犯逮捕された旨告げられてもいなかったから,自らが現行犯逮捕されたことに気付いていなかったものである。しかし,被告人の原審公判供述や一色の原審公判証言によれば,被告人は,当時,進んで警察署に出頭して事情を説明する意思であった(398丁)し,一色は,被告人に逃走を企てたり暴れたりする様子がうかがわれなかったので手錠等を使用せず(60丁),その場で逮捕事実を告げると取り乱すおそれがあるので告げなかった(105丁)という経緯が認められる。警察官による物理的な力の行使は,謙抑的になされるべきであるから,警察官が現行犯逮捕された被疑者を受け取り,警察署に連行する際,常にその身体に直接的な支配を設定すべきとはいえないし,被疑者には警察署に連行された後弁解録取手続が予定されているから,連行される際に現行犯逮捕されたことを伝えなければならないともいえない。本件現行犯逮捕手続に所論の違法は存しない。
(3) 弁解録取手続について
上記認定のとおり,被告人は,本件当日午後3時15分ころ,六田警察官に引致されて,本件の経緯,状況につき,黙秘権の告知を受けることなく複数の警察官の取調べを受けた後,午後3時55分ころ,六田から本件マンションで春野に逮捕されたことを告げられるとともに,引き続き黙秘権の告知を受けることなく被疑事実の要旨と弁護人が選任できる旨を告げられて弁解を聴取され,弁護人の選任を希望して休憩した後の同日夜,五木警察官の取調べを受け,その際,黙秘権の告知を受けたという経緯が認められる。そうすると,刑訴法216条により準用される同法203条1項は,逮捕された被疑者を受け取った司法警察員は「直ちに」弁解録取手続を行うべき旨を規定しているから,六田が被告人を受け取ってから弁解録取手続を開始するまでに約40分間が経過していた点は適切さを欠くものの,本件捜査手続を違法とするほどの時間の経過とはいえない。また,刑訴法203条1項の弁解録取手続自体は,取調べではなく,同法198条2項所定の黙秘権の告知まで要請されるものではないと解される(最判昭和27年3月27日刑集6巻3号520頁)ものの,被告人に対する弁解録取手続は,その前に行われていた事実上の取調べに引き続いて行われており,それらは一連のものと認められるから,これらの経過に照らすと,黙秘権を告知することなくこれらの一連の手続が行われたことは不適切な取扱いといわざるを得ない。しかし,弁解録取手続に先立つ取調べは,複数の警察官が途中の中断を含めて(401丁,424丁)40分間程度行ったにすぎず,六田が作成した弁解録取書(甲51)も,被告人の簡単な供述を内容とするものにすぎないから,六田による弁解録取手続やそれに先立つ取調べに重大な違法があるとはいえず,所論②は採用できない。
(4) 捜査比例の原則との関係等について
関係証拠によれば,春野の110番通報を受けて多数の警察官が臨場したほか,多数の警察官を動員して本件マンションの実況見分が実施され,更に被告人の自宅を捜索するなどしたことが認められる。しかし,本件犯行の経緯,状況,共犯者の存否等を捜査するために必要かつ相当な捜査を遂げることは,実体的な真実の発見のために捜査機関に許容されているところであって,上記の程度の捜査を実施することが違法であるとは到底いえない。また,上記のような本件捜査やこれに引き続く本件公訴の提起が日本共産党をねらい打ちにするというような動機,目的の下になされたものと疑うべき証拠も存しない。所論は採用できない。
(5) 結論
以上によれば,本件の捜査や起訴の手続に本件公訴の提起を無効ならしめるような重大な違法や公訴権の濫用は存しない。
(法令の適用)
被告人の判示行為は,刑法130条前段に該当するので,所定刑中罰金刑を選択し,所定の金額の範囲内で,被告人を罰金5万円に処し,同法21条を適用して,未決勾留日数のうちその1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分をその刑に算入し,原審における訴訟費用は,刑訴法181条1項本文により,被告人に負担させることとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田修 裁判官 稗田雅洋 裁判官 吉井隆平)
*******
政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
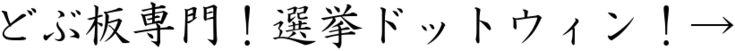




この記事へのコメントはありません。