
政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
裁判年月日 平成27年 5月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)21209号
事件名 株主代表訴訟事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA05288001
裁判経過
控訴審 平成28年 7月19日 東京高裁 判決 平27(ネ)3610号 株主代表所掌控訴事件
出典
判時 2355号82頁<参考収録>
金商 1472号34頁
資料版商事法務 377号185頁
評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 3168号(旬刊商事法務2076号)
田上雄大・月刊税務事例 48巻7号57頁
参照条文
政治資金規正法8条の2
政治資金規正法21条1項
政治資金規正法26条1号
民法644条
会社法330条
会社法355条
会社法423条1項
裁判年月日 平成27年 5月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)21209号
事件名 株主代表訴訟事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA05288001
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,a株式会社に対し,458万5000円及びこれに対する平成23年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,a株式会社(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,主位的には,本件会社が政治資金規正法(以下「法」ということがある。)8条の2所定の政治資金パーティー(以下「政治資金パーティー」という。)のパーティー券(以下「パーティー券」という。)を,出席の予定がないのに購入したことが,政治資金規正法上の「寄附」に当たり,会社が政党及び政治資金団体以外の者に対して寄附をすることを禁じている法21条1項に違反するものであると主張し,予備的には,パーティー券の購入を所管する取締役には,確実に出席が見込める枚数の限度でのみパーティー券を購入すべき義務,あるいは,国会議員からの違法な便宜供与を受けるなど不当な目的でこれを購入してはならない義務があるのに,これに反してパーティー券を購入した被告には善管注意義務違反があると主張して,パーティー券の購入に係る業務を所管する部署の担当取締役であった被告に対し,会社法847条2項に基づき,同法423条1項に基づく損害賠償として,出席する予定がないのに購入したパーティー券の代金相当額である458万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を本件会社に対して支払うことを求める株主代表訴訟の事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等を掲記したもの以外は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 本件会社は,平成22年4月1日に相互会社から株式会社に組織変更し,同日,その株式を東京証券取引市場第一部に上場した,生命保険業を主たる業務とする株式会社である。(乙1)
イ 原告は,平成23年1月27日時点において本件会社の株式を6か月以上継続して保有している株主である。
ウ 被告は,平成13年に本件会社の取締役に選任され,平成16年4月からは常務取締役,平成19年7月からは取締役常務執行役員,平成20年4月からは取締役専務執行役員,平成22年4月からは代表取締役社長の地位にあった者である。被告は,取締役選任後から平成22年3月までの間は調査部を担当していたが,同部は所管省庁との折衝や政治対応をその業務の一部としていた。(乙16,17)
(2) 本件会社は,別紙1の「開催日」欄の日に行われた同「議員」欄記載の国会議員の政治資金パーティーについて,同「枚数」欄記載のパーティー券を購入し,同「金額(万円)」欄(表の左から4列目のもの)記載の金額の支出をした(ただし,同表においてアルファベットで表示された議員は,A,B,C,D,E,F,G,H又はIの各国会議員のいずれかを指し,これらの議員に関する政治資金パーティーの日は明示されていない。)。(乙25,26,弁論の全趣旨)
(3) 本件会社が平成16年度(本件会社の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までである。)から平成22年度までの間に購入した,国会議員又はその政治団体が開催する政治資金パーティーのパーティー券の各年度ごとの合計額は,1224万7000円(平成22年度)ないし1602万7000円(平成18年度)であった。(乙1)
(4) 原告は,平成23年2月25日,本件会社に対し,平成19年度以降のパーティー券の購入等に関し,被告に取締役としての善管注意義務違反があるとして,被告の責任を追及する訴えを提起することを請求したが,本件会社は被告に対してその責任を追及する訴えを提起しなかった。(甲2から5まで(枝番号のあるものはこれを含む。))
(5) 原告は,平成23年6月27日,本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2 争点
(1) 本件会社によるパーティー券の購入が,政治資金規正法上の「寄附」に該当するか(主位的主張)
(2) 本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入したことについて,被告に善管注意義務違反があるか(予備的主張)
(3) 損害額
3 争点(1)に関する当事者の主張
(1) 原告
ア 法21条1項,26条1項は,株式会社が特定の国会議員個人に対して「政治活動に関する寄附」(以下,政治資金規正法上の寄附を「「寄附」」ということがある。)をすることを刑罰によって禁止している。そして,法4条3項は,「寄附」とは,金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は交付で,党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうものと定め,「債務の履行としてされるもの」は「寄附」には該当しないとしているが,形式的には「債務の履行」に該当するものであっても,対価性がないものなど,社会通念上実質的に寄附と認められるものは,「寄附」に該当すると解される。
パーティー券の購入代金は,形式的には政治資金パーティーに出席する対価であって,その支払は「債務の履行」であるが,当該支払が社会通念上実質的には寄附と認められる場合には,パーティー券の購入代金には対価性がなく,「寄附」に該当する。パーティー券は,政治資金パーティーに出席することを予定して購入するものであるから,通常,パーティー券は出席予定者の人数分だけ購入するものであり,仮に購入したパーティー券の中に出席することを予定しない分が含まれている場合には,政治資金パーティーの主催者(以下「主催者」という。)にとっては,その分の購入代金の贈与を受けたのと同じ結果になる。そうすると,主催者が贈与を受けるのと同じ結果となることを認識しながら出席を予定しないパーティー券を購入することは,購入の時点でパーティー券購入代金の対価を得ることを放棄しているのであるから,社会通念上,実質的には,当該パーティー券の購入代金を贈与したのと同視されるべきである。そして,金銭の贈与は,「寄附」に該当するから,贈与と同視されるべき出席を予定しないパーティー券の購入代金の支払も,社会通念上実質的には寄附であると認められ,その購入代金の支払は「寄附」に該当する。
イ 本件会社は,国会議員側からの依頼に基づき,出席予定人数を定めないままパーティー券を購入しており,実際にパーティーに出席する人数は多くても5人であったから,実際には,5枚を超える部分のパーティー券はそもそも出席を予定しない分として購入していたものである。
そうすると,別紙1の「5枚超枚数」欄記載の各パーティー券(以下「5枚超部分」という。)は,各政治資金パーティーについて本件会社において出席を予定していなかった部分であるから,その代金(同「金額(万円)」欄(表の右端のもの)記載の金額)の支払は,社会通念上実質的にみれば,主催者に対する金銭の贈与と同視されるのであり,「寄附」に該当する。
したがって,本件会社がした5枚超部分の購入は,法21条1項に違反する。
ウ 被告は,本件会社の調査部担当取締役として,特定の国会議員のパーティー券を購入するに当たり,その購入代金が「寄附」に該当しないように注意すべき立場にあった。そして,パーティー券の購入が「寄附」に該当し得ることは文献でも紹介されているのであり,特定の政治家からパーティー券を継続的に購入していたことからすると,被告には出席を予定しないパーティー券の購入が「寄附」に該当するか否かを十分に検討する機会があったことは明らかである。また,被告は調査部長に就任して以来,調査部門を統括する立場にあったのであるから,本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入していることを認識していたことは明らかである。したがって,被告が,法令違反を認識し得なかったとはいえない。本件会社においては,形式的に法の手続に従っておけば「寄附」には該当しないという安易な誤解の下,出席を予定しない分のパーティー券の購入を続けていたのであり,この点について責任者である被告が法令違反を認識し得なかったとはいえない。
エ したがって,被告は,法21条1項に違反して本件会社に違法な支出をさせ,損害を生じさせたのであるから,会社法423条1項に基づき,本件会社が被った損害を賠償する義務を負う。
(2) 被告
ア 現在の政治資金規正法は,パーティー券購入代金を「寄附」と峻別した上でパーティー券の購入額の上限を150万円とする規定(法22条の8)を置いている。これらの規定は,平成4年の改正前は,政治資金規正法にパーティー券の購入制限の規定がなかったため,購入するパーティー券の対価が社会常識の範囲内をはるかに超えたり,その購入枚数が出席を前提とした妥当なものでない場合は,「寄附」に該当するという解釈で対応が図られていたのに対して,パーティー券の購入代金がいくらを超えれば社会常識の範囲を超えるのか,購入枚数のうち何割程度を下回る参加になれば社会常識の範囲を超えるのかといった点は,社会常識の内容が不明朗であることもあって,解釈が困難であるため,この点に関する準則を定める趣旨で設けられたものである。このように,国会は,現行の政治資金規正法の立法時において,パーティー券の購入額と政治資金パーティーへの参加の問題の両方を含めて議論した上で,最終的に,パーティー券の購入額の上限の規定のみを設けることによって議論を収束させたのであり,現行の政治資金規正法は,パーティー券購入者が政治資金パーティーの全てについて参加したか否かを問題としていない。
また,政府も,パーティー券の購入代金が「寄附」に該当しないという解釈を何度も確認しており,当該解釈に当たり,購入したパーティー券の全てについて政治資金パーティーに参加することといった条件を付したことはないのであって,政府は,政治資金パーティーへの参加の要否の点を問題とすることなく,パーティー券の購入代金は「寄附」に該当しないと解釈している。
さらに,パーティー券の購入が「寄附」に該当すると,主催者側にも1年以下の禁固又は50万円以下の罰金という罰則が科されることになるところ,主催者がパーティー券の販売をする段階でパーティー券購入者が出席を予定しているかどうかを判別することは不可能であり,そうであるにもかかわらず,出席の予定があるかどうかというパーティー券購入者側の事情でパーティー券の購入が「寄附」となり,主催者に罰則が科せられ得るとすると,パーティー券の販売の法的安定が著しく害され,政治資金パーティーの開催に対する委縮効果が生じ,結果的に政治資金パーティーを開催すること自体が不可能となる。
次に,政治資金規正法は,本人以外の名義又は匿名でパーティー券を購入することを禁じているところ(法22条の8,22条の6第1項),個人であっても,上記のとおり150万円までのパーティー券の購入を認めており(法22条の8),仮にパーティー券が1枚2万円であれば,個人が最大75枚のパーティー券を購入することを明示的に許容しているのであって,パーティー券購入枚数と出席予定者の厳密な1対1対応を求めない規定を設けているのであり,出席を予定しないパーティー券の購入が「寄附」に当たると解するのは,現行の政治資金規正法の規定と矛盾するものである。
加えて,政治資金規正法は,法人その他の団体が負担する党費又は会費は「寄附」とみなすという規定(同法5条2項)を設けているように,「寄附」とみなすべき支出については,その旨の明確な規定を置いており,実際,現行の政治資金規正法の起草者は,パーティー券の購入代金を「寄附」とみなすについては法律上の特別の擬制をしなければならないと解しているし,平成5年には,日本共産党が,政治資金規正法に政治資金パーティーの収入を「寄附」とみなす規定を設ける法案を提出したことがある。このような国会での議論及び法案の提出は,現行の政治資金規正法においてはみなし規定がなければ一定の類型の支出を「寄附」とみなすことができないことを示している。そして,同法には,購入したパーティー券のうち出席しなかった分を「寄附」とみなすという規定は存在しない。
以上によれば,出席を予定しない分のパーティー券の購入が「寄附」に当たると解することはできない。
イ また,本件会社は,結果的には出席人数を確保できずに購入した枚数の全部について参加しきれなかったことはあっても,事前の購入段階で,出席を全く想定せずにパーティー券を購入していたということはない。
ウ よって,本件会社によるパーティー券の購入は,「寄附」に該当しない。
4 争点(2)に関する当事者の主張
(1) 原告
ア パーティー券の購入は,その程度及び態様によっては,政治家との癒着,政治資金規正法との抵触等の問題が発生しかねない危険性を有する行為である。したがって,パーティー券購入について決定し,監督すべき立場にある被告において,極めて慎重に判断すべきものであり,パーティー券の購入に際して,過去の政治資金パーティーへの出席人数及び出席可能な人数について,資料を収集し,分析し,検討を行うことが不可欠である。そして,過去の出席実績に照らして確実に出席が見込まれる枚数の限度でのみ購入し,いやしくも,パーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」にならないよう,また,違法な便益供与を得ることを目的とした購入を行わないよう,慎重に判断して決定することが求められる。
イ しかるに,被告は,過去の実際の出席人数を調査,検討していなかった。また,本件会社において,出席予定である政治関係の担当者は2名であり,被告を含めても確実に出席が見込まれる人数は3名であったところ,本件会社は,10枚にも上るパーティー券を多数回にわたって購入していたものであり,被告が出席予定人数を検討していなかったことは明らかである。
さらに,パーティー券の購入は,一部の親密な国会議員から,職務上得た情報の事前通告,保険業界に生じた保険金の不払等の問題に関して国会において行われた参考人招致に係る質疑時間の変更,国会における発言,他の議員の説得工作,保険金の不払等の問題に関する行政処分についての金融庁担当者への働きかけ等,国会議員の職務上の地位に基づく具体的な便益供与を目的としたものである。したがって,パーティー券の購入と当該便宜供与との間に個別具体的な関連性が認められないとしても,そもそも法律上保護されない利益を得るために不当な目的で購入したものであるから,パーティー券の購入には何ら合理性がない。
したがって,5枚超部分の購入は,パーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」を行い,違法な便宜供与を得るために不当な目的をもって行われたものであり,著しく不合理である。
ウ 被告は,平成9年4月に本件会社の調査部長に就任して以来,調査部門を統括する立場にあったから,過去のパーティー券購入金額及び購入枚数,実際の出席人数について認識する立場にあった。加えて,被告も政治資金パーティーに参加していたから,少なくとも,自らが出席した政治資金パーティーについて,購入枚数に満たない出席人数であったことは当然に認識していた。また,自らが出席していない政治資金パーティーについても,同様に最大でも5名しか出席していなかったという概略は当然に予見できており,担当者に確認すれば容易に確認できたものである。
したがって,被告は,出席が予定されていないパーティー券を購入することを認識していた。
エ 被告が,出席が予定されていないパーティー券を購入することを認識していたことからすれば,被告は,担当者に指示するなどして,過去の出席人数を確認させ,出席予定人数を検討させた上で,出席可能人数に見合う枚数を購入するように決定し,又は担当者に指示すれば,出席が予定されていないパーティー券の購入は容易に解消できた。しかるに,被告は,漫然とその購入を継続したものであるから,被告には回避義務違反もある。
オ 被告に,出席が予定されていないパーティー券を購入することについての認識可能性がなかったとしても,被告の地位に照らせば,配下の従業員が違法行為をしないよう監督すべき注意義務がある。しかるに,被告は,パーティー券の購入枚数と出席人数を確認,報告させることなく,購入枚数と出席人数とのかい離を解消させずに配下の従業員に漫然とパーティー券を購入させ続けて違法な支出を招いたのであるから,被告は,監督義務を怠っていた。
カ よって,被告には,出席が予定されていないパーティー券の購入について,善管注意義務違反がある。
(2) 被告
ア 前記3(2)アのとおり,購入したパーティー券のうち,出席予定を超えた分が全額「寄附」となり,政治資金規正法に抵触するということにはならないから,過去の出席人数や出席予定人数の調査をする必要はない。常識的に見て出席の余地がおよそないような極端に多量のパーティー券を購入するような場合には,政治資金規正法違反の問題が生じ得るが,本件会社においては,10枚を超えるパーティー券は購入されていなかったし,購入したパーティー券の枚数に見合った人数が出席できるように努めていたものであるから,過去の出席人数等を調査しなくても,同法違反の問題は生じない。
イ また,国会議員からの便宜供与に該当するような行為はなく,パーティー券の購入と国会議員との行為との間に関連性はない。さらに,上記のとおり,本件会社によるパーティー券の購入は,「寄附」に該当するようなものではなく,購入したパーティー券の全てについては出席できなくても,平均的なパーティー券購入枚数からすれば,総体としてみれば購入したパーティー券を全て利用していたこと,購入枚数の多いパーティーについても,できる限り枚数に見合った人数が出席できるよう努めていたこと,10枚を超えるパーティー券は購入されておらず,大量の欠席者ができるような態様でのパーティー券の購入はされなかったという事情も存在するのであるから,本件会社がパーティー券を購入する経営判断を行ったことは,不合理なものではない。さらに,本件会社は,民主政治の発展のため社会の構成員たる企業が担うべき社会貢献の一環としてパーティー券を購入したものであり,そのようなパーティー券の購入を行った被告の判断に不合理な点はない。
ウ したがって,被告に善管注意義務違反が成立する余地はない。
5 争点(3)に関する当事者の主張
(1) 原告
ア 主位的主張に係る損害額
被告の法令違反によって本件会社が被った損害額は,出席が予定されていなかった分(実際に出席しなかった分)のパーティー券の購入代金である。そして,本件会社において,実際にパーティーに出席していたのは最高5名であったから,5枚超部分は出席が予定されていなかった分のパーティー券である。したがって,5枚超部分の購入代金(別紙1の「金額(万円)」欄(表の右端のもの))の合計が,被告の法令違反による損害となるところ,その購入代金額の合計額は,458万5000円である。
イ 予備的主張に係る損害額
被告の善管注意義務違反によって,本件会社は何ら対価関係が認められない出席予定枚数を超えるパーティー券の購入を継続していたものであるから,前記アのとおり,少なくとも5枚超部分の購入代金である合計458万5000円が,被告の善管注意義務違反による損害である。
(2) 被告
争う。
本件会社によるパーティー券の購入は政治資金規正法上の「寄附」に該当せず,対価性のある合理的な行為であったから,パーティー券の購入は,本件会社に何らの損害も生じさせていない。
第3 当裁判所の判断
1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) パーティー券の購入は,本件会社の社内規定上,政治献金に準ずるものとして総務部の分掌業務とされていたが,パーティー券の購入に関する一般的な規則は特に定められておらず,次のような事務手続の流れで,個別に総務部に事前申請が行われ,同部の承認の下に購入されていた。(乙1,証人J,証人K)
ア 調査部は,毎年1月頃,次年度のパーティー券の購入に係る予算枠の案を作成して総務部に提出し,総務部が収益管理部の承認を得ることで予算枠を確定させる。
イ 国会議員の秘書から,調査部の政治担当者に対して,通常,政治資金パーティー開催の1か月程前に,パーティー券の購入が依頼される。同担当者は,当該時点での社会情勢,経営状況,他社の動向,他の議員とのバランス,議員の政治理念や実際の政治活動の内容,過去の購入実績等を考慮した上で,パーティー券を購入すべきか否か,購入するとして何枚購入するかについて,上記予算枠の範囲内で検討する。
ウ その検討の結果について調査部内での決裁が完了すると,調査部は総務部に対して,パーティー券の購入を申請する。総務部は,これを承認する場合には,同部において購入手続を行う。
エ 調査部の担当取締役であった被告に対しては,上記予算枠が確定した時点でその旨の報告がされるが,個別のパーティー券の購入に関する決裁は調査部長において行っていたため,平成19年度から平成22年度までの間,被告が個別のパーティー券の購入についての上記決裁に関与することはなかった。
(2) 本件会社は,全てのパーティー券について,前項の手続により購入していたものであり,その購入に際して,簿外資金等の出所の不透明な金員を用いたり,代金の支払に際して不自然な作為が介在しているといった形跡はない。(乙1,証人J)
(3) 本件会社が購入していたパーティー券は,概ね1枚1万円ないし3万円程度であったところ,平成19年度から平成22年度までの年度ごとの政治資金パーティー1回当たりの平均購入額は約3万9000円ないし約6万円であった。一方,1回の政治資金パーティーについて20万円を超えて購入すると,政治資金パーティーの収支報告書に購入者の住所,氏名等が記載されることになることや,多数のパーティー券を購入してもそれに見合った出席者を確保できないことから,資金効率をも考慮して,1回の政治資金パーティーについてのパーティー券の購入金額は20万円を限度とし,10枚を超えてパーティー券を購入することはなかった。(乙1,18,証人J,証人K)
(4) 本件会社が購入したパーティー券に係る政治資金パーティーには,特段の事情のない限り,本件会社の調査部所属の従業員が1名又は2名が必ず出席し,これに加えて被告や調査部の他の従業員が出席することがあり,出席者数としては2,3名のことが多かった。これを超える数のパーティー券を購入した場合において,1回の政治資金パーティーに出席するのは5人程度までであることが多かったが,7,8名が参加する場合もあった。(証人J,証人K)
(5) 社団法人生命保険協会(以下「生保協会」という。)は,日本において免許を受けて事業を行っている生命保険会社の全てが加盟している社団法人であるところ,生保協会の協会長は,いわゆる生命保険大手4社と呼ばれる本件会社,b保険相互会社,c保険相互会社,d保険相互会社の社長が交代でこれを務める慣例となっていた。
本件会社の社長は,平成18年7月から平成19年7月までの期間及び平成22年7月以降に,生保協会の協会長を務めていた。
本件会社においては,その社長が生保協会長を務めている期間には,パーティー券の購入枚数を例年よりも増加させる慣行があった。(乙1,証人K)
(6) 平成17年から平成19年にかけて,各生命保険会社において,本来支払うべき保険金の支払がされていない事案や支払漏れ,請求案内漏れの事案が発覚し,報道等がされることとなった(以下,これらを併せて「保険金支払問題」という。)。
本件会社調査部の担当者(以下「本件担当者」という。)は,平成19年4月頃,保険金支払問題に関する金融庁への対応や衆議院財務金融委員会での参考人質疑に関する対応を巡って,関係するe党所属の複数の国会議員を訪問し,同議員らから上記参考人質疑に関する情報を得たり,同議員らに対して本件会社の保険金支払問題に対する取組の状況を説明するなどしたほか,平成20年には,同議員らから金融庁の本件会社に対する業務改善命令の発令に関する情報を得るなどした。
上記参考人質疑において招致される生命保険業界の参考人について,当初は,同時に招致される損害保険業界の参考人よりも多く招致されることが提案されていたところ,本件担当者が,L議員(以下「L議員」という。),M議員(以下「M議員」という。)及びN議員に,参考人質疑について生命保険業界と損害保険業界の招致人数及び質疑時間を同一にすることを要望したほか,O議員(以下「O議員」という。)に上記の要望についてL議員を説得することを依頼し,O議員とL議員との協議の結果,生保協会及び社団法人日本損害保険協会の両協会長にそれぞれ1時間ずつの質疑を実施する方向で臨むこととなり,上記委員会理事懇談会での協議を経て,最終的に当面行われる参考人質疑においては上記の内容とすることが決まった。また,参考人質疑に先立ち,本件担当者が,P議員(以下「P議員」という。)に対して,質問内容の事前通告に消極的であった国会議員に対する説得を依頼し,P議員の取り次ぎにより事前通告を受けることができた。本件担当者がM議員を訪問した際に,M議員から,L議員には随分頑張ってもらった,くれぐれもよろしく頼むとの発言がされた。
そして,平成19年5月18日に上記参考人質疑が実施され,当時の生保協会の協会長であった本件会社の代表取締役Q(以下「Q取締役」という。)が損保協会の協会長と共にそれぞれ1時間の質疑を受けたが,その際,Q取締役が,本件会社における不適切な保険金の不払や支払漏れの発生率が0.05パーセントである旨説明したところ,L議員は,数字としては比較的少ないように感じるが,たとえ0.05%でも国民の皆さんそれぞれにとっては大変重大なことであると思うので,限りなく0に近づける姿勢をしっかりと貫いていただきたい旨発言し,また,本件会社が導入していた保険金の支払を促進した営業職員に対する奨励金支給制度について,よくそこまでやったなという感じがしないわけでもない,ぜひそうしたインセンティブをこれからも続けてほしい,生保協会長として業界の他の会社にもそれを勧めていただければありがたいとの発言をした。(甲16の5,乙1,証人J,証人K)
(7) 本件会社は,前記(6)において本件担当者が接触した国会議員(L議員を除く。以下「本件関係議員」という。)について平成19年度の前後を通じ継続的にパーティー券の購入をした(ただし,購入したのは本件関係議員のみに限られない。)。
L議員に関しては,同議員の秘書の依頼を受けてパーティー券を購入するようになり,平成19年度から平成22年度にかけて1年当たり2万円ないし8万円のパーティー券を購入した。ただし,このパーティー券に係る政治資金パーティーは,e党愛知県支部連合会等が主催するものであって,L議員又はその政治資金管理団体が主催するものではなかった。(乙1)
(8) 本件会社は,財務金融分野に造詣の深い国会議員や保険会社として関心を有している国会議員を中心に,一定の国会議員を,「主要議員」,「友好議員」等の名称で分類した表(以下「本件分類表」という。)及び上記「主要議員」等の定義やこれに対する本件会社側の取組姿勢やパーティー券対応の方針についてまとめた表(以下「本件定義表」という。)を作成していた。本件定義表には,例えば,「主要議員」について,対象議員として「業界に対する理解が深く,様々な場面での活躍,業界のために資する助言等が引き続き期待できる議員」とし,取組姿勢として「親密な関係を維持し,更なる理解を深める」,パーティー券対応として「原則として,現状維持とするが,各社の負担が増えないように留意する」といった内容の記載がある。(甲12の1・2,乙2,証人J,証人K)
(9) 本件会社の平成19年度から平成21年度の経営成績及び財務状況は,別紙2のとおりである。(乙1,7)
2 争点(1)(本件会社によるパーティー券の購入が,政治資金規正法上の「寄附」に該当するか)について
(1) 政治資金規正法は,「会社,労働組合,職員団体その他の団体は,政党及び政治資金団体以外の者に対しては,政治活動に関する寄附をしてはならない。」旨を定めるとともに(法21条1項),「何人も,政治資金パーティーの対価の支払をする場合において,一の政治資金パーティーにつき,150万円を超えて,当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。」と定めており(法22条の8第3項),これらの定めによれば,パーティー券の購入は,同法上,原則として「寄附」には該当しないものと解される。もっとも,「寄附」とは,「金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は交付(以下「金銭の交付等」という。)で,党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と定められているところ(法4条3項),形式的にはパーティー券の購入に伴う代金の支払であっても,社会通念上,その対価的意義を著しく損なう支出であると評価される場合には,当該支払を債務の履行とみることはできないというべきであるから,当該支払は「寄附」に当たるというべきである。
これを本件についてみるに,一般に,政治資金パーティーを開催する場合には,その主催者は,その参加者数(購入されたパーティー券の数)に応じた場所を用意し,飲食物その他の応接の準備を行い,その規模に応じた費用を支出するものであるところ,証拠上,本件に係る政治資金パーティーにおいて購入されたパーティー券の数に応じた相応の準備と支出がされていなかったことをうかがわせる事情はない。そして,前記1(3)及び同(9)において認定した本件会社が購入したパーティー券の数量と本件会社の経営成績及び財務状況から伺われる本件会社の規模を踏まえれば,本件会社の購入したパーティー券の枚数や金額自体が特に不自然,不相応であるとは認められない一方で,同(1)から同(3)までの認定事実によれば,本件会社においては,上記パーティー券の購入を正式な社内手続を経て行っており,適法,適正なパーティー券の購入となるように配慮していたことが認められる。そして,同(4)において認定した本件会社の政治資金パーティーへの出席状況及び上記の本件会社の規模を踏まえれば,およそ購入枚数に見合うだけの人数の参加が想定できないような数のパーティー券を購入したものとは認められない。これらの事情を考慮すると,本件会社による5枚を超えるパーティー券の購入が,社会通念上,対価性を著しく損なっていると認めるには至らないから,「寄附」に当たると認めることはできない。
(2)ア 原告は,出席を予定しないパーティー券の購入代金の支払は,主催者にとっては,その購入代金分の贈与を受けたのと同じ結果となり,これを認識しながら出席予定のないパーティー券を購入することは,その購入の時点でパーティー券購入代金の対価を得ることを放棄しているのであるから,社会通念上実質的には当該パーティー券の購入代金を贈与したと同視されるべきであると主張し,本件会社は,もともと5人を超える出席を予定せずパーティー券を購入していたから,5人超部分については、社会通念上実質的には主催者に対する金銭の贈与と同視すべきである旨主張する。
イ しかし,政治資金規正法の規定及びその立法経緯を踏まえれば,政治資金パーティーにおいては,その対価として支払われる金銭が同パーティーの開催費用として全て費消されるわけではないことを前提としつつ,これを規制する方法として1回の政治資金パーティーの開催ごとに同一の者からの支払額の総額を定めたものということができる。そして,同法は,規制方法として上記の方法のみを規定していること,その規制される金額が150万円と相当高額であり,通常想定される政治資金パーティーの一人当たりの対価からすれば数十人分以上の対価に相当し,さらには上記金額の規制は個人にも適用されるものであること等,本件に顕れた同法における政治資金パーティーの規制の在り方を踏まえると,同法は,政治資金パーティーにおいて,その対価の支払時において,支払に相当する参加者が具体的に予定されていることを要するとしたものとは解されない。
ウ また,前記1における認定のとおり,本件会社においては,購入したパーティー券に係る政治資金パーティーについて,出席する本件会社の役員及び従業員は5名程度までであり,10人分のパーティー券を購入した場合であっても10人で出席したことはないこと,また,パーティー券の購入に当たって具体的な出席人数を考えた上で購入していたわけではないことが認められるが,一方で,本件会社においては,できる限り購入したパーティー券について出席するように努めており,7,8人出席したものもあったというのであって,本訴訟において原告が主張する政治資金パーティーのそれぞれについて本件会社側の出席者が何人であったか,証拠上明らかではないことにも鑑みると,本件会社が,購入時において,出席することを全く想定もしない数のパーティー券の購入をしたものとまでは認めるに至らないのであって,原告の指摘する事情を踏まえても,上記認定を覆すには至らない。
エ よって,原告の主張は採用できない。
オ なお,原告は,本件会社が5枚超部分を購入するにあたり,本件会社側は5名を超える分は出席を予定しておらず,主催者側もパーティーの出席者名や出席者数を確認しており,それまでの出席状況から見て5人を超える出席がされないことを認識しているから,出席を予定しないパーティー券の購入は,パーティー券の購入について通謀虚偽表示をするような場合に当たるとも主張する。
しかし,政治資金パーティーの主催者と本件会社の担当者が,はじめから出席することがないとわかった上でパーティー券を購入することについて通謀ないし認識を共有していたことを示す証拠はない。そして,実際の出席人数から直ちに,パーティー券の購入の際に購入者に出席の予定があったかどうかを知り得るものではないし,上記のとおり,本件会社が適法にパーティー券を購入できるのは実際の参加予定数として具体的に想定された分のみであるとは解されず,実際に本件会社が購入したのも会社の規模等に照らし不相応なものではなかったことをも踏まえると,従前,購入枚数分の出席がなかったという事情があったからといって,主催者において,パーティー券の購入者が出席予定のないパーティー券を購入していると認識し得ると直ちにいうこともできない。
(3) 以上によれば,本件会社が行ったパーティー券の購入が,政治資金規正法上の寄附に当たるということはできないから,原告の主位的主張は採用できない。
3 争点(2)(本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入したことについて,被告に善管注意義務違反があるか)について
(1)ア 原告は,①本件会社がパーティー券を購入する際に,被告は政治資金パーティーへの出席予定人数を検討せず,また,過去の出席人数を調査してもいなかったものであって,パーティー券の購入は過去の実績に照らして確実に出席が見込まれる限度で購入していたものとは認められず,パーティー券の購入は,これに仮託して実質的な「寄附」を行ったものであること,②本件会社は,違法な便宜供与を得るために不当な目的をもってパーティー券を購入したものであることからすれば,パーティー券の購入は著しく不合理であり,被告には取締役としての善管注意義務違反があると主張する。
イ このうち,①については,前記2における認定,説示のとおり,本件会社が行ったパーティー券の購入は「寄附」に当たるものではなく,パーティー券の購入に仮託して「寄附」を行ったものであるともいえない。また,上記説示のとおり,本件会社において出席することが全く想定もされないような数のパーティー券を購入したものとは認められないし,上記本件会社の規模等や本件会社が1回の政治資金パーティーについて購入したパーティー券の枚数等に照らしても,その購入数が特に不相応なものであったとは認められないのであって,その購入は合理的な範囲で行われていたと認めるのが相当である。
ウ また,②について,前記1(6)のとおり,被告や調査部の従業員が,国会議員に対して,保険金支払問題や国会での参考人質疑に関し,本件会社側の説明及び要望等を述べたこと,国会議員らがその意見や要望に沿うとも受け取り得る言動を行ったり,国会議員らから本件参考人質疑や保険金支払問題に関する金融庁による本件会社に対する行政処分についての情報を得たりしたことが認められ,また,本件会社のパーティー券購入の対象となった国会議員に本件関係議員が含まれていること,L議員に関しては平成19年度以降パーティー券が購入されたことが認められる。
しかし,前記認定のとおり,L議員に関するパーティー券はL議員又はその政治資金管理団体が主催する政治資金パーティーのものではないし,そのことを置くとしても,その購入額は1年当たり2万円から8万円程度と少額に留まる。また,本件会社によるパーティー券の購入数が特に不相応なものであるとは認められないものであるところ,本件関係議員に対するパーティー券の購入についてみても,保険金支払問題と連動してパーティー券の購入額が増減していることを認めるに足りる的確な証拠はない(本件関係議員を含む国会議員のパーティー券の購入額は,議員によって異なるものの,おおむね平成17年頃から平成19年頃まで増加し,平成20年度,平成21年度は減少した後,平成22年度には増加している傾向がうかがわれるところ(乙1),この時期は本件会社の社長が生保協会の協会長を務めた時期であり,前記1(5)の認定事実を踏まえると,上記購入金額の増額が保険金支払問題と関連しているとは認められない。)。さらに,パーティー券の購入に当たっては社内の正規の手続を経て行っており,その資金の出所や支払方法について不自然な作為がされた証拠もない。そうすると,本件会社が,L議員及び本件関係議員を含む国会議員らからの便宜供与を受けることをことさらに期待し,それを目的としてパーティー券を購入していたと認めることはできない。
エ 以上によれば,本件会社がしたパーティー券の購入は,法の規制に従って合理的な範囲内で行われたものであって,これについて被告に取締役としての善管注意義務違反があるということはできない。
(2)ア 原告は,①M議員がした,L議員には随分頑張ってもらった,くれぐれもよろしく頼むとの発言は,本件参考人質疑に関して便宜を図ったL議員に対し,本件会社又は生命保険業界でパーティー券の購入等の利益供与を行うよう依頼をしたものであり,このような発言があることからして,本件会社と特定の国会議員との間で,便宜供与を期待してパーティー券購入等の利益供与が行われるという癒着関係が構築されていたといえる,②本件会社がパーティー券を購入した相手の多くが,金融業界に関連する部会や委員会等での活動経験が長い議員や,生命保険業界に関連する主要な役職に就いた議員であることから,本件会社がいざという時に本件会社に対する国会議員の地位に基づく便宜供与を期待する趣旨でパーティー券の購入等を行っていたことが明らかである,③本件定義表と本件分類表を併せて読めば,生命保険業界に資する助言等が期待できる議員との間の緊密な関係を維持すること等を目的として,本件会社を含む生命保険会社が,分担を決めて一定の基準に従い組織的,計画的にパーティー券の購入を行っていたことが明らかである,④国会議員との緊密な関係を維持するために,毎年1000万円以上の金銭を,組織的,計画的に特定議員に対して支払っているのであり,特に,出席を予定しないで購入したパーティー券の代金相当額458万5000円については,違法,不当な便宜供与以外には何らの対価関係も認められないから,国会議員の具体的な職務行為とパーティー券購入等との対価関係がある,⑤本件会社は,政治資金パーティーの対価として20万円を超える支払をした場合には氏名等が収支報告書に記載されることを意識し,本件会社の名称等が出ることの危惧から,購入金額を20万円に抑えていたものであり,そのような危惧を抱いていたのは違法な便宜供与を目的として購入していたからであると主張する。
イ しかし,①については,上記説示のとおり,L議員に関するパーティー券の購入は同議員に直接向けられたものではなく,また,金額も少額であることに照らすと,上記M議員の発言のみによって,本件会社が同議員からの個別具体的な便宜供与を期待して,あるいは,便宜供与への見返りとしてパーティー券を購入したと推認するには至らない。
また,②については,生命保険会社である本件会社として,関連する政党の部会や国会の委員会等での活動経験が長い国会議員や,生命保険業界に関連する主要な役職に就いた国会議員の政治資金パーティーに出席して,国会議員や関係者,出席者との情報交換ないし意見交換をしようとすることは格別不自然,不当なこととはいえず,このことから,パーティー券の購入の目的が国会議員からの個別具体的な案件における違法な便宜供与にあると断ずることはできない。
③については,政治資金規正法等の現行法令上,企業が政治資金の寄付をしたり政治資金パーティーの対価を支払うなどの政治活動に対する出捐を行ったりすること自体は許容されているところ,各企業の判断により出捐の対象やその多寡を決めて対応することが直ちに違法又は不当であるとは解されない。そして,上記認定のとおり,本件会社の購入していたパーティー券は最大でも1回当たり20万円であり,これは会社の規模等に照らして不相応なものではなく,特定の国会議員に対する出捐としても特に不相当なものとまでは認められないし,証拠(甲12の1・2,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,本件会社が本件分類表及び本件定義表の記載に従ってパーティー券を購入する国会議員やその数を決めていたともいえないから,本件分類表及び本件定義表の存在から,直ちに国会議員との間で不相当に親密な関係があったことや違法な便宜供与を受けるためにパーティー券を購入していたことまでを推認することはできない。
④については,本件会社のパーティー券の1年当たりの購入額としてみても,その規模,経営実績及び社会経済的地位に照らして合理的な範囲を逸脱することを認めるに足りる証拠はないほか,5枚超部分を含むパーティー券の購入について,政治資金規正法に違反するものとは認めるに至らないことはこれまでに説示したとおりであって,この点に関する原告の主張は前提を欠くし,その他パーティー券の購入が国会議員の具体的な職務行為と対価関係があるものであることを示す的確な証拠はない(なお,原告の請求に係る前提事実(2)摘示の国会議員と本件関係議員は3人を除いて一致しない。)。
そして,⑤については,上記のとおり1回当たりのパーティー券の購入額が本件会社の規模等に照らし不相応ではなく,国会議員ごとや年間を通じた購入総額についてもこれが不相当に高額であることを認めるに至らないことに鑑みれば,収支報告書に本件会社の名前が出ないようにすることを考慮していたとしても,そのことから直ちに,パーティー券が違法な便宜供与を目的とするものであったということはできない。
ウ したがって,原告の上記主張はいずれも採用できない。
(3) また,原告は,被告には,出席が予定されていないパーティー券の購入は解消すべきであったのにこれを怠った回避義務違反,又は配下の従業員に購入枚数と出席人数との乖離を解消させずに漫然とパーティー券を購入させ続け,違法な支出を招いた監督義務違反があると主張する。
しかし,これまでに説示したとおり,本件会社のパーティー券の購入に違法,不当な点があったとは認められないから,被告に,上記の回避義務違反や監督義務違反といった取締役としての善管注意義務違反があるということもできず,原告の主張はいずれも採用できない。
(4) したがって,原告の予備的主張は採用できない。
4 結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野寺真也 裁判官 能登謙太郎 裁判官 日下部祥史)
別紙
当事者目録
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 阪口徳雄
同 大住洋
同 金啓彦
同 前川拓郎
同 矢吹保博
同 杉村元章
同 松丸正
同 辻公雄
同 河野豊
同 古川拓
同 由良尚文
同 塚田朋子
同 富田智和
同 加藤昌利
同 白井啓太郎
同 須井康雄
同 沼田洋祐
同訴訟復代理人弁護士 笠井計志
埼玉県春日部市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 中村直人
同 仁科秀隆
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
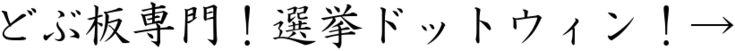




この記事へのコメントはありません。