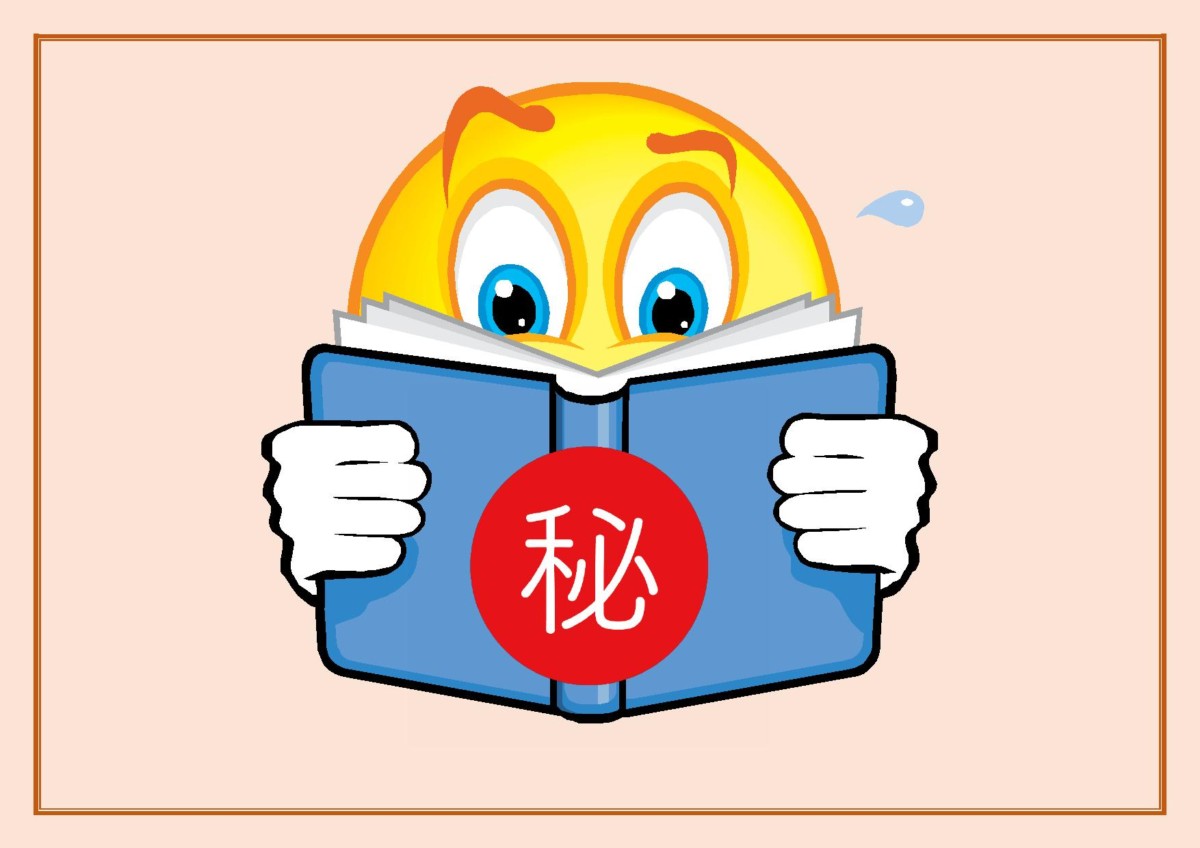
「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(26)平成30年 9月27日 東京地裁 平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(26)平成30年 9月27日 東京地裁 平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
裁判年月日 平成30年 9月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)36676号
事件名 総会決議無効確認等請求事件
文献番号 2018WLJPCA09278007
裁判年月日 平成30年 9月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)36676号
事件名 総会決議無効確認等請求事件
文献番号 2018WLJPCA09278007
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X1
東京都台東区〈以下省略〉
原告 亡X2訴訟承継人 X3
東京都大田区〈以下省略〉
原告 X4
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X5
東京都北区〈以下省略〉
原告 X6
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X7
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X8
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X9
上記8名訴訟代理人弁護士 佐賀豪
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y協同組合
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 春日秀一郎
同 國塚道和
同 神田知江美
主文
1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。
2 原告らの予備的請求をいずれも却下する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(主位的請求)
1 平成28年7月31日付け被告の臨時総会における役員選挙規約変更の決議が無効であることを確認する。
2 平成28年7月31日付け被告の臨時総会における理事としてB,C,D,E,F,A,G,H及びIを,監事としてJ及びKをそれぞれ選任する旨の決議が無効であることを確認する。
(予備的請求)
1 平成28年7月31日付け被告の臨時総会における役員選挙規約変更の決議を取り消す。
2 平成28年7月31日付け被告の臨時総会における理事としてB,C,D,E,F,A,G,H及びIを,監事としてJ及びKをそれぞれ選任する旨の決議を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,中小企業等協同組合法(以下,「組合法」という。)3条1号の組合である被告に対し,被告の組合員である原告らが,被告において完全連記式投票制を採用することは組合法1条の趣旨に反するなどとして,被告の臨時総会における理事等を改選する旨の決議等の無効確認を求めるとともに,予備的に,上記総会の招集手続が法令等に違反するなどとして,決議の取消しを求める事案である。
1 前提事実(各掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められるか,又は顕著な事実である。)
(1)被告は,昭和56年2月18日に設立した,主たる事務所を東京都中央卸売市場a市場内に置く,組合法3条1号の組合であり,東京都及び近隣県に事業場を有する,青果物の小売業を行う事業者を組合員としている。
被告の組合員数は現在,110名程度であり,a市場において,青果物に関する小売市場取引に参加するためには,同市場内の小売事業組合に所属することが求められている。
(甲1,弁論の全趣旨)
(2)原告らは,いずれも被告の組合員である(弁論の全趣旨)。
(3)平成28年7月31日付け被告の臨時総会(以下,「本件臨時総会」という。)において,第5号議案「役員選挙規約一部変更の件」(以下,「本件第5号議案」という。)及び第8号議案「役員任期満了による改選の件」(以下,「本件第8号議案」という。)が決議された(乙18の1ないし18の3)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)本件第5号議案にかかる決議について無効事由があるか。(争点1)
ア 原告らの主張
被告の役員選挙規約(以下,「本件規約」という。)13条1項3号は,投票できる人数を3人までとする制限連記式投票制を定めたものである。本件第5号議案にかかる決議は,本件規約13条1項3号を削除するものであるが,それによって,被告の定款及び本件規約において,いかなる投票制度を採用したか定めのない状態とすることは,組合法1条,33条,35条に反し,無効である。
イ 被告の主張
本件規約13条1項3号は,「最低3人に投票しなければ無効とする」との規定にすぎず,制限連記式投票制を定めたものではない。
(2)本件第8号議案にかかる決議について無効事由があるか。(争点2)
ア 原告らの主張
(ア)被告において完全連記式投票制を採用することは,組合法1条及び35条11項に反するものであるから,完全連記式投票制を前提に行われた本件臨時総会における役員選挙(以下,「本件選挙」という。)は無効である。
(イ)組合法33条1項11号は,「役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定」は定款に記載することと定めているところ,被告の定款には投票の方法についての定めがなく,当該状態で行われた本件選挙は,同法33条1項11号に反し無効である。
(ウ)本件規約には,いかなる投票制度を採用したかの定めがないところ,当該状態で行われた本件選挙は,組合法1条,33条及び35条に反し無効である。
イ 被告の主張
(ア)組合法は,最も民主的な方法である無記名投票選挙に関して,単記式か連記式か,連記式ならば完全連記式か制限連記式か,いかなる投票制度を採用するかについて,何ら規制をしていない。被告において完全連記式投票制を採用したことは同法1条及び35条11項に反するものではない。
(イ)被告の定款32条は,「役員の選挙は,連記式無記名投票によって行う(同条2項)」との規定を含む役員選挙に関する基本事項を定めたうえで,「役員の選挙に関する事項は,本条で定めるもののほか規約で定める(同条7項)」としており,組合法33条1項11号の「役員の選挙又は選任に関する規定」は既に定款に定められている。
(ウ)本件規約において,完全連記式投票制か制限連記式投票制かを定める必要はなく,本件選挙は組合法1条等に反するものではない。
(3)本件第5号議案及び本件第8号議案にかかる決議に関する取消しの訴えについて,訴えの利益があるか。(争点3)
ア 原告らの主張
本件第8号議案にかかる決議が取り消されれば,本件臨時総会で選任された役員による被告の業務執行も問題となり,新たに役員が選任されたことで当然に業務執行の瑕疵が治癒されるわけではないので,訴えの利益はなお存在している。
イ 被告の主張
被告においては,本件訴訟で取消しの対象となっている決議に基づいて選任された役員が任期満了によって退任し,平成30年5月27日付け被告の通常総会(以下,「平成30年通常総会」という。)において,新たに役員が選任された。また,同総会において,本件規約が第13条1項3号を削除した形で決議され,改めて承認を受けた。
同総会における決議は,取消しの訴えが提起されることなく確定しているため,本件第5号議案及び本件第8号議案にかかる決議に関する取消しの訴えについては,訴えの利益が存在しない。
(4)本件第5号議案及び本件第8号議案にかかる決議について,取消事由があるか。(争点4)
ア 原告らの主張
(ア)招集手続の瑕疵
平成28年7月20日付け招集通知(以下,「本件招集通知」という。)は,当時の理事長であった原告X1(以下,「原告X1」という。)の権限に基づかずに発送されているため無効である。また,本件招集通知には,完全連記式投票制を前提とした投票用紙が同封されているところ,本件規約13条1項3号を削除する旨の承認手続を経ていない段階で,同投票用紙を同封することは,あたかも被告が完全連記式投票制を採用したかの外観を組合員に与えるものであり,著しく不公正な招集手続である。
(イ)決議方法の瑕疵
投票の方法は定款記載事項であり,定款変更の手続を経なければこれを定めることができないところ,本件招集通知には,本件規約13条1項3号を削除する旨の議案しか記載されておらず,完全連記式投票制の採否について触れていない。本件第5号議案にかかる決議によって,完全連記式投票制を承認したと解することはできず,仮に,承認まで読み込むとすれば,招集通知に記載のない議案について決議したに等しく,決議の方法が著しく不公正である。
イ 被告の主張
(ア)招集手続の瑕疵
平成28年6月11日付け被告の理事会において,本件臨時総会を開催することが決定し,同決定に基づいて本件招集通知が発送された。原告X1は本件招集通知の発送を差し止めたことはなく,同人には,本件臨時総会の開催を取り消す権限もない。
また,仮に本件第5号議案が否決されるのであれば,配布した投票用紙が使用されないだけのことであり,事前に完全連記式投票制を前提とした投票用紙を配布したことが,著しく不公正な招集手続には当たらない。
(イ)決議方法の瑕疵
完全連記式投票制か制限連記式投票制かの別は定款記載事項ではない。
また,本件選挙が行われる前に,本件規約13条1項3号を削除する理由について詳細な説明があったことからすれば,決議の方法が著しく不公正とはいえない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実に加えて,証拠(甲30ないし32,乙29,30,60,61,後掲各証拠,証人G,同A,同L,原告X1本人,原告X6(以下,「原告X6」という。)本人,原告X4(以下,「原告X4」という。)本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告は,従前,地域等でまとまった「支部制」を採用しており,被告内部には「b」,「c」,「d」,「e」,「f」,「g」,「h」,「i」及び「j」支部並びに「k」支所が存在していた。その後,組合員数の減少等により支部制を維持する必要性が減少し,支部制を廃止して,10地域からなる地域制としたうえで,各地域から1名の「役員推薦会議委員」を選出することとした。そして,同委員により構成された推薦会議において,役員の候補者を決定し,総会の議決で役員を決することとなったが,事実上,10地域の各役員推薦会議委員10名が,そのまま総会の承認を経て理事となっていた。(乙2の2,弁論の全趣旨)
(2)平成27年5月24日付け被告の通常総会(以下,「平成27年通常総会」という。)において,理事の選任方法について,従来の選任制を維持するか,選挙制へ移行するかが議論され,選挙制に移行する旨の定款変更が決議された。
被告の理事会は,組合法74条の東京都中小企業団体中央会(以下,「中央会」という。)から役員選挙規約のひな型を交付され,それを基に本件規約の作成に取りかかった。被告の理事会は,同ひな型の「無効投票」の項目に「被選挙人の○人を記載したかを確認し難いもの」との記載があったことから,上記○の部分に数字を入れなければならないものと考え,組合法35条2項に「理事の定数は,3人以上とし,監事の定数は,1人以上とする」と規定されていることから,○の部分に3の数字を入れることとした。
(甲2,3,14,乙1の1,1の2,2の3)
(3)被告は,中央会から,平成27年通常総会で決議された定款について,役員の選挙に関連する条文に不足がある旨の指摘を受け,同年8月9日付け被告の臨時総会において,定款を一部変更する旨の決議を行った。
その結果,被告の定款は,以下のように規定された。
25条 役員の定数は,次のとおりとする。
1項 理事 7人以上9人以内
2項 監事 1人又は2人
32条1項 役員は,次に掲げる者のうちから,総会において選挙する。
1号 組合員又は組合員たる法人の役員であって,立候補し,又は理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
2号 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって,理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
2項 役員の選挙は,連記式無記名投票によって行う。
7項 役員の選挙に関する事項は,本条で定めるもののほか規約で定める。
(甲1,21)
(4)また,同日付け被告の臨時総会において,理事の選任方法が候補者制に決定したことにより,従前の「役員選任規約」を「役員選挙規約」に変更する必要がある旨の説明がされ,本件規約が示されたうえで,役員選挙規約変更の件が承認可決された。
本件規約は,13条において「無効投票」と題したうえで以下のように規定されている。
1項 次の投票は,無効とする。ただし,第1号の事項については書面による選挙権を行う場合は,この限りでない。
1号 所定の用紙を用いないもの
2号 記載すべき被選挙人の数を超えて記載したもの
3号 被選挙人の3人を記載したかを確認し難いもの
2項 投票が,前項各号に該当するかどうかの判断は,選挙管理人が,選挙立会人の意見を徴して決定する。
なお,上記決議の際,本件規約の内容及び詳細は総会の承認を受けるに至らず,これらは理事会に一任された。
(甲2,21,24,乙2の1,2の2,44)
(5)平成28年3月1日,中央会の担当者が被告の事務所を訪れ,選挙のスケジュール及び本件規約を確認した。
応対した被告の事務員は,同担当者から「無効投票の13条1項3号は1人または2人に投票した人の票が無効になる」,「組合員は1人から9人まで投票することができる権利があるのだから,このままでは選挙できない」旨を告げられ,それを指導と受け取ったことから,同月3日,被告の理事であったGにその旨を報告した。
(甲2,乙3)
(6)同月19日付け被告の理事会において,被告の事務員が,中央会の担当者から告げられた内容を報告した。同年4月23日付け被告の理事会において,特段異論が出ないまま,本件規約13条1項3号を被告の総会で削除することが確認されるとともに,役員選挙の投票人数についても議論が行われ,1人が9人まで投票できると役員が偏ってしまう場合があるので,1人以上5人までとする意見が出されたものの,最終的には,1人以上9人までとすることが決定された。
(甲22の13,乙4の1,4の2)
(7)当時被告の理事長であった原告X1は,同年5月9日付けで,全組合員に対して書面を送付し,同書面には,5人又は3人の連記式を提案したが反対されたこと,9人連記式は選挙として公平性に欠けるものであること,原告X1外しの選挙が行われようとしていること,原告X4,原告X6及び原告X1を含む5人の理事候補者に対して応援を頼むことなどが記載されていた(乙6の1,6の2)。
(8)同月29日,原告X4を議長として,被告の通常総会が行われた。同総会では,被告の会計書類が理事会で承認手続を経ていなかったことから決算関係書類承認の決議が行われず,その他の議案についても,長時間にわたって議論が行われたものの,決議がされないまま散会となった(甲23)。
(9)同年6月11日付け被告の理事会において,同年7月31日に本件臨時総会を開催することが決定されるとともに,改めて,役員選挙の投票者数について議論が行われた。原告X6は,同議論の中で「だから,それは。それはこの内容の変更に関しては組合でよく話し合って決めてくれって言われてるから,だから俺は,これはちょうど3人って書いてあるからね。被選挙人の数は3人とすると。それで,もうこれはオーケーになっちゃう。」と述べ,本件規約13条1項3号の文言を被選挙人の記載できる数を3人までとする規程と読み替えたうえで維持することを提案したものの,本件臨時総会においても,本件規約13条1項3号を削除する旨の議案を提案することが決まった。
被告の理事会は,同年6月21日付けで,全組合員に対して,同年7月31日に本件臨時総会を行う旨の通知をし,原告X1もこれに押印した。
(甲28の1,28の2,乙9,10)
(10)その後,X2(原告X3の父)作成の定款の一部変更及び本件規約の変更を目的とした臨時総会招集請求書(以下,「X2請求書」という。)が提出されたことにより,同年7月16日付け被告の理事会が開催された。同理事会でX2請求書の扱いを議論した結果,同請求書で審議を請求された議案について,本件臨時総会で審議すれば良いとの意見と,本件臨時総会と同日に別の臨時総会を開催し,選挙は後日改めて実施すべきであるとの意見が対立し,結論が出なかったため,X2請求書への対応は原告X1に一任することとされた。また,原告X1に対しては,選挙を延期することが可能かどうかを中央会に確認することが要求され,同理事会は終了した。(甲9,24,28の1,28の4)
(11)同月19日,原告X1名義で,全組合員に対して,「これまでの理事会決定事項の執行はすべていったん凍結して白紙にし,予定していた総会の招集も取り消します」と記載した書面が配布された。翌20日,被告は,全組合員に対して,組合印が押捺された本件招集通知を発送し,同招集通知には,被選挙人として1人から9人まで選ぶことができる投票用紙が同封された。
同月23日付けで,原告X1は,全組合員に対して,本件臨時総会の招集を取り消す旨の通知書を配布した。
同月25日,被告組合員から,原告X1の理事長解任を求める請求書が提出された。
(甲7,乙13ないし15)
(12)同月26日付け被告の理事会において,X2請求書にかかる議案及び原告X1の理事長解任請求にかかる議案を,本件臨時総会の議案として追加する旨が決定された。同日,被告の副理事長であったBは,個人名で,全組合員に対して,臨時総会を同年7月31日に予定どおり開催する旨,X2請求書にかかる議案及び原告X1の理事長解任請求にかかる議案が追加された旨を通知した。
同月28日,原告X1は,全組合員に対して,本件招集通知は無効であり,本件臨時総会は不開催である旨を記載した書面を送付した。
(甲8,乙16,17)
(13)同月31日に本件臨時総会が開催され,X2請求書にかかる議案は否決,原告X1の理事長解任請求にかかる議案は可決された。また,本件第5号議案にかかる決議が承認可決され,連記式無記名投票による本件選挙が行われた。本件選挙においては,従前のb支部(所属組合員数18人)から2人(原告らの主張によれば,原告X1を支持する候補者とされている。以下同様。),c支部(同13人)から2人(原告X1を支持する候補者と支持しない候補者),d支部(同11人)から2人(原告X1を支持しない候補者),f支部(同8人)から1人(原告X1を支持しない候補者),g支部(同9人)から2人(原告X1を支持しない候補者),h支部(同21人)から2人(原告X1を支持しない候補者),i支部(同8人)から0人,j支部(同14人)から2人(原告X1を支持する候補者と支持しない候補者)の理事候補者が出て,c支部から1人,d支部から2人,f支部から1人,g支部から2人,h支部から2人,j支部から1人の理事が選出された。本件選挙で選出された理事9人は,いずれも51から58の得票数を得ており,落選した理事候補者は,いずれも2から5の得票数を得ていた。
なお,k支所は本件臨時総会の前に他の組合に移転していた。
(乙18の1ないし18の3,45の1,45の2,弁論の全趣旨)
(14)平成30年通常総会において,第7号議案「本件規約における字句の一部修正の件」として,13条1項3号を削除した形での本件規約が示されたうえで,本文の趣旨に反しない字句の修正を代表理事に一任することを諮ったところ,原案どおり可決決定した。また,第8号議案「役員任期満了による改選の件」として,理事8人及び監事2人が任期満了により退任し,定数の立候補者が出たため,投票を行わずに,立候補者全員を当選者と可決決定した。
上記2つの決議については,提訴期間内に取消訴訟が提起されないまま確定した。
(乙62,63,弁論の全趣旨)
2 争点1(本件第5号議案にかかる決議について,無効事由が認められるか)について
(1)本件規約13条1項は,各号に該当する投票は無効とする旨を定めているところ,他の号の記載ぶりとの比較や,同項3号に3の数字が入った経緯等に照らせば,本件規約13条1項3号は,「最低3人の氏名を記載していることが確認できない場合には無効とする」との無効事由の1つを定めたものと解することが相当である。
(2)この点,原告らは,被告の定款及び本件規約には,いかなる投票制度を採用するかの規程がなく,従前の被告の理事会においても本件規約13条1項3号が投票方法に絡めて議論されていたことからすれば,同号は,単に無効事由の一つを定めた規程と解釈するのではなく,制限連記式投票制を採用した規程として解釈するのが合理的であると主張する。
(3)たしかに,被告の定款及び本件規約には,完全連記式投票制と制限連記式投票制のいずれを採用するかが明記されていないものの,後記3(2)及び(3)のとおり,被告の定款及び本件規約にこれらの別を記載していないことが,直ちに組合法に反するものとは認められず,本件規約13条1項3号の文言や成立経緯から導かれる解釈に反して,あえて同号を制限連記式投票制を定めた規程であると解する必要性は乏しい。
加えて,前記認定事実によれば,平成28年4月23日付け被告の理事会において,本件規約13条1項3号が特段の意味を持つ条項とは認識されないまま,同号の削除が決定されたこと,同年6月11付け被告の理事会において,原告X6が「同号を被選挙人の記載できる数を3人までとする規程と読み替えるべき」旨の発言をしていることが認められ,これらに照らせば,被告の理事会においても,従前,同号が制限連記式投票制を定めた規程であるとは認識されていなかったことが認められる。
よって,原告らの主張は採用できず,本件規約13条1項3号を,投票人数を3人までとする制限連記式投票制を定めた規程であると解することはできない。
(4)よって,本件規約13条1項3号が制限連記式投票制を定めたものであり,同号の削除は組合法1条,33条,35条に反するとの原告らの主張は,その前提を欠くものであるから採用することができず,本件第5号議案にかかる決議が無効であるとは認められない。
3 争点2(本件第8号議案にかかる決議について,無効事由が認められるか)について
(1)(ア)(被告において完全連記式投票制を採用することができるか)について
ア 原告らは,中小企業等協同組合における業務意思決定は,極力全組合員の意思が反映された形で執り行うことが求められるところ,完全連記式投票制はあくまで多数派に当選者を独占させる投票方法である以上,当該組合において,完全連記式投票制を採用しても多数派の独占とならない特段の事情がある場合に限って,完全連記式投票制を採用することが認められるべきであるとし,被告においては,かかる特段の事情はなく,むしろ,被告の規模,性質,沿革等にかんがみれば,より一層少数派からの役員選出の要請が働くというべきであるから,被告において完全連記式投票制を採用することは組合法1条及び35条11項に反し,完全連記式投票制を採用して行われた本件選挙は無効であると主張する。
イ 組合法35条3項は,「役員は,定款の定めるところにより,総会において選挙する」として,同条8項は「役員の選挙は,無記名投票によって行う」と定めている。そして,同条10項は,「第8項の規定にかかわらず,役員の選挙は,出席者中に異議がないときは,指名推薦の方法によって行うことができる」とし,同条11項において「指名推薦の方法を用いる場合においては,被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り,出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする」と定めている。
組合法の上記規定に照らせば,同法は役員の選挙に関して,無記名投票によることを原則としているが,組合員が少数の場合や,組合員相互間で知悉している場合等には,投票制の煩を避けるために,例外として,指名推薦制を採用することができる旨を定めたものである。そして,指名推薦制を採用する場合には,役員の構成が多数派代表に偏することを防止するために,第11項において,当選の要件として出席者全員の一致を求め,一人でも異議を唱えれば当選の効力が認められないとしているものである。
つまり,組合法では,無記名投票による選挙は,それ自体をもって少数派からも代表者を役員に送り込むことが可能な制度であることから,指名推薦制における出席者全員の一致のような特別の要件を課さなかったものと認められ,無記名投票を採用したうえで,さらに少数派からの代表者の選出を容易とする要件を課すべきであり,特段の事情がなければ,完全連記式投票制を採用することはできないとの原告らの主張はその根拠を欠くものであり,採用できない。
ウ 加えて,原告らは,原告X1を支持しない地域を「多数派」(h,d,c,g及びf支部。これらの所属組合員数は62人。),支持する地域を「少数派」(j,b,i及びe支部。これらの所属組合員数は48人。)と定義したうえで,被告においては,いまだ支部ごとのまとまりが強いため,本件選挙で完全連記式投票制を採用したことによって,多数派を形成する支部側が推薦する者のみが役員に選出され,少数派からの役員選出が行われなかったと主張する。しかし,原告X6自身が本人尋問において,i支部にはまとまりがない旨を供述している点や,本件選挙においてもc支部及びj支部から,原告X1を支持する候補者と支持しない候補者の両名が立候補している点などに照らすと,支部ごとに「多数派」と「少数派」を明確に分けることが可能であるかは疑問である。また,本件選挙で落選した候補者の得票数は,いずれも2票から5票であり,これらの候補者が「少数派」とされる支部を代表し,同支部に所属する組合員らの支持を得ていたと認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,本件選挙において,完全連記式投票制を採用したことにより,原告らの主張する「少数派」からの役員選出が不当に制限されたとは認められない。
エ たしかに,本件臨時総会に至るまでの被告の理事会における議論や,同総会で行われた説明等にかんがみれば,被告において完全連記式投票制と制限連記式投票制のいずれを採用するかについて,十分な議論が行われたかについては疑問なしとはしないが,その点をもって,本件選挙が組合法1条及び35条に違反するものとはいえず,原告らの主張には理由がない。
(2)(イ)(被告の定款に記載すべき事項)について
原告らは,被告の定款において完全連記式投票制と制限連記式投票制のいずれを採用するかを明記していないことは,組合法33条1項11号に反し,当該状態で行われた本件選挙は無効であると主張する。
しかし,組合法は,定款の必要的記載事項として「役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定」を定めているものの(同法33条1項11号),完全連記式投票制か制限連記式投票制かの別までを記載するよう求めているものとは解されず,組合の規模等によって定款の必要的記載事項が異なるとする合理的な理由も認められない。そして,前記認定事実によれば,被告の定款32条には,2項に「役員の選挙は,連記式無記名投票によって行う」,7項に「役員の選挙に関する事項は,本条で定めるもののほか規約で定める」と定められており,必要的記載事項は記載されているとみるべきである。
よって,被告の定款が組合法33条1項11号に反しているとは認められず,定款に明記されていないことから本件選挙が無効であるとの原告らの主張は理由がない。
(3)(ウ)(本件規約に定めるべき事項)について
原告らは,本件規約において,完全連記式投票制か制限連記式投票制のいずれを採用するかを明記していないことは,組合法1条,33条,35条に反し,当該状態で行われた本件選挙は無効であると主張する。
しかし,組合において,規約を設けるかどうかはそもそも任意であるところ(同法34条),規約に投票制についての明記がないことをもって組合法1条等に反するということはできない。
よって,本件規約に明記されていないことから,本件選挙が無効であるとの原告らの主張は理由がない。
4 争点3(訴えの利益)について
(1)株主総会決議取消しの訴えは形成の訴えであるが,役員選任の総会決議取消しの訴えが係属中,その決議に基づいて選任された役員らがすべて任期満了により退任し,その後の株主総会の決議によって役員が新たに選任され,その結果,取消しを求める選任決議に基づく役員がもはや現存しなくなったときは,特別の事情のないかぎり,決議取消しの訴えは実益がないものとなり,訴えの利益を欠くに至るものと解するのが相当である(最高裁昭和45年4月2日第一小法廷判決民集24巻4号223頁)。
前記認定事実によれば,被告においては,本件臨時総会で選任された理事ら役員がすべて任期満了により退任し,平成30年通常総会において,新たな役員が選挙を経ずに選任されたことによって,取消しを求める決議に基づく理事ら役員が存在しなくなったことが認められるから,本件第8号議案にかかる決議の取消しについては,訴えの利益を欠くに至ったものと解するのが相当である。
(2)この点,原告らは,本件第8号議案にかかる決議が取り消されれば,同決議に基づいて選任された役員による被告の業務執行も問題となり,新たに役員が選任されたことで当然に業務執行の瑕疵が治癒されるわけではないので,訴えの利益は存在すると主張する。しかし,原告らの主張によっても,同決議により選任された役員のいかなる業務執行が,被告にどのような損害を与えたのかが明らかでなく,本件第8号議案にかかる決議の法的効力を否定すべき特別な事情は認められない。
原告らの主張は採用できない。
(3)また,決議取消しの訴えが係属中,当該決議と同一の内容を持ち,当該決議の取消判決が確定した場合には遡って効力を生ずるものとされている決議が有効に成立し,それが確定したときは,決議取消しの訴えの利益は失われると解するのが相当である(最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決民集46巻7号2580頁)。
前記認定事実によれば,被告においては,平成30年通常総会において,13条1項3号を削除した本件規約が改めて承認決議され,同決議が確定していることが認められる。そして,本件規約13条1項3号は,投票において「最低3人の氏名を記載していることが確認できない場合には無効とする」との無効事由の1つを定めたものであるところ,本件選挙で選任された役員らがすべて任期満了により退任し,新たな役員が選任されていること,本件臨時総会後,平成30年通常総会までの間に,被告において本件規約に基づく行為が行われたとは認められないことなどに照らせば,本件第5号議案にかかる決議については,仮にこれらの決議について取消しの事由があると判断してこれを取り消してみても,被告の現在の法律関係ないし財産状態に変動を生じさせるものではないから,もはや取消しを求める訴えの利益は失われているものと解するのが相当である。
(4)よって,本件第5号議案及び本件第8号議案にかかる決議の取消しについて,訴えの利益は認められないから,その余の点について判断するまでもなく,これらを却下することとする。
5 以上によれば,原告らの主位的請求はいずれも理由がないから棄却することとし,予備的請求はいずれも訴えの利益を欠くことから却下することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 松山美樹)
「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日 神戸地裁 平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日 東京地裁 平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日 東京高裁 平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日 大阪地裁 平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日 甲府地裁 平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日 水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日 東京高裁 平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日 盛岡地裁 平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日 名古屋地裁 平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日 東京地裁 平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日 東京地裁 平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日 東京地裁 平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日 東京地裁 平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日 東京地裁 平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日 大阪高裁 平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日 東京地裁 平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日 東京高裁 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日 東京高裁 平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日 東京高裁 平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日 高松高裁 平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日 東京地裁 平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日 東京地裁 平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日 東京高裁 平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日 東京地裁 平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日 東京地裁 平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日 東京高裁 平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日 東京地裁 平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日 最高裁第三小法廷 平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日 千葉地裁 平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日 福岡地裁 平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日 東京地裁 平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日 東京地裁 平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日 東京高裁 平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日 神戸地裁 平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日 東京地裁 平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日 徳島地裁 平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日 青森地裁 平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日 青森地裁 平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日 青森地裁 平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日 東京地裁 平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日 東京地裁 平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日 東京地裁 平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日 東京地裁 平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日 静岡地裁 平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日 高松高裁 平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日 神戸地裁豊岡支部 平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日 静岡地裁 平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日 東京地裁立川支部 平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日 東京地裁 平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!

①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
| 【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
| 選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
| 営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。 |
| ①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
| ②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
| ③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
| ④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
| ⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
| 選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
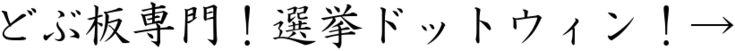



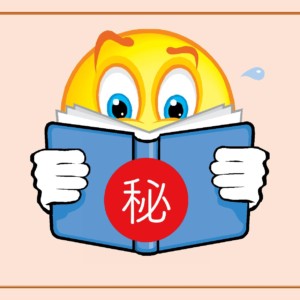
この記事へのコメントはありません。