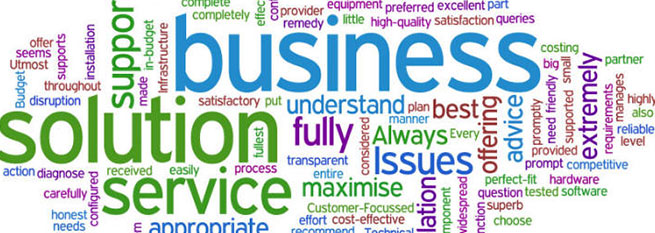
選挙関連用語集
| 3ない運動(さんないうんどう)とは? | 「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動 |
| ウグイス嬢(うぐいすじょう)とは? | 一般的には「ウグイス嬢」と言われている、選挙カーなどに乗り込んで立候補者の名前を呼び掛ける女性のこと。公職選挙法上では「車上等運動員」にあたる。男性が車乗等運動員を行う場合には「選挙カラス」と呼ばれることもある。ウグイス嬢を専業で行っている人材も一部にはいるが、一般的には当該選挙区の地元のタレントやフリーアナウンサーなどイベントでMCを行う者が担当するケースが多い。車乗等運動員の報酬上限額は規定で決まっており、その上限額以上を報酬として支払うと選挙違反になるため注意が必要である。皆さんご存じ街宣車で候補の名前を決死の覚悟のように訴える女性のこと。ウグイス嬢を派遣する業者があって特に党派は関係ないので、同じウグイス嬢でも派遣先に応じて自民党の応援をやったり民主党の応援をやったりする。候補者の奥さんや知人の女性や支持団体の女性がウグイス嬢をやることもある。若くて綺麗なウグイス嬢だと街宣車の男衆の士気も俄然上がる。ベテランのおばさんウグイス嬢だと(ベテランの方が遙かに上手なんだけど)街宣車の男衆は割と沈黙してる。 |
| カラス(からす)とは? | 選挙カーなどに乗り込んで立候補者の名前を呼び掛ける男性のこと。「ウグイス嬢」と同様に、公職選挙法上では「車上等運動員」にあたる。ウグイス嬢の項目も参照のこと。男版のウグイス嬢(候補者以外)はカラスと呼ばれる。街宣車から勇ましく訴えることを使命とする。ウグイス嬢に比べて出番は少ないが、女性が確保できなかったときなどはカラスが活躍する。ベテランではないので最後には喉が切れてほとんど絶叫に近くなる。 |
| スパイ(すぱい)とは? | 実際にいる。ボランティアに紛れて宗教系の人などが入ってきて事務所内の情報を敵対陣営に内通する。事務所内でしか知らないはずの情報が敵対陣営に漏れていたり、あるいは何故か敵対陣営の内部の動きが情報として伝わってきたりする。秘書を中心にスパイにはかなり気をつけている。 |
| ポスター(ぽすたー)とは? | 支持者宅でポスターを貼ってくれている場所はゼンリンの地図上に全てメモされている。ポスターは選挙期間に応じてボランティアが車で回って張り替えを行う。公設掲示板に貼るポスターは、選挙管理委員会で告示日に行われるくじ引きで貼る位置(番号)が決まる。その番号を連絡してボランティアが車で一斉に貼って回る。 |
| ボランティア(ぼらんてぃあ)とは? | 選挙事務所はお金で雇われた運動員とボランティアによる人海戦術で動く。ボランティアは支持者や政策に共感した純粋な市民が来る場合も稀にあるが、大部分は労組や宗教など支持団体の動員である。ボランティアは地図落としや公選葉書の宛名書きや電話作戦やビラ配りなどに回される。たまに純粋な市民で政策に共鳴したすごく変わった人物が来て事務所の雰囲気を破壊することがあるが、そういう時は丁重に事務所の仕事からは遠ざけるようにする。 |
| 為書き(ためがき)とは? | 選挙番組などでよく事務所に映っている「祈 必勝」と政治家の名前が書いてあるデカい張り紙のことを為書きという。為書きは送られてきたらとにかく事務所の壁に貼りまくる。壁に貼る場所が無くなったら天井に貼ったりする。これは選挙に与える影響は皆無に近いが、政治家にとっては年賀状のようなもので誰から送られてきたかは記録して、送った人が立候補するときには逆に為書きを送る。社交的な慣習だが、礼儀を尽くすのが極めて大事な世界。 |
| 一般選挙(いっぱんせんきょ) | 都道府県、及び市区町村議会の議員全員を選出する選挙。議員、または当選人全員がいなくなった場合に行われる(4年間の任期満了、議会の解散、議員の退職、選挙の全部無効など)。都道府県、市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。 |
| 引き続き同一都道府県内の区域に住所を有していることの確認とは? | 都道府県知事選挙や都道府県議会議員選挙において、同一都道府県内の住所移転を行った場合は、継続して当該都道府県内に住所を有していることの確認を受けなければなりません。これは各投票所の投票管理者に申請を行うことによって、受けることができます。また、事前に転出前の市区町村や転出後の市区町村でこの確認を受けることで「引き続き証明書」を取得することができますが、この「引き続き証明書」を提示することによっても投票を行うことができます。 |
| 演説会(えんぜつかい)とは? | 会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合。候補者等が会場に聴衆を集めて政見や主張を演説する会合。 |
| 開票管理者(かいひょうかんりしゃ)とは? | 開票に関する事務(投票の点検、投票の効力決定、開票結果報告、開票録作成、開票所の取締りなど)を行う人。市区町村の選挙管理委員会が有権者の中から選任する。各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の取締りなど)を行う。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。 |
| 開票区(かいひょうく)とは? | 選挙の開票を行うために決められた-定の区域。原則として1市区町村1開票区である。選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市町村の区域とされている(市町村の中に複数の選挙区がある場合は、その選挙区が区域となる)。 |
| 開票立会人(かいひょうたちあいにん)とは? | 開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する。具体的には、開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行う。公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者から3人になるまで補充選任する。開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する。具体的には、開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行う。公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者から3人になるまで補充選任する。 |
| 街宣車(がいせんしゃ)とは? | 業界では「宣車」と略されて呼ばれることが多い。街宣車を専門に扱う業者が存在する。街宣車は適当に街中を走り回っているように見えるが、実は前日に街宣ルートが決められている。街宣ルートは名簿の支持者宅が多い場所を重点的に回る。同じ選挙区で同じ党から複数の立候補者がいる場合は、「誰々は○○地区」「誰々は○○地区」など縄張りや地盤が分割される場合が多く、街宣車で回って良い場所と回ってはいけない場所が存在する場合もある(特に地方選挙)。街宣車の主要な目的は政策を伝えることではなく、支持者宅を中心に「選挙が近いですよ」ということを告知することにある。それと街宣車が移動している時間的制約もあり、無党派層を中心に苦手な人が多い候補者名の連呼が行われることになる。 |
| 街頭演説(がいとうえんぜつ)とは? | 駅前などの街頭で、居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説。駅前などの街頭で、居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説。 |
| 確認団体(かくにんだんたい)とは? | 選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、総務大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、総務大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。 |
| 間接民主主義(かんせつみんしゅしゅぎ) | 国民が間接的に参加して行う民主主義。選挙で代表を選ぶことによって行われる。国民が間接的に参加して行う民主主義。選挙で代表を選ぶことによって行われる。 |
| 寄附の禁止(きふのきんし)とは? | 選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁じられている。(お中元やお歳暮、差入れ等も寄附に当たる)選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁止されている。お中元やお歳暮、差入れ等も寄附に当たる。 |
| 期日前投票(きじつぜんとうひょう)とは? | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者が、当該選挙期日の告示または公示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所において行う投票。選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者が、当該選挙期日の告示または公示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所において行う投票。投票日に投票所に行けない人が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で、投票日前に投票する制度。仕事以外の理由でもできる。 |
| 記号式投票(きごうしきとうひょう)とは? | あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票のこと。地方公共団体の議会議員及び長の選挙について、条例により採用できる。東京都内においては現在、港区が区長選挙で採用している(かつては三鷹市、青梅市、小平市において採用されていた。)。あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票の方式。 |
| 供託(きょうたく)とは? | 無責任な立候補を防ぐため、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数に達しない場合には、全額または一部没収される。供託額は衆議院小選挙区300万円、参議院選挙区300万円、都道府県知事300万円、都道府県議会60万円、指定都市長240万円、指定都市議会50万円、市区長100万円、市区議会30万円、町村長50万円、衆議院比例代表1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、参議院比例代表1候補者につき600万円。供託金が高額すぎるため、立候補に事実上の対する規制になっており、供託金の額を引き下げるべきだという議論がある。候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収される。供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、指定都市の長240万円、その他の市の議会30万円、その他の市の長100万円、町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、参議院の比例代表は1候補者につき600万円である。 |
| 供託金(きょうたくきん)とは? | 選挙において立候補するためには、一定額以上のお金を供託しなければなりません。このお金のことを供託金といい、立候補者が乱立することを防ぐために設けられた制度です。 |
| 空中戦(くうちゅうせん)とは? | |
| 経歴放送(けいれきほうそう)とは? | 候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するテレビやラジオ放送。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事選挙の時に放送される。支持者固めではなく、駅など街頭で無差別に色々な人にビラを配ったり政策を訴えたり握手したりするのを空中戦と呼ぶ。空中戦は都市部では効果的だが、地方になると人が密集して歩いている場所は少ないのであまり効果が無い場合が多い。「桃太郎」と呼ばれる十数人規模で陣形を組んで街頭を行進して支持を訴える戦術もある。テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。 |
| 候補者名簿(こうほしゃめいぼ)とは? | 衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、一定の要件を満たした政党等が届け出ることができる候補者名簿のこと。(参照:比例代表選挙)衆議院、参議院の比例代表選挙で一定の要件を満たした政党が、候補者氏名等を記し、届け出た名簿。この登載者の中から当選者が決まる。 |
| 公示・告示(こうじ・こくじ)とは? | いずれも選挙日を告知する行為のことを指します。公示は内閣の助言と承認に基づいて天皇が行う国事行為で、衆議院総選挙及び参議院通常選挙において行われます。それ以外の選挙については、告示となり、各選挙を管理する選挙管理委員会が行います。立候補届出書類を選挙管理委員会に届け出るのもこの公示日または告示日であるため、立候補受付日ということもあります。両者ともに選挙期日を告知すること。「公示」は衆議院総選挙及び参議院通常選挙の場合のみの呼称。これは、天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うからである。それ以外の選挙は「告示」となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われる。国政選挙であっても補欠選挙等は告示となる。どちらとも、選挙期日を告知することをいう。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙および参議院通常選挙でのみ行われる。それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても補欠選挙等については告示となる。 |
| 公職(こうしょく)とは? | 衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の職。公職選挙法が対象とする「公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体議会の議員、および長の職を指す(公職選挙法3条)。これらの職にあるものは、公職選挙法を順守する必要がある。衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の職。 |
| 公選葉書(こうせんはがき)とは? | 選挙期間中に有権者に送ることが出来る葉書。国政選挙や地方選挙などによって枚数が決まっている。公選葉書には必ず誰からの紹介で送っているかを記入する欄がある。最近は名簿のデータを元にプリントアウトするところが増えたが、手書きの方が熱意が伝わるという理由と、事務所内で暇な中だるみの雰囲気をつくらないために、ボランティア(≒動員された人)にボールペンで宛名書きをお願いすることが多い。国政選挙だと数千通を書くので、これも人海戦術の途方もない作業。書き終わったら郵便局に輸送する。 |
| 拘束名簿式(こうそくめいぼしき)とは? | 政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。衆議院の比例代表選挙で採用されている。(対語:非拘束名簿式)比例代表選挙の一つの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順序」がつけられた名簿をもとに行われる。衆議院比例代表選挙で採用されている。政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。衆議院の比例代表選挙で採用されている。 |
| 再選挙(さいせんきょ)とは? | 選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに、当選人の不足を補う選挙。(類語:補欠選挙)選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに行われる当選人の不足を補う選挙。 |
| 最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)とは? | 最高裁判所裁判官を辞めさせるか否かを国民が審査する制度。衆議院議員総選挙と合わせて行われる。対象者は、任命後初めて衆議院議員総選挙が行われる裁判官と、前回の審査期日から10年を経過した後初めて衆議院議員総選挙が行われる裁判官となる。 |
| 在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)とは? | 外国に住む日本の有権者で、衆議院議員、参議院議員選挙の投票を希望する人を登録する選挙人名簿。外国に住んでいる日本の有権者で、衆議院及び参議院議員選挙の国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。 |
| 在外投票(ざいがいとうひょう)とは? | 海外に住む有権者が、日本の国政選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票。在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票のいずれかの方法により投票できる。仕事や留学などの事情で海外に住む人が、衆議院議員選挙および参議院議員選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている人。投票方法としては、在外公館投票、郵便等投票、帰国投票がある。 |
| 資金管理団体(しきんかんりだんたい)とは? | 政党、政治資金団体以外の政治団体のうち、公職の候補者が自らが代表者になっている政治団体のうちの一つを、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した団体。公職の候補者等が、自身の政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治団体のこと。 |
| 事前運動(じぜんうんどう)とは? | 選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うこと。罰則をもって禁止されている。公示・告示の前に許されるのは、政治活動のみである。選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。 |
| 事前審査(じぜんしんさ)とは? | 告示日または公示日に提出される立候補届出書類を事前に審査することをいいます。立候補受付日における書類の不備を極力少なくするために行っています。 |
| 自書式投票(じしょしきとうひょう)とは? | 投票用紙に候補者の氏名や政党等の名称を自書して行う投票のこと。(対語:記号式投票)投票者本人が自分で候補者や政党等の名前を書いて投票箱に入れる投票。 |
| 車乗等運動員(じょうしゃとううんどういん)とは? | 自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者のこと。公職選挙法の規定により、報酬を支払うことが認められている。「ウグイス嬢」や「選挙カラス」と呼ばれることが多い。ウグイス嬢の項目も参照のこと。 |
| 収支報告書(しゅうしほうこくしょ)とは? | 選挙運動費用と政治団体の収支報告書がある。選挙運動費用の収支報告書は、候補者の選挙運動に関する収入及び支出について、選挙後にその選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。政治団体の収支報告書は、政党その他の政治団体について、その年における収入及び支出を、毎年、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。いずれも、その要旨は公表され、収支報告書は閲覧の対象となる。 |
| 重複立候補(じゅうふく〈ちょうふく〉りっこうほ)とは? | 2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。 |
| 重複立候補(ちょうふくりっこうほ)とは? | 通常は禁止されている。しかし衆議院議員選挙では、政党届出された小選挙区の候補者を比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。 |
| 出納責任者(すいとうせきにんしゃ)とは? | 選挙運動における収支の責任一切を担う者。選挙管理委員会に届出をし、収支報告の義務もある。選挙運動における収支の責任一切を担う者。選挙管理委員会に届出をし、収支報告の義務もある。 |
| 小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ)とは? | 衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に約300の小選挙区があったが、平成25年7月28日から施行された改正公職選挙法により小選挙区の数は5減少し295となった。衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区がある。 |
| 小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)とは? | 政策本位、政党本位の選挙を実現するために衆議院議員総選挙に採用されている制度で、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度。小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度。政策本位、政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員総選挙に採用されている。 |
| 職務代理者(しょくむだいりにん)とは? | 投票管理者に事故があり、又は欠けた場合において、その職務を代理する者のことをいいます。各選挙の選挙権を有する者の中から選任することとなっており、取手市の場合は投票事務に従事する職員の内、各選挙の選挙権を有する者を1人選任することとなっております。 |
| 推薦団体(すいせんだんたい)とは? | 確認団体に所属していない候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその内容等の確認を受けた政党・政治団体のこと。確認団体所属以外の候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体のこと。 |
| 推薦届出(すいせんとどけで)とは? | 選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。 |
| 政見放送(せいけんほうそう)とは? | 候補者の政見や主張、政党政策などをテレビやラジオを通して放送すること。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。テレビやラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。 |
| 政治資金団体(せいじしきんだんたい)とは? | 政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党がその旨の指定をし、総務大臣に届出している政治団体のこと。 |
| 政治団体(せいじだんたい)とは? | 政治資金規正法において、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体をいう。(1)政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること(2)特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされる。(1)政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)(2)政治資金団体(3)特定パーティー開催団体 |
| 政党(せいとう)とは? | 政治資金規正法上は、次のいずれかにあてはまる政治団体をいう。(1)所属国会議員が5人以上(2)前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上 |
| 政党助成金(せいとうじょせいきん)とは? | 国が政党に対し助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした交付金。 |
| 政党届出(せいとうとどけで)とは? | 衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法。一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙、及び参議院比例代表選挙で行われる立候補届出方法。一定の要件を満たす政党・政治団体のみが行う。衆議院の小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院の比例代表選挙で行われる立候補届出方法。一定の要件を満たす政党・政治団体が行う。 |
| 惜敗率(せきはいりつ)とは? | 衆議院小選挙区選挙において、最多得票者の得票数に対するその候補者の得票数の割合。衆議院比例代表選挙における重複立候補者(小選挙区で当選した者を除く)の名簿登載順位が同じ場合は、惜敗率の高い順に当選人となる順位が定められる。 |
| 設置選挙(せっちせんきょ)とは? | 地方公共団体が新しく設置された場合、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙。新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙。 |
| 選挙運動員(せんきょうんどういん)とは? | 選挙運動員とは、公職選挙法上の「選挙運動」を行う者。選挙管理委員会から交付された腕章を着用しなければならない。 |
| 選挙運動期間(せんきょうんどうきかん)とは? | 立候補届が受理された時から投票日前日の午後12時まで(ただし、街頭演説は午後8時まで)。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。立候補届が受理された時から投票日前日の午後12時まで(ただし、街頭演説は午後8時まで)。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。 |
| 選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)とは? | 公正な選挙の実施を管理するための公的機関。中央選挙管理会、都道府県・市区町村の選挙管理委員会がある。選挙の公正な実施を管理するための公的機関。中央選挙管理会、都道府県・市区町村の選挙管理委員会がある。 |
| 選挙期日(せんきょきじつ)とは? | 選挙の投票を行ういわゆる「投票日」のこと。投票日のことをいいます。あくまで投票日当日を指す言葉ですので、期日前投票日はこれには当たりません。 |
| 選挙区(せんきょく)とは? | 議員を選挙するために都道府県や区市町村などの区域を区分して定められた区域のこと。衆議院小選挙区選出議員選挙は289、東京都議会議員選挙は42の選挙区がある。議員を選挙するために都道府県や市町村などの区域を基本として定められた区域のこと。 |
| 選挙権(せんきょけん)とは? | 選挙で立候補者を選ぶことができる権利。選挙で投票する権利のこと。選挙で選ぶことができる権利のこと。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件=欠格条項)がある。積極的要件としては、衆議院議員・参議院議員の選挙では満18歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者であること。市町村長・市町村議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市町村に住所のある者であること。消極的要件としては、以下の条件に当てはまらないこと。(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
| 選挙権・被選挙権の停止(せんきょけん・ひせんきょけんのていし)とは? | 一定期間、投票や立候補ができなくなること。選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもの。選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもので、一定期間、投票や立候補ができなくなること。 |
| 選挙権の消極的要件(せんきょけんのしょうきょくてきようけん)とは? | 選挙権を持つために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。選挙権を持つためにひとつでも当てはまってはいけない条件。(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終えていない者(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 |
| 選挙権の積極的要件(せんきょけんのせっきょくてきようけん)とは? | 選挙権を持つために、その人が必ず備えていなければならない要件。選挙権を持つために必ず備えていなければならない要件。衆議院議員・参議院議員の選挙では満20歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者であること。市区町村長・市区町村議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者であること。 |
| 選挙公報(せんきょこうほう)とは? | 候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、政見経歴等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行する。衆議院及び参議院議員比例代表選挙においては、政党の政策や名簿登載された候補者の紹介等が政党からの申請により掲載される。投票日の2日前までに全世帯に配布される。国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書。選挙管理委員会が発行し、投票日の2日前までに全世帯に配布される。国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書。選挙管理委員会が発行し、投票日の2日前までに全世帯に配布される。国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。 |
| 選挙広報支援会社(せんきょこうほうしえんがいしゃ) | 選挙立候補(予定)者の政治活動や選挙運動等の広報支援サービスを提供している「選挙.WIN!」のような会社。 |
| 選挙事務員(せんきょじむいん)とは? | 選挙事務所内で選挙に関する事務作業を行う者。電話による投票依頼などの「選挙運動」を行うものは選挙事務員ではない。事前に届出をすれば、選挙事務員に対しては報酬を支払うことが可能である。 |
| 選挙事由(せんきょじゆう)とは? | 選挙が行われることになった理由。任期の満了、議会の解散、議員や当選人の不足など。選挙が行われることになった理由。任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがある。 |
| 選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)とは? | 選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。 |
| 選挙争訟(せんきょそうしょう)とは? | 選挙手続きの瑕疵(かし=欠点)などで、選挙の結果が変わったはずだと選挙人や候補者が主張して、選挙の有効無効を争うもの。選挙手続きに不都合があったとし、その選挙の全部または一部の効力を争うもの。 |
| 選挙長(せんきょちょう)とは? | 開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどした上で当選人を決定する選挙会に関する事務を行う。選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会)によって選任される。 |
| 選挙費用の公営(せんきょひようのこうえい)とは? | 国又は地方公共団体が候補者や政党等の選挙運動費用の一部を負担すること。選挙の種類により、負担する範囲・金額が異なる。選挙管理委員会から業者へ直接支払われるため、立候補者が立替払いをする必要はないことが多い。国または地方公共団体が、候補者や政党の選挙運動費用の一部を負担するもの。 |
| 選挙立会人(せんきょたちあいにん)とは? | 選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、当該選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については当該選挙分会長)に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は当該選挙長が当該選挙の選挙権を有する者から3人になるまで補充選任する。 |
| 総選挙(そうせんきょ)とは? | 衆議院議員全員を選ぶ選挙。比例代表選挙と小選挙区選挙を同日に行う。併せて最高裁判所裁判官が国民審査に付される。衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。小選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行う。併せて、最高裁判所裁判官が国民審査に付される。 |
| 代理投票(だいりとうひょう)とは? | 心身の故障などの事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合、投票所の係員が本人の指示する候補者の氏名等を代理記載する制度。投票所の係員が記載する際には、別の係員が立会い、本人の指示したとおり記載したことを確認する。 |
| 地図落とし(ちずおとし)とは? | 各支持団体や議員から提出された名簿を元に、名簿に書かれている人の住所をゼンリンの住宅地図に蛍光ペンで一軒一軒マーキングしていく作業。何千人、場合によっては何万人もマーキングしていく途方もない作業。この地図は街宣ルートの策定や本当はやってはいけない戸別訪問に使われることが多い。最近は地図業者が開発した選挙用ソフトウェアで、ExcelやAccessやFileMakerなどから地図に自動的にマッピングできる方法が普及しつつある。しかし名簿は未だ紙ベースの場合が多いので、地図落としはほぼ必ず必要になる。 |
| 朝立ち(あさたち・あさだち)とは? | 早朝に駅頭や橋などに候補者が立って演説することを朝立ちという。朝立ちは街宣車よりはもう少しだけ内容のある話であることが多い。朝立ちは一見すると効果が無いように見えるが、毎日朝に立って演説している姿に心打たれて握手を求めてくる人が実際いる。朝立ちは侮れない。 |
| 直接選挙(ちょくせつせんきょ)とは? | 一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。日本のほとんどの選挙がこの方式。選挙権を持つ人が、投票により直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。日本のほとんどの選挙がこの方式。一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。日本のほとんどの選挙がこの方式。 |
| 直接民主主義(ちょくせつみんしゅしゅぎ)とは? | 国民全員が直接参加して行う民主主義の政治。民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向き。通称使用の申請戸籍名に代わるものとして芸名やペンネーム等の通称が広く通用している場合、候補者や政党がその通称の使用を申請する制度(本名を仮名書きする場合も申請を要する)。申請が認められると、立候補届出等の告示、新聞広告、政見放送、経歴放送、選挙公報、投票記載所の氏名等の掲示については、本名に代えて通称が使用される。これら以外のもの(選挙運動用ポスター等)については、通称を使用するかどうかは候補者が自由に決めてよい。国民全員が直接参加して行う民主主義の政治。民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向き。 |
| 通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい)とは? | 戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称が広く通用している場合、候補者や政党が、その通称の使用を申請する制度。この申請が認められると立候補者名の告示や選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名を仮名書きやカタカナで記載する場合も申請が必要となる。本名以外の芸名やペンネームなどの通称で広く知られている候補者が、その通称の使用を申請する制度。 |
| 通常選挙(つうじょうせんきょ)とは? | 参議院議員の半数を選ぶ選挙。3年に1回ずつ比例代表選挙と選挙区選挙を同日に行う。6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行う。 |
| 定数(ていすう)とは? | 選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。国会議員は法律で定められ、東京都議会議員の場合は、条例により42選挙区で総定数127と定められている。選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。 |
| 点字投票(てんじとうひょう)とは? | 目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度。投票所で申請して行う。期日前・不在者投票でも行なうことができる(ただし郵便等による不在者投票の場合をのぞく)。 |
| 電話作戦(でんわさくせん)とは? | 名簿を元に支持者宅に電話を掛ける。事務所はそのために複数の電話回線を契約する。「○○の紹介でお電話させて頂きました、誰々事務所でございます」から始まって「厳しい選挙戦ですが、只今一生懸命頑張っておりますのでよろしくお願いいたします」ということを伝える。電話はボランティアしか行ってはいけないことになっている。お金で雇われた運動員が電話をすると公職選挙法違反になる。誰に電話を掛けたのかは名簿のコピーに印をつける。このとき、相手の反応をメモする。好意的な応対だったら「○」、ただ聞いているだけだったら「△」、ガチャ切りや「もう掛けてこないでください」だったら「×」など。その集計結果は毎晩の選対会議で報告される。 |
| 電話作戦の裏技(でんわさくせんのうらわざ)とは? | 電話は投票日に有権者に掛けてはいけない。しかし裏技があって電話を掛ける方法もある。「私達は選挙に投票しようと皆様に呼びかける活動を行っているものでございます。今日は投票日です。投票に行かれますよう是非よろしくお願いいたします」と事務所名を名乗らずに投票を呼びかける自発的な団体であることを話して、名簿の支持者宅に電話を掛ける戦術がある。 |
| 投票管理者(とうひょうかんりしゃ)とは? | 投票所において、投票事務全般を管理執行し、投票に関する全ての手続きについて最終的な決定権をもつ最高責任者をいいます。各選挙の選挙権を有する者の中から選任することとなっており、取手市では市政協力員に推薦を依頼しています。各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務(投票用紙の交付、選挙人の確認や投票拒否、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持など)を行う。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務(投票用紙の交付、選挙人の確認や投票拒否、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持など)を行う。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。 |
| 投票区(とうひょうく)とは? | 円滑に投票事務を行えるようにするために、選挙区をいくつかの区域に分けた上で選挙を行っています。この区域を投票区と呼びます。選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区という。公正で間違いのない選挙を行うために、市区町村の区域を分けて定められた投票を行なうための区域。有権者は自分の属する投票区で投票する。選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区という。 |
| 投票立会人(とうひょうたちあいにん)とは? | 投票事務の執行が公正に行われるよう、投票手続全般の立会い、投票の拒否等の手続に対する意見陳述、投票箱の送致などを行う人。その選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から本人の承諾を得て、市区町村の選挙管理委員会が2人以上5人以下を選任する。投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する人のこと。具体的には投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行う。市町村選挙管理委員会は、当該選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任する。(期日前投票にかかる選挙立会人は2人。) |
| 当選・落選(とうせん・らくせん)とは? | 慣習的に開票作業が行われているときは候補者は事務所にいないことが多い。自宅か近場のホテルに待機する。当選確実または落選確実になったときに事務所に現れる慣習になっている。最近は最初から事務所にいる人も増えてきたけど。 |
| 当選争訟(とうせんそうしょう)とは? | 選挙が有効に行われたことを前提にして、当選人の決定が誤っていると主張して争うこと。選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。 |
| 統一選挙(とういつせんきょ)とは? | 選挙日程を全国統一で実施する地方公共団体の選挙のことをいいます。各市町村の選挙日を統一することで投票率を上げる狙いがあります。 |
| 統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)とは? | 都道府県知事、区市町村長、都道府県議会議員、区市町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に1回行われる。統一で行われる選挙はある一定の期間に任期満了する選挙であり、毎回特例法によって定められる。都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国的に同じ日に行う選挙。4年に1回行われる。 |
| 入場整理券(にゅうじょうせいりけん)とは? | 投票を行うための整理券のことをいいます。あくまで整理券であるため、これがなくても口頭で本人確認ができれば投票を行うことができます。取手市の場合は、封書型のものを各世帯に配布しており、1世帯につき6名の氏名や投票所名等が連記されております。 |
| 任期(にんき)とは? | 選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間。参議院議員は6年、その他の選挙で選ばれたものは4年。選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。 |
| 任期満了(にんきまんりょう)とは? | 議員や長の任期が終了すること。 |
| 買収罪(ばいしゅうざい)とは? | 票の獲得のために、立候補者やその関係者が有権者に金品などの利益を与えたり、申込みや約束をすることにより成立した罪。票の獲得のために金品など利益を供与するもの。申込みや約束だけでも罪が成立する。 |
| 比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ)とは? | 政党等が候補者の名簿を届け出、得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員180名、参議院議員96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数になっている。政党等が候補者の名簿を届け出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員では180名、参議院議員では96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。政党の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員180名、参議院議員96名(3年ごとに48名ずつ)の定数となっている。 |
| 秘密投票(ひみつとうひょう)とは? | 憲法で定められている「投票の秘密は保障される」という選挙の基本原則のひとつで、自由な意思による選挙権の行使を保障するためのもの。「投票の秘密は保障される」という選挙の基本原則のひとつ。自由な意思による選挙権の行使を保障するために憲法で定められている。 |
| 被選挙権(ひせんきょけん)とは? | 国会議員や都道府県・区市町村の議会議員、長に就くための選挙に国民や市民の代表として立候補することができる権利のこと。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に就くための選挙に立候補することができる権利のこと。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。積極的要件としては、衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること、参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること、都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。市町村長は日本国民で満25歳以上であること。市町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を持っていることである。消極的要件は選挙権の消極的要件とほぼ同様である(選挙権の項参照)。 |
| 被選挙権の消極的要件(ひせんきょけんのしょうきょくてきようけん)とは? | 選挙に立候補するために、ひとつでも当てはまってはいけない条件。(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 (2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く) (3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。 (4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 (5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 (6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者選挙に立候補するために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。 |
| 被選挙権の積極的要件(ひせんきょけんのせっきょくてきようけん)とは? | 選挙に立候補するために必ず備えていなければならない一定の要件。衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること。参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること。都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。市区町村長は日本国民で満25歳以上であること。市区町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。選挙に立候補するために、その人が必ず備えていなければならない一定の資格。 |
| 非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)とは? | 政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。比例代表選挙の一つの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順序」がつけられていない名簿をもとに行われる。参議院比例代表選挙で採用されていて、この場合は候補者個人の得票数の順位が当選の順位となる。 |
| 不在者投票(ふざいしゃとうひょう)とは? | ある市区町村の選挙人名簿に登録されている者が出張等の理由で当該市区町村で投票を行えない場合に、滞在先の市区町村で投票を行うことをいいます。不在者投票ができる期間は公示日の翌日または告示の翌日から投票日前日までとなっております。投票日に投票所に行けない人が、出張、滞在先の市区町村や病院、老人ホームなどで投票日前に投票する制度。仕事以外の理由でもできる。 |
| 普通選挙(ふつうせんきょ)とは? | 納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない選挙。 |
| 文書図画(ぶんしょとが)とは? | 物体に記載された意思表示であって、文字またはその他の符号によって表示されたものを文書、象形によって表示されたものを図画といいます。 |
| 平等選挙(びょうどうせんきょ)とは? | 各選挙人誰もに選挙権を平等に保障する選挙。 |
| 補欠選挙(ほけつせんきょ)とは? | 議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。(類語:再選挙)現職の議員が死亡したり、辞職したりすると議員定数に欠員が生じます。公職選挙法では、一定数以上の欠員が生じた場合その欠員を埋めるために選挙を行わなければならないと規定しており、この欠員を埋めるための選挙を補欠選挙といいます。 |
| 法定選挙運動費(ほうていせんきょうんどうひよう)とは? | 法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。 |
| 法定得票数(ほうていとくひょうすう)とは? | 衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙で法律で定められた当選人となるために必要な、一定数以上の得票数。 |
| 本人届出(ほんにんとどけで)とは? | 立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。(類語:推薦届出) |
| 名簿(めいぼ)とは? | 選挙の中で極めて重要なのが支持団体などから提供される名簿。この名簿をどれくらい集められるかが選挙戦を左右する場合も多い(特に地方選挙)。「○○(支持団体)の推薦を受けて頑張っております、誰々です」「○○(議員や著名人)の紹介でご挨拶させて頂きます、誰々です」など、どこの紹介かを明らかにして「支持固め」に使われる。同窓会名簿が使われる場合もあるが、最近は禁止されているケースも多い。ちなみに同窓生は割と高い確率で支持者になってくれる。 |
| 洋上投票(ようじょうとうひょう)とは? | 遠洋区域を航行する船舶等の船員が船舶からファクシミリで投票できる制度。対象となる船員はあらかじめ区市町村選挙管理委員会に申請を行い選挙人名簿登録証明書を受けている人で、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行うことができる。遠洋区域を航行する船舶等の船員が、船舶からファクシミリで投票できる制度。指定船舶に乗船する船員は、市区町村の選挙管理委員会からあらかじめ選挙人名簿登録証明書の交付を受けておく必要がある。 |
| 立会人(たちあいにん)とは? | 各投票所にボランティアを立会人として派遣する。各陣営の立会人はずっと座って投票行動が正しく行われているかを見守る。投票時間終了後、投票箱が公民館などに集められるが、ここにも各陣営から人を派遣する。開票作業で文字が汚かったりして誰に投票したのか判別がつきにくいものがある。それを「これは誰々に投票したものです」と主張する役目である。判別がつかない場合は、1票を分割する。たまに選挙区の最終開票結果で小数点がついていることがあるが、これは各陣営で1票を分割したことによるものである。また開票状況から情勢を事務所に速報を入れる。 |
| 立候補の禁止と制限(りっこうほのきんしとせいげん)とは? | 公職選挙法によって厳しく定められている、被選挙権を持たない人が国政や地方自治体の選挙に立候補できない決まり。ほかに連座制による立候補禁止期間による制限、複数の選挙への重複立候補の制限などがある。被選挙権を持たない人は国政や地方自治体の選挙に立候補できない。公職選挙法によって厳しく定められている。また連座制による立候補禁止期間による制限、複数の選挙への重複立候補の制限などがある。 |
| 立候補制度(りっこうほせいど)とは? | 立候補を届け出た人以外は当選できない、と定めた制度。日本の選挙の大原則で、公職につく意思のない人を選挙で選ばないようにするための制度。公職につく意思のない人を選挙で選ばないようにするために、立候補を届け出た人以外は当選できない、と定めた制度。日本の選挙の大原則。 |
| 連座制(れんざせい)とは? | 候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。 |
| 労務者(ろうむしゃ)とは? | 選挙において単純労務に従事する者。選挙運動に必要な物品の運搬や演説会の会場設営などが単純労務にあたる。労務者に対しては規定の範囲内で報酬を支払うことが可能であり、事前の届出も不要である。 |
■ポスター広告PR代行(商用・政治)
■ポスター広告PR党《入党のご案内》
■ポスター広告PR党《ポスター貼りのポスターとは?》
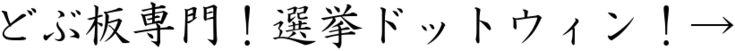

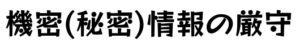
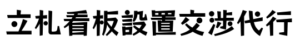
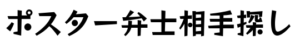
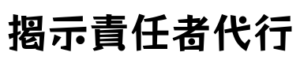
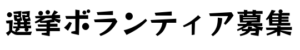
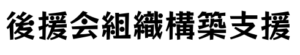
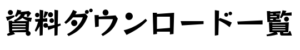
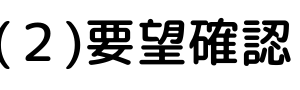



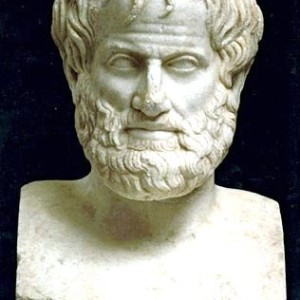


この記事へのコメントはありません。