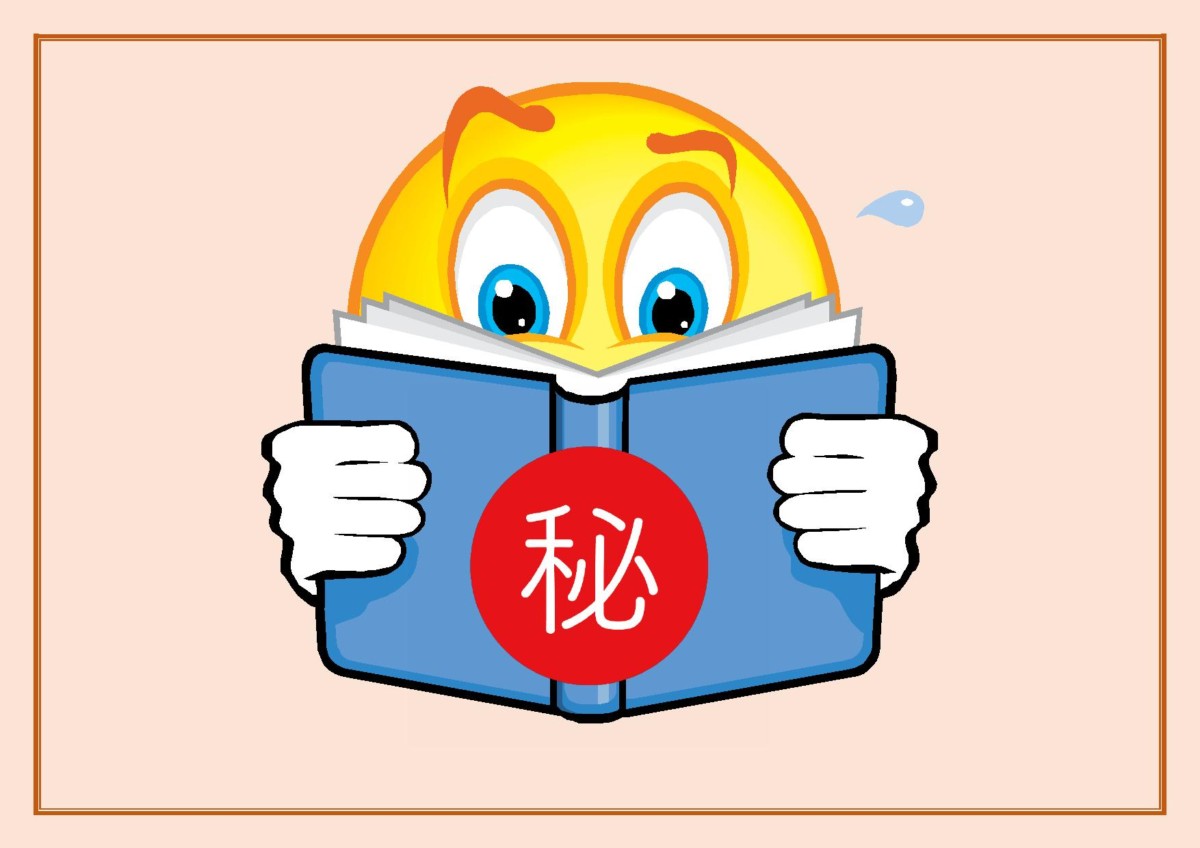
「公職選挙法」に関する裁判例(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
裁判年月日 平成27年 3月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)299号
事件名 投票効力無効取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA03318024
要旨
◆平成26年2月23日に実施された本件土地区画整理審議会委員の選挙(本件選挙)で当選しなかった原告が、被告市は違法に原告を被選挙権のない候補者として取り扱ったなどとして、本件選挙における原告に対する投票の効力を無効とした処分及び原告が投じた投票を無効とした処分の各取消しを求めるとともに、原告が本件土地区画整理審議会の予備委員の地位を有することの確認を求めた事案において、原告が取消しを求める対象たる処分を、個々の投票の効力に係る決定を踏まえてされた予備委員選出公告からの除外と解し、本件各取消しの訴えを適法とした上で、被選挙権を有することの証明に関する確認書面取得に係る被告市への委任状に取得手数料300円を添えて提出するように市長が定め、原告がこの定めに沿った対応をしなかったために被告市が原告を被選挙権のない者として扱ったことは適法であるから、これを踏まえてされた予備委員選出公告からの除外は適法であるなどとして、請求を棄却した事例
参照条文
土地区画整理法63条4項2号
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法10条1項
裁判官
小林宏司 (コバヤシコウジ) 第41期 現所属 最高裁判所上席調査官
平成28年2月22日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成24年1月10日 ~ 最高裁判所事務総局審議官
平成21年4月1日 ~ 平成24年1月9日 最高裁判所調査官
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 事務総局民事局第一課長、第三課長、広報課付
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 事務総局民事局第二課長
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 事務総局行政局参事官
平成11年5月9日 ~ 依願退官
平成10年4月1日 ~ 平成11年5月8日 大阪地方裁判所
平成8年3月21日 ~ 平成10年3月31日 事務総局広報課付、秘書課付
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月20日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所
徳井真 (トクイマコト) 第55期 現所属 秋田地方・家庭裁判所大館支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 秋田地方・家庭裁判所大館支部(支部長)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成26年3月31日 検事(法務省大臣官房司法法制部付)
平成20年4月1日 ~ 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 那覇家庭裁判所、那覇地方裁判所
平成16年10月16日 ~ 平成17年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成14年10月16日 ~ 平成16年10月15日 札幌地方裁判所
堀内元城 (ホリウチモトキ) 第56期 現所属 鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部(支部長)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 事務総局家庭局付
平成15年10月16日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所
引用判例
昭和39年10月29日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)296号 ごみ焼場設置条例無効確認等請求事件
昭和38年 9月26日 最高裁第一小法廷 判決 昭38(オ)563号 行政処分取消請求事件
関連判例
昭和39年10月29日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)296号 ごみ焼場設置条例無効確認等請求事件
Westlaw作成目次
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 平成26年2月23日に実施さ…
2 原告が,○○土地区画整理審議…
第2 事案の概要
1 本件審議会委員の選挙に係る制…
(1) 委員と予備委員
(2) 委員の選挙
(3) 予備委員の選出
2 前提事実(顕著な事実並びに掲…
(1) 被告は,本件土地区画整理事業…
(2) 被告は,本件審議会委員につき…
(3) 原告は,平成26年2月7日,…
(4) 羽村市長は,平成26年2月1…
(5) 本件選挙で選挙すべき委員の定…
(6) 原告は,平成26年7月2日,…
3 争点
(1) 本件各取消しの訴えの適法性(…
(2) 原告が本件審議会の予備委員の…
4 上記争点に対する当事者の主張…
(1) 争点(1)(本件各取消しの訴…
(2) 争点(2)(原告が本件審議会…
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各取消しの訴…
(1) 委員の選挙及び予備委員の選出…
(2) 予備委員選出手続における処分
(3) 本件における取消請求の対象
(4) 被告が原告を被選挙権のない者…
(5) 小括
2 争点(2)(原告が本件審議会…
第4 結論
裁判年月日 平成27年 3月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)299号
事件名 投票効力無効取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA03318024
東京都羽村市〈以下省略〉
原告 X
東京都羽村市〈以下省略〉
被告 羽村市
代表者兼処分行政庁 羽村市長 A
指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 平成26年2月23日に実施された「福生都市計画事業○○土地区画整理事業」の「審議会委員選挙」において,被選挙権者であった原告に対する投票の効力を無効とした処分及び原告が投じた投票を無効とした処分をいずれも取り消す。
2 原告が,○○土地区画整理審議会委員の予備委員としての地位を有することを確認する。
第2 事案の概要
本件は,平成26年2月23日に実施された「福生都市計画事業○○土地区画整理事業」(以下「本件土地区画整理事業」という。)の土地区画整理審議会(以下「本件審議会」という。)委員の選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補したが,当選しなかった原告が,被告は違法に原告を被選挙権のない候補者として取り扱ったものであるなどとして,本件選挙における原告に対する投票の効力を無効とした処分及び原告が投じた投票を無効とした処分の各取消し(以下「本件各取消しの訴え」という。)並びに原告が本件審議会の予備委員の地位を有することの確認を求める事案である。
1 本件審議会委員の選挙に係る制度の概要
本件審議会委員の選挙に係る制度のうち本件に関係する部分は,土地区画整理法(以下「法」という。),土地区画整理法施行令(以下「令」という。)及び福生都市計画事業○○土地区画整理事業施行規程(平成14年羽村市条例第37号。以下「本件施行規程」という。乙4)に,それぞれ別紙2のとおり定められている(以下,法,令及び本件施行規程を併せて「本件各法令」という。)。その概要は,次のとおりである。
(1) 委員と予備委員
土地区画整理審議会の委員は,政令で定めるところにより,施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が,それぞれのうちから各別に選挙する(法58条1項)。また,同審議会に,施行規程で定めるところにより,施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができ(法59条1項),委員に欠員を生じた場合は,施行規程で定めるところにより,予備委員をもってこれを補充する(同条5項)。
(2) 委員の選挙
委員は確定選挙人名簿に記載された選挙人がこれらの者のうちから選挙するが(令23条),施行規程で定めた場合においては,候補者のうちから選挙するものとすることができる(令24条1項)。本件土地区画整理事業については,候補者のうちから選挙する立候補制が採られている(本件施行規程12条)。
委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては,選挙人は,所定の期間内に,立候補届を市町村長等に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができ(令24条2項),立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は,市町村長等が定める(同条3項)。
選挙に当たっては,市町村長等によって,選挙場ごとに,投票及び開票に関する事務を担任する選挙管理者が任命される(令27条)。選挙は無記名投票によって行われ(令29条),選挙管理者は,開票に当たって立会人の立会の下に投票を点検し(令33条1項),立会人の意見を聞いて,投票の効力を決定し(同条2項),投票の点検が終わると,有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し,直ちにその結果を市町村長等に報告する(同条3項)。その際,被選挙権のない者の氏名を記載した投票は無効とされる(令34条1項4号)。
上記報告を受けた市町村長等は,直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し,当選人を定め(令35条1項),当選人の氏名及び住所を公告するとともに,当選人に対して当選の旨を通知する(同条5項)。当選人の当選の効力は,上記公告があった日から生じ(令37条),選挙人又は当選しなかった者は,選挙又は当選の効力に関する異議がある場合においては,所定の期間内に,市町村長等に対し,文書をもってこれを申し出ることができる(令40条)。
(3) 予備委員の選出
審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置き(法59条1項,本件施行規程13条1項),その数は,宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内(ただし,選挙すべき委員の数が1人の場合は1人)であり(法59条2項,本件施行規程13条2項),委員の選挙において,当選人を除いて,一定数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定められる(法59条3項,本件施行規程13条3項)。予備委員を定めた場合は,予備委員となった者にその旨を通知するとともに,令35条5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所を公告する(本件施行規程13条4項)。予備委員として定められた者は,上記公告があった日において予備委員としての地位を取得する(同条5項)。
2 前提事実(顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 被告は,本件土地区画整理事業の施行者であり,原告は,本件土地区画整理事業の施行地区内の宅地について借地権を有する者である(乙4,弁論の全趣旨)。
(2) 被告は,本件審議会委員につき,平成26年2月23日に本件選挙を実施することとし,本件土地区画整理事業の情報誌である「△△」第41号(同年1月15日発行。以下「本件情報誌」という。)に,立候補の受付を行う旨を掲載した。本件情報誌には,未成年者,成年被後見人又は被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は立候補できない旨のほか,立候補の届出に関し,大要,以下のとおりの記載がある。(下線部は,本件情報誌の記載中において下線が引かれている部分である。甲1,乙5,10)
ア 受付期間及び時間
平成26年1月31日(金)~平成26年2月9日(日)まで
午前8時30分~午後5時15分まで(土・日曜日を含む)
イ 届出に必要な書類
(ア) 本人が届出する場合 立候補届1通
推薦による届出の場合 立候補推薦届1通
立候補推薦届承諾書1通
(イ) 成年被後見人又は被保佐人の登記がないことの証明(証明の取得は,全国の法務局又は地方法務局へお問い合わせください。)
※ 「本登記がないことの証明」の取得を市へ委任される場合は,「委任状」に取得手数料300円を添えて,立候補届出又は立候補推薦届出とあわせて提出してください。
(ウ) 「禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」でないことを証明する書類(詳細は,立候補者の本籍地の区市町村へお問い合わせください。)
※ 上記内容の確認を市へ委任される場合は,「委任状」を立候補届出又は立候補推薦届出とあわせて提出してください。
(エ) 選挙公報原稿
(3) 原告は,平成26年2月7日,候補者の種類を「借地権のうちから選挙される委員の候補者」として,本件選挙への立候補を届け出るとともに,上記(2)イ(イ)の証明に係る申請及び受領に関する一切につき,羽村市長を代理人として権限を委任する旨の委任状を提出したが,取得手数料300円を委任状に添えて提出しなかった(甲2,弁論の全趣旨)。
(4) 羽村市長は,平成26年2月17日,原告に対し,「立候補届出に必要な書類等の提出について(通知)」(乙1)と題する書面により,①立候補届出に必要な書類のうち,成年被後見人又は被保佐人とする記録について「登記されていないことの証明」,若しくは同証明を市が代理申請し受領するために必要な収入印紙代300円について提出するよう,原告が立候補届出を提出した際に伝えたが,未だ提出がないこと,②原告自ら成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明を取得する場合には,遅くとも選挙当日である同月23日午後8時までに,市に代理申請を委任する場合には収入印紙代300円を同月20日午後5時15分までに,提出を要すること,③提出がされない場合には,法63条4項2号に掲げる被選挙権の適格性の確認ができないため失格の扱いとなること,④提出に当たっては,既に送付している本件情報誌を参照してほしいことを連絡したが,原告は上記②の証明及び収入印紙代のいずれも上記各期限までに提出しなかった(弁論の全趣旨)。
(5) 本件選挙で選挙すべき委員の定数は,宅地の所有者が選挙する委員について7名,借地権を有する者が選挙する委員について1名であったところ,前者の候補者として8名,後者の候補者として原告を含む2名がそれぞれ立候補した(甲6,7)。
平成26年2月23日,本件選挙の投開票が実施され,宅地所有者から7名,借地権者から1名が本件審議会委員に当選し,また,予備委員として,宅地所有者から1名が選出された。本件選挙の選挙録(甲4)によれば,借地権の部の委員の選挙については,原告ともう1人の候補が立候補し,投票総数16票のうち11票を当該候補が獲得して委員に当選したが,原告については失格とされ,16票から上記11票を除いた5票は,被選挙権のない候補者の氏名を記載したものとして無効投票とされた。その結果,原告は,委員に当選せず,予備委員にも選出されなかった。(甲3,弁論の全趣旨)
(6) 原告は,平成26年7月2日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3 争点
(1) 本件各取消しの訴えの適法性(請求の趣旨1項関係)
(2) 原告が本件審議会の予備委員の地位を有するか否か(請求の趣旨2項関係)
4 上記争点に対する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件各取消しの訴えの適法性)について
ア 被告の主張の要旨
(ア) 原告の被選挙権については,法63条4項に規定する欠格事由(以下,単に「欠格事由」ともいう。)がないことを確認できる書面の提出がなく,これを確認できなかったことから,被選挙権のない者として取り扱ったものであり,また,無効票については,被選挙権のない者の氏名を書いた投票を令34条1項4号の規定に基づき無効として取り扱ったものであって,法令の定めに従って事務を行ったものに過ぎず,本件各取消しの訴えに係る事務の取扱いには公権力の行使に当たる行為は存在しないから,行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には当たらない。
(イ) 原告は,被告が原告を被選挙権を有する者として取り扱っていたのに,開票後になってから遡及して原告を被選挙権のない者として取り扱うのは違法である旨主張するが,被告は投票終了前までは原告の被選挙権の有無が確定していないことから候補者として扱い,投票終了時をもって被選挙権のない者と確定したものである。
イ 原告の主張の要旨
(ア) 本件選挙の効力は,候補者の地位に直接影響を与え,委員に選任され,受諾すれば法律に定める権限を行うことが義務付けられ,令40条において,選挙又は当選の効力に関する異議申立ても許されている。本件においては,開票の結果,原告の氏名を記載した有効票が5票あったにもかかわらず(甲4参照),選挙管理者は,市長に報告する時点で,根拠もなく「被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの」に分類したものであり,かかる選挙管理者の行為は,権限を逸脱した違法なものである。
(イ) 被告は,原告の被選挙権については,欠格事由がないことの確認ができなかった旨主張するが,原告は法63条4項各号に該当しないことを自認し,後記(2)イのとおり明らかに違法な300円の納付以外は必要書類を全て提出している。被告も立候補届を受理し,候補者名等の公告や広報等により,原告を被選挙権を有する者として取り扱っていたのであって,公告の訂正も選挙人への周知も図らず,開票後になってから遡及して原告を被選挙権のない者として取り扱うのは違法であり,原告を始め,状況を知らされずに原告に投じた借地権者の投票権を不当に剥奪することになる。被告の処分通知の有無にかかわらず,原告は不当な事務処理という権力的な事実行為によって被選挙権を剥奪され,公権力の行使による不利益を継続的に受けているのであって,処分性が認められることは明らかである。
(2) 争点(2)(原告が本件審議会の予備委員の地位を有するか否か)について
ア 原告の主張の要旨
以下の事情に照らすと,本件選挙には重大明白な瑕疵があり,違法である。
(ア) 本件情報誌においては,法63条4項の欠格事由のうち,成年被後見人又は被保佐人の登記がないこと(同項2号参照)だけでなく,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと(同項3号参照)についても証明が求められているにもかかわらず,同要件については証明書類が未提出であっても不問に付されており,恣意的で公正を欠く。
(イ) 被告は,原告の立候補時に法63条4項の欠格事由がないことを確認する書面の提出がなかったと主張するが,このような書面の提出は平成16年及び平成21年の過去2回の本件審議会委員の選挙においては求められていなかったにもかかわらず,被告は,本件選挙において,突然,根拠規定も示さず,一方的かつ不当にこれを要求してきたものである。法63条4項は,候補者に欠格事由がないことの立証義務を負わせていると解釈すべきものではなく,他の公務員の任用,選考や選挙における欠格事由の扱いと比較しても,候補者の自己責任において,欠格事由の不存在の証明なしでも申請することができると解すべきである。また,市町村施行者は,法74条により,官公署の長に対し,無償で必要な簿書閲覧等を求めることができるにもかかわらず,不当に候補者に証明を求めているものである。
被告は,立候補の手続について,令24条3項に基づき羽村市長が決定した上,本件情報誌により周知した旨主張するが,本件情報誌は関係権利者に配布するための情報誌に過ぎず,これをもって,300円の納付義務の根拠とできるものではないし,未納付の場合の取扱いについて明記されておらず,原告を失格とした処分の根拠とはならない。
(ウ) 法58条5項は,委員が法63条4項2号又は3号に掲げる者となった場合にその地位を失う旨定めているところ,本件選挙の投票開始から終了までの間,この点に関する原告の身分の変化は生じていない。被告は,欠格事由がないことの確認ができなかったとするが,この点を理由とするのであれば,上記規定の趣旨から,少なくとも,投票開始までに,原告に立候補の不受理を通知し,かつ,選挙権保有者全員にそのことを周知する義務があるというべきである。
(エ) 本件施行規程6条は,事業に要する費用は,次の各号に定めるものを除き施行者が負担すると定め,選挙の費用は除外されていない。よって,事業に要する費用である300円の要求は違法である。
イ 被告の主張の要旨
(ア) 本件選挙の立候補の届出に当たっては,欠格事由がないことを確認するため成年被後見人又は被保佐人の登記がないことの証明(以下,これらを証明するための書面を「確認書面」という。)を必要とし,また,確認書面の提出に代えて,市がこれを代理取得するための委任状及び取得手数料(収入印紙購入代)300円の提出によることができることとしているが,原告は,立候補の届出の際,確認書面を提出せず,また,市による代理取得のための委任状は提出したものの,取得手数料300円を提出しなかった。さらに,被告がこれらの提出を促す通知をしたにもかかわらず,原告は,期限までに確認書面も取得手数料も提出しなかった。その結果,被告は原告について欠格事由がないことの確認ができず,被選挙権のない者として取り扱うことになったものであり,その当然の結果として,原告は予備委員について定めた法59条3項の規定を満たしていないことは明らかである。よって,原告は,予備委員の地位を有しない。
(イ) 法63条4項3号の欠格事由がないこと(禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと)については,証明書類が未提出であっても不問に付されているとの原告の主張については,被告はすべての候補者について確認を行っている。候補者が証明書類を提出する選択も可能とするため必要書類に加えているが,提出がない場合は候補者の本籍地自治体に照会して確認している。
(ウ) 原告は,過去の審議会委員選挙では確認書面の提出が求められていなかった旨主張するが,自ら証明を要する書面については自己負担が原則であることから,本件選挙から立候補の手続の見直しを行い,令24条3項に基づき羽村市長が決定した上,本件情報誌により候補者を含む選挙人に周知して実施したものであって,他にも同様の例があり,何ら問題はない。
(エ) 原告は,被告は法74条により,官公署の長に対し,無償で必要な簿書閲覧等を求めることができる旨主張するが,確認書面は同条により請求することが不可能であるため,候補者に提出を求めるほか方法がない。また,法58条5項に関する原告の主張については,同項は選挙された審議会委員が法63条4項2号又は3号に掲げる者となった場合にその地位を失う旨の規定であり,候補者に関する規定ではない。
(オ) 原告は,取得手数料300円について,本件施行規程6条の事業に要する費用として施行者の負担となる旨主張するが,候補者が自ら証明する書面については自己負担が原則であり,何ら違法な点はない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各取消しの訴えの適法性)について
(1) 委員の選挙及び予備委員の選出についての不服申立て方法
まず,土地区画整理審議会の委員の選挙及び予備委員の選出についての不服を申し立てる方法についてみると,例えば,国会議員等の選挙について定めた公職選挙法においては,民衆訴訟たる選挙訴訟が定められ(202条以下),選挙の効力や当選の効力に関する訴訟は,同法の定める手続に基づくものに限り提起することができると解される(最高裁昭和38年(オ)第563号同年9月26日第一小法廷判決・民集17巻8号1060頁参照)のに対し,土地区画整理審議会の委員の選挙及び予備委員の選出については,本件各法令上,上記のような特別な訴訟についての定めはされていない。土地区画整理審議会の委員の選挙人又は当選しなかった者については,異議の申立てに係る定めが置かれているが(令40条),別途訴訟を提起することは排除されていないし(同条5項),予備委員の選出については異議の申立ても含めて不服申立てに係る具体的な定めはされていないところである。そうすると,予備委員の選出について不服がある者は,行政事件訴訟法の要件を満たす限りにおいて,抗告訴訟である処分の取消しの訴えを起こすことができるものというべきであり,本件訴えのうち処分の取消しを求める部分も,この趣旨のものと解される。
そして,処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)の対象は,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為であるが,この「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は,公権力の主体たる国又は公共団体が行う法令に基づく行為のうち,公権力の行使としてされる行為であって,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照)。
(2) 予備委員選出手続における処分
ところで,原告は,処分取消しを求める訴えの請求において,「原告に対する投票の効力を無効とした処分」及び「原告が投じた投票を無効とした処分」を取消しの対象として挙げるのであるが,かかる処分が具体的に何を指すのかは必ずしも判然としない。そこで,本件審議会の予備委員選出手続において処分といえるものがあるかどうかについて検討する。
本件各法令の定めるところについてみると,先にも述べたとおり,本件審議会委員の選挙においては,選挙管理者は,個別の投票の効力を決定した上,投票の点検が終わると,有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し,直ちにその結果を市町村長等に報告し,これを受けた市長は直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し,当選人を定め,当選人の氏名及び住所を公告し,当選人の当選の効力は,当該公告があった日から生じるとされている。そして,予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて,一定数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定められ,予備委員を定めた場合は,当選人に係る上記公告と併せて予備委員の氏名及び住所を公告し,予備委員として定められた者は,当該公告があった日において予備委員としての地位を取得することとなる。
以上の定めによると,個々の投票の効力を決定するのは選挙管理者であるが,その決定それ自体は,予備委員としての地位の取得の有無を直接決めるものではないから,処分とはいい難い。そして,本件審議会委員の選挙の候補者であって当選人とはならなかったが一定数以上の有効得票を得た者が,予備委員としての地位を取得するかどうかは,予備委員として定められたとの公告をされるか否かによって定まることになるから,その者につき当該公告がされなかったこと(以下「予備委員選出公告からの除外」という。)は,直接その者の権利義務を形成するものというべきであり,その者に対する関係で処分に当たるものというべきである。なお,当該処分の有無は,当選人に係る上記公告に併せて当該候補者を予備委員とする公告がされるか否かによって明らかになるものと解されるし,予備委員となった者の公告をする主体は本件施行規程上明示されていないものの,併せて行われる当選人の公告が市長によって行われることからすれば,予備委員となった者の公告をする者すなわち処分権者は市長であると解される。
(3) 本件における取消請求の対象
原告の主張は,つまるところ,予備委員に選出されなかったことについて不服を述べ,処分の取消しを求めるものであって,上記(2)で見たとおり,予備委員選出公告からの除外が処分と解されることに照らすと,当該主張を善解すれば,原告が取消しを求める対象たる処分とは,個々の投票の効力に係る決定を踏まえてされた予備委員選出公告からの除外を指しているものと解される。このように解すれば,本件各取消しの訴えは適法というべきであり,これを不適法という被告の主張は採用できない。
そして,予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて,一定数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定められるものであるところ,被選挙権のない者の氏名を記載した投票は無効とされる(令34条1項4号)から,原告を被選挙権のない者として扱ったことが適法であるとされるのであれば,仮に原告に対する投票があってもそれは無効票となり,原告が予備委員に選出される余地はなく,これを踏まえてされた予備委員選出公告からの除外は適法ということとなる。そこで,このような観点から,被告が原告を被選挙権のない者と扱ったことの適否について,項を改めて検討する。
(4) 被告が原告を被選挙権のない者と扱ったことの適否
ア 成年被後見人又は被保佐人は委員の被選挙権を有しないところ(法63条4項2号),羽村市長は,候補者に対して,成年被後見人又は被保佐人の登記がないことの証明に係る確認書面の提出を求め,同書面の取得を被告に委任する場合は,委任状に取得手数料300円を添えて提出するものとしている(乙10)が,原告は,委任状のみ提出し,投票終了までに手数料を提出しなかったため,開票段階において被選挙権のない者として取り扱われたものである。そこで,以下,羽村市長が委任状に取得手数料300円を添えて提出するように定めたことの適否,原告がこの定めに沿った対応をしなかったために,被告が原告を被選挙権のない者として扱ったことの適否について順に検討する。
イ 候補者に委任状及び手数料の提出を求めたことの適否
法58条1項は,委員は政令で定めるところにより選挙するとし,これを受けた令24条3項は,立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は,市町村長等が定める旨定める。令24条3項が,市町村長等が定める事項についてそれ以上に特段触れていないことに照らすと,当該事項について定める内容,定める形式,当該定めの周知の在り方等については,市町村長等の合理的な裁量に委ねたものと解される。
そこで,まず,候補者に対し,確認書面の提出又は同書面の取得を被告に委任するための委任状の提出を求めた事情についてみると,本件選挙の前回までの選挙においては確認書面又は委任状の提出が求められていなかったことがうかがわれる(乙11,弁論の全趣旨)のに対して,本件選挙においてその提出を求めることとされたのは,近年プライバシー保護の観点から確認書面の公用申請に関する法務局の取扱いが変更され,地方公共団体の職員による交付請求には,市町村長の職権により家庭裁判所に対し法定後見開始の申立てを行う場合など他に交付を請求する方法がなく職務上の必要性が認められる場合でない限り応じられないものとされ,本件選挙についてはかかる職務上の必要性が認められないとの対応を法務局からされたことが背景事情として存在すると認められる(乙8,9)。この点について,被告があくまで過去の選挙と同様の取扱いを法務局に求めた場合,これを拒否されるなどして円滑な選挙の実施に支障が生じるおそれもあるというべきであるから,候補者に確認書面又は委任状の提出を求めることとしたことが不合理であるとはいえない。
また,委任状を提出する場合に取得手数料300円を添えるよう求めたのは,例えば,選挙権又は被選挙権の要件である施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有することについても,必要に応じて相続を証する書面の提出が必要となるし,法人が立候補する場合には資格証明書等の添付が必要になるところ,これらの場合における上記書面等の取得に係る費用は,選挙権を行使しようとする者や立候補をしようとする者が負担しており(弁論の全趣旨),上記委任状についても,これらと同様に,候補者が自ら証明する書面については自己負担が原則であるとの考えに立って負担を求めることとしたものと解される。このような考えが不合理であるとはいえず,また,負担を求める金額も実費(弁論の全趣旨)の300円であって立候補の妨げになるようなものとはいえない。この点につき,原告は,候補者に手数料を負担させることは,事業に要する費用は所定のものを除き施行者である被告が負担すると定める本件施行規程6条に違反すると主張するが,委員への立候補に要する費用をもってただちに事業に要する費用であるといえるものではないから,この主張は採用できない。
このほか,確認書面又は委任状の提出を求めることの定め方や周知の方法等が不合理であるとみるべき事情もない。
以上検討したところによれば,羽村市長が候補者に確認書面又は委任状の提出を求め,後者を提出する場合には手数料を添えるよう定めたことが,同市長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできない。
ウ 原告を被選挙権のない者として扱ったことの適否
被告は,原告が確認書面の提出をせず,また同書面の取得を被告に委任するための所定の手数料を支払わず,原告に成年被後見人又は被保佐人の登記がないことが確認できなかったことから,被選挙権のない者として扱ったものである。
この点,法63条は,1項において選挙権又は被選挙権を有する者の要件につき定め,同条4項において当該要件を満たしても被選挙権を有しない場合につき定めているが,これらの要件を具体的にどのように認定するかについては具体的に定めていない。そして,先にも見たとおり,羽村市長は,法58条1項及び令24条3項による順次の委任を受けて,被選挙権を有することの証明に係る確認書面又は委任状の提出を求める定めをしたものと解されるところであるが,これは,立候補受付開始から立候補届の締切り,候補者氏名等の公告,投開票及び当選人決定公告等が比較的短期間に行われる本件選挙(乙5参照)において,被選挙権の有無を一義的かつ明確に判断するため,候補者において提出にさほどの困難を伴わない確認書面という確度の高い証明方法に係る公的書類又はこれに代わる手段としての委任状及び手数料を提出させることとし,もって,選挙人による集合的行為として行われる選挙の混乱を防ぐとともに,その円滑な実施を図ろうとしたものと解される。仮に候補者からかかる書面の提出がされなかったにもかかわらず,当該候補者の被選挙権の有無については被告において別途調査の上で確定すべきことを求めるとなれば,法や令の委任に基づき上記のような定めをした趣旨が没却され,円滑な選挙の実施に支障を生じ得ることとならざるを得ない。
比較のために公職選挙法の定めを見ると,同法11条1項は選挙権及び被選挙権を有しない者を挙げるのであるが,同条3項は,市町村長は,その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するものについて同条1項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなったことを知ったときは,遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならないとし,同法86条の4第9項は,立候補の届出のあった者が公職の候補者となることができない者であることを知ったときには,選挙長はその届出を却下しなければならない旨定めている。すなわち,候補者の被選挙権の有無に係る情報が選挙管理委員会に集約され,被選挙権のない者を選挙から予め排除するための手段が与えられており,選挙を施行する側はこれを用いて適切に選挙を実施する責務を有しているといえるのであって,かかる場合において何らかの事情で被選挙権のない者が当選人となり,又は被選挙権を有するにもかかわらずこれがないものとされたような場合には当選の効力に関する同法所定の不服申立てをすることができるものと解される。これに対し,土地区画整理審議会の委員の選挙(公職選挙法上の選挙とは異なり,その候補者は施行地区の所在する市町村等に居住するとは限らないものである。)については,候補者の被選挙権の有無に係る情報収集等のための上記のような手段は設けられておらず,先にも見たとおり,法58条1項は,委員は政令で定めるところにより選挙するとし,これを受けた令24条3項において,立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は,市町村長等が定めるとされているところである。
以上のような法令の定めの差異をも踏まえると,土地区画整理審議会の委員の選挙に関し,被選挙権を有することについての立証の負担を候補者側に合理的な範囲で負わせることが否定されているとは解されず,その結果として,確認書面を提出しないことなどから欠格事由の有無について確認できない者について,被選挙権のない者として取り扱うことを禁じているとまでは解されない。
そして,この点を除き,本件において,原告を被選挙権のない者として扱ったことについて,これを違法・不当とみるべき事情はない。そうすると,被告が原告を被選挙権のない者として扱ったことは適法というべきである。
(5) 小括
以上検討したとおり,被告が原告を被選挙権のない者として扱ったことは適法というべきであるから,これを踏まえてされた予備委員選出公告からの除外は適法ということとなる。したがって,この点に関する原告の主張を採用することはできない。
なお,原告は,被告が本件選挙に係る投票終了時刻まで原告を候補者として取り扱いながら開票段階において原告の被選挙権を否定したことの違法をも主張する。しかしながら,仮に原告が当初から候補者として取り扱われなかった場合に原告が予備委員に選出されることがないのは,事後的に被選挙権を有しないと判断される場合と変わりがないのであるから,原告の主張するような違法は,上記結論を左右するものとはいえない。この点について,原告は選挙人の選択に影響を与えたなどとして違法事由を種々主張するが,前記(1)で見たとおり,本件訴訟は選挙訴訟ではなく主観訴訟である抗告訴訟と解されるから,原告の法律上の利益に関係のない違法事由(行政事件訴訟法10条1項参照)を主張することはできない。
2 争点(2)(原告が本件審議会の予備委員の地位を有するか否か)について
原告は,本件選挙には重大明白な瑕疵があり,違法であるとして,原告が本件審議会の予備委員の地位を有することの確認を求めている。しかしながら,既に見たとおり,予備委員は,予備委員として定められた旨の公告によってその地位を取得するものであるところ,本件において原告が予備委員として定められた旨の公告がされていないのは明らかであるから,原告が予備委員の地位を有するとはいえない。
付言すると,原告に対する予備委員選出公告からの除外処分が違法である場合には,その取消判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)により,原告が予備委員としての地位を得ることになり得るものであるが,先にも見たとおり,原告に対する予備委員選出公告からの除外処分が違法であるともいえない。
第4 結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 徳井真 裁判官 堀内元城)
別紙1
指定代理人目録
小山和茂,細谷文雄,石川直人,中根勉,橋本雅央,山﨑信介,池田明生
以上
別紙2
本件各法令の定め
1 法の定め
(1) 2条(定義)
ア この法律において「土地区画整理事業」とは,都市計画区域内の土地について,公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため,この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。(1項)
イ この法律において「施行者」とは,土地区画整理事業を施行する者をいう。(2項)
ウ この法律において「施行地区」とは,土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。(3項)
(2) 3条(土地区画整理事業の施行)
都道府県又は市町村は,施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(4項)
(3) 52条(施行規程及び事業計画の決定)
都道府県又は市町村は,3条4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては,施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において,その事業計画において定める設計の概要について,国土交通省令で定めるところにより,都道府県にあっては国土交通大臣の,市町村にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。(1項)
(4) 56条(土地区画整理審議会の設置)
都道府県又は市町村が3条4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに,都道府県又は市町村に,土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。(1項)
(5) 57条(審議会の組織)
審議会は,10人から50人までの範囲内において,政令で定める基準に従って施行規程で定める数の委員をもって組織する。
(6) 58条(委員)
ア 委員は,政令で定めるところにより,施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては,工区。)内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が,それぞれのうちから各別に選挙する。(以下略。1項)
イ 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなった場合及び委員が63条4項2号又は3号に掲げる者となった場合においては,委員は,その地位を失う。(5項)
(7) 59条(予備委員)
ア 審議会に,施行規程で定めるところにより,施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。(1項)
イ 予備委員の数は,施行規程で定めるものとし,その数は,それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し,選挙すべき委員の数が1人の場合においては,1人とする。(2項)
ウ 予備委員には,前条1項に規定する選挙において,当選人を除いて,施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において,施行規程で定めるところにより,得票数の多い者から順次なるものとする。(3項)
エ 前条1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては,施行規程で定めるところにより,予備委員をもってこれを補充する。(5項)
(8) 63条(委員の選挙権及び被選挙権)
ア 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,委員の選挙について,各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。(1項)
イ 次の各号のいずれかに掲げる者は,1項の規定にかかわらず,委員の被選挙権を有しない。(4項)
1号 未成年者
2号 成年被後見人又は被保佐人
3号 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(9) 74条(関係簿書の閲覧等)
国土交通大臣,都道府県知事,市町村長若しくは機構理事長等又は72条1項後段に掲げる者は,土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては,施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し,又はその他の官公署の長に対し,無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
2 令の定め
(1) 23条(選挙人)
委員は,確定選挙人名簿に記載された者(以下34条を除き,本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。
(2) 24条(立候補制)
ア 委員は,施行規程で定めた場合においては,候補者のうちから選挙するものとすることができる。(1項)
イ 前項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては,選挙人は,所定の期間内に,立候補届を市町村長等に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができる。(2項)
ウ 前項の立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は,市町村長等が定める。(3項)
(3) 27条(選挙管理者及び立会人)
市町村長等は,選挙場ごとに,投票及び開票に関する事務を担任させるため,その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。
(4) 29条(投票)
委員の選挙は,無記名投票によって行うものとする。
(5) 33条(開票)
ア 選挙管理者は,立会人の立会の下に,投票を点検しなければならない。(1項)
イ 前項の場合においては,選挙管理者は,立会人の意見を聞いて,投票の効力を決定するものとする。その決定に当っては,次条の規定に反しない限りにおいて,その投票をした選挙人の意思が明らかであれば,その投票を有効とするようにしなければならない。(2項)
ウ 投票の点検が終った場合においては,選挙管理者は,有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し,直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。(3項)
(6) 34条(投票の効力)
委員の選挙については,次の各号の一に該当する投票は,無効とする。(1項)
4号 被選挙権のない者の氏名を記載したもの
(7) 35条(当選人の決定)
ア 市町村長等は,33条3項の規定による報告を受けた場合においては,直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し,当選人を定めなければならない。(1項)
イ 市町村長等は,当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果,再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては,直ちに当選人を定めなければならない。(2項)
ウ 前2項の場合においては,施行規程で定める数(中略)以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次当選人を定めるものとし,得票数が同じであるときは,市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。(3項)
エ 1項,2項(中略)の規定により当選人を定めた場合においては,市町村長等は,直ちに当選人の氏名及び住所(中略)を公告するとともに,当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。(5項)
(8) 37条(当選の効力の発生)
当選人の当選の効力は,24条1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては35条5項の公告があった日(中略)から生ずるものとする。
(9) 40条(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)
ア 選挙人又は当選しなかった者は,選挙又は当選の効力に関する異議(中略)がある場合においては,選挙に関しては選挙期日,当選に関しては37条の規定により当選の効力が発生した日又は38条の公告があった日から2週間以内に,市町村長等に対し,文書をもってこれを申し出ることができる。(1項)
イ 市町村長等は,前項の異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から2週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において,決定は,文書をもってし,理由を附けて申出人に交付するとともに,その要旨を公告しなければならない。(2項)
ウ 市町村長等は,1項の規定により選挙の効力に関する異議の申出があった場合において,選挙に関する規定に違反することがあるときは,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り,その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。(3項)
エ 市町村長等は,1項の規定により当選の効力に関する異議の申出があった場合においても,その選挙が前項の場合に該当するときは,その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。(4項)
オ 委員は,選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の提起に対する決定又は判決が確定するまでは,その職を失わない。(5項)
3 本件施行規程の定め
(1) 6条(費用の負担)
事業に要する費用は,次の各号に定めるものを除き施行者が負担する。
ア 法96条2項の規定により定める保留地の処分金(1号)
イ 国の補助金又は東京都の交付金若しくは補助金(2号)
(2) 9条(土地区画整理審議会の設置)
事業を施行するため,法56条1項の規定により福生都市計画事業○○土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(3) 10条(委員の定数)
法57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。(1項)
(4) 12条(立候補制)
法58条1項の規定により選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。(1項)
(5) 13条(予備委員)
ア 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。(1項)
イ 予備委員の数は,宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。(2項)
ウ 予備委員は,委員の選挙において当選人を除いて,次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,市長がくじで順位を定める。(3項)
エ 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者にその旨を通知するとともに令35条5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(中略)を公告するものとする。(4項)
オ 3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。(5項)
(6) 14条(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は,当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
以上
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
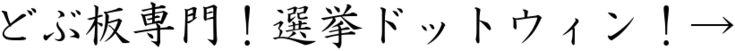



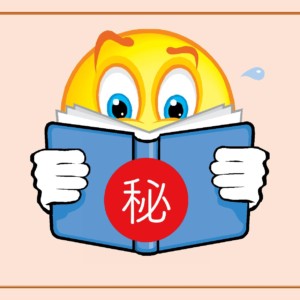
この記事へのコメントはありません。