
政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
裁判年月日 平成30年 4月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA04198012
裁判年月日 平成30年 4月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA04198012
平成28年(行ウ)第144号 難民不認定処分取消請求事件(以下「甲事件」という。),
平成28年(行ウ)第154号 難民不認定処分取消請求事件(以下「乙事件」という。)
福岡県行橋市〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告夫」という。)
同所
原告 X2(以下「原告妻」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
同 鈴木雅子
同 本田麻奈弥
同 小田川綾音
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 別紙1指定代理人目録記載のとおり
主文
1 本件訴えのうち,原告らを難民に認定する旨の処分の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 甲事件
ア 処分行政庁が平成23年5月11日付けで原告夫に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
イ 処分行政庁は,原告夫を難民に認定せよ。
(2) 乙事件
ア 処分行政庁が平成24年10月22日付けで原告妻に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
イ 処分行政庁は,原告妻を難民に認定せよ。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文1,2項と同旨
第2 事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」又は「本国」という。)の国籍を有する外国人である原告らが,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,処分行政庁から,難民の認定をしない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めるとともに,原告らについて,難民である旨の認定をすることの義務付け(以下「本件各義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
1 関係法令の定め
関係法令の定めは,別紙2「関係法令の定め」に記載のとおりである(同別紙で定義した略語は,本文においても用いることとする。)。
2 前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告らの身分事項
ア 原告夫は,1977年(昭和52年)○月○日,バングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人男性である。
イ 原告妻は,1984年(昭和59年)○月○日,バングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人女性である。
ウ 原告らは,2007年(平成19年)3月2日,婚姻した(乙8の1・2,乙11〔4頁〕)。
(2) 原告らの入国及び在留状況
ア(ア) 原告夫は,平成21年7月2日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告夫は,平成21年7月27日,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,在留資格「特定活動」,在留期間「3月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
(ウ) 原告夫は,平成21年10月14日及び平成22年1月18日,東京入管局長から,在留期間を「3月」とする在留期間更新許可を受けた。
(エ) 原告夫は,平成22年1月27日,東京入管局長から,在留資格「特定活動」,在留期間「3月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
(オ) 原告夫は,平成22年4月26日,東京入管局長から,在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受け,同年10月29日,平成23年4月22日及び同年10月31日,平成24年4月27日,同年11月7日,平成25年5月23日,同年12月9日,平成26年6月6日,平成27年1月13日及び同年7月31日,福岡入国管理局長(以下「福岡入管局長」という。)から,いずれも在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた(乙2の1)。
(カ) 原告夫は,平成28年3月31日,福岡入管局長から,在留資格「特定活動」,在留期間「6月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
(キ) 原告夫は,平成28年4月4日,福岡入国管理局(以下「福岡入管」という。)北九州出張所において,資格外活動許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年8月30日,同申請を不許可とした(乙42)。
(ク) 原告夫は,平成28年5月24日,福岡入管北九州出張所において,在留資格変更許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年6月17日,原告夫の上記申請を不許可とし,同日,原告夫にその旨を通知した。
(ケ) 原告夫は,平成28年9月30日,在留資格変更許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年11月24日,同申請を終止処分とし,在留期間「6月」とする在留期間更新許可をした(乙42)。
原告夫は,平成29年5月1日,在留資格変更許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年7月19日,同申請を終止処分とし,在留期間「6月」とする在留期間更新許可をした(乙42)。
イ(ア) 原告妻は,平成24年4月5日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告妻は,平成24年4月16日,福岡入管局長から,在留資格「特定活動」,在留期間「6月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
(ウ) 原告妻は,平成24年9月26日,平成25年5月1日及び同年11月11日,福岡入管局長から,いずれも在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた。
(エ) 原告妻は,平成26年4月21日,福岡入管局長から,在留期間「6月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」とする在留期間更新許可を受けた。
(オ) 原告妻は,平成26年11月17日及び平成27年6月16日,福岡入管局長から,在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた。
(カ) 原告妻は,平成28年2月1日,福岡入管局長から,在留資格「特定活動」,在留期間「6月」,指定活動「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。
(キ) 原告妻は,平成28年4月4日,福岡入管北九州出張所において,資格外活動許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年8月30日,同申請を不許可とした(乙43)。
(ク) 原告妻は,平成28年7月25日,在留資格変更許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年9月30日,同申請を終止処分とし,在留期間「6月」とする在留期間更新許可をした(乙43)。
原告妻は,平成29年3月21日,在留資格変更許可申請をしたが,福岡入管局長は,同年5月25日,同申請を終止処分とし,在留期間「6月」とする在留期間更新許可をした(乙43)。
(3) 原告夫の難民認定申請に係る経緯等
ア 原告夫は,平成21年7月16日,東京入管横浜支局(以下「横浜支局」という。)において,難民認定の申請(以下「本件原告夫申請」という。)をした(乙3)。
イ 横浜支局難民調査官は,平成21年10月15日,原告夫から事情を聴取した。
福岡入管難民調査官は,平成23年3月18日,原告夫から事情を聴取した。
ウ 処分行政庁は,平成23年5月11日,原告夫に対し,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件原告夫不認定処分」という。)をした。
エ 原告夫は,平成23年6月14日,本件原告夫不認定処分の通知を受け,本件原告夫不認定処分に対する異議申立てをした。
オ 福岡入管難民調査官は,平成25年11月26日,原告夫から事情を聴取した。
平成26年7月4日,原告夫の口頭意見陳述及び審尋が行われた。
福岡入管難民調査官は,同年11月25日,原告夫から事情を聴取した。
カ 処分行政庁は,平成27年8月31日,上記エの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年10月6日,原告夫に対し,その旨の通知をした。
キ 原告夫は,平成27年10月16日,処分行政庁に対し,2回目の難民認定申請をした。
ク 処分行政庁は,平成28年4月27日,上記キの原告夫の難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分をし,同年6月21日,原告夫にその旨通知した。
ケ 原告夫は,平成28年6月21日,処分行政庁に対し,上記クの原告夫に係る難民不認定処分について,審査請求をした。
(4) 原告妻の難民認定申請に至る経緯等
ア 原告妻は,平成24年4月16日,福岡入管において,難民認定申請をした(乙14)。
イ 福岡入管難民調査官は,平成24年9月26日,原告妻から事情を聴取した。
ウ 処分行政庁は,平成24年10月22日,原告妻に対し,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件原告妻不認定処分」といい,本件原告夫不認定処分と併せて「本件各不認定処分」という。)をした。
エ 原告妻は,平成24年11月7日,本件原告妻不認定処分の通知を受け,本件原告妻不認定処分に対する異議申立てをした。
オ 平成26年7月4日,原告妻の口頭意見陳述及び審尋が行われた。
福岡入管難民調査官は,同年11月25日,原告妻から事情を聴取した。
カ 処分行政庁は,平成27年8月31日,上記エの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年10月6日,原告妻に対し,その旨の通知をした。
キ 原告妻は,平成27年10月16日,処分行政庁に対し,2回目の難民認定申請をした。
ク 処分行政庁は,平成28年4月27日,上記キの原告妻の難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分をし,同年6月21日,原告妻にその旨通知した。
ケ 原告夫は,平成28年6月21日,処分行政庁に対し,上記クの原告妻に係る難民不認定処分について,審査請求をした。
(5) 本件各訴えの提起
原告らは,平成28年3月31日,本件各訴えを提起した(顕著な事実)。
3 争点
(1) 本件原告夫不認定処分の適法性(原告夫の難民該当性)
(2) 本件原告妻不認定処分の適法性(原告妻の難民該当性)
(3) 本件各義務付けの訴えの適法性等
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件原告夫不認定処分の適法性(原告夫の難民該当性))について
(原告らの主張)
ア 原告夫は,バングラデシュのチッタゴン丘陵地帯(以下「CHT」という。)の先住のジュマ民族であるところ,同地域の先住民族は,政府主導のベンガル人入植政策によって苛烈な抑圧に置かれてきた。原告夫は,現に,何度も拘束や暴力を受けてきたものであり,これは,正に入植政策に反対するジュマ民族の置かれている状況そのものであり,現在に至っても,入植者による襲撃事件やチッタゴン丘陵人民連帯連合会(以下「PCJSS」という。)と統一人民民主戦線(以下「UPDF」という。)との間の暴力事件が継続して起きている。
イ 原告夫は,UPDFの活動家であったところ,UPDFは,1997年(平成9年)に締結された和平協定に反対する勢力であり,政府からもPCJSSからも抑圧を受けている。特に,PCJSSとUPDFとの間の確執と紛争が継続していることは,様々な情報が示している。
また,原告夫は,2008年(平成20年)4月3日,PCJSSのメンバーに自宅を襲撃され,同人らに原告夫の母親を殺害された。
ウ 原告夫は,単にUPDFの活動家であったのみならず,2005年(平成17年)に出家してUPDFの活動をしていないにもかかわらず,2006年(平成18年)にUPDFのメンバーとして発砲事件を惹起したなどとして逮捕状(以下「本件逮捕状」という。)の発付を受けており,UPDFの活動家として,また,国家に対する反逆者として位置付けられているものであって,そこから認識し得る危険度は計り知れないものがある。
エ 原告夫は,日本においても,ジュマ民族・CHT問題について取組を継続して行っており,特にジュマボイスに加わって活動に参加しているところ,ジュマボイスで活動している別のメンバーが国家反逆罪でバングラデシュ政府から逮捕状を発付されており,ジュマボイスの活動が明らかに政府当局に敵対する位置付けとなってしまっていることは,そのメンバーである原告夫に対して逮捕状が発付されていることからも明確になっており,その中でジュマボイスの活動は国家への反逆と明示されている。
オ 以上を総合すれば,原告夫に対する迫害のおそれがあることは明白である。
(被告の主張)
ア(ア) 入管法が定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により,難民条約の適用を受ける難民をいい,これらの各規定によれば,難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの等をいう。
(イ) 上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該難民認定申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
(ウ) いかなる手続を経て難民認定がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国の入管法及びその関係法令の規定や,難民の認定をする旨の処分の授益処分としての性質等に照らせば,難民であることの資料の提出義務と立証責任は難民認定申請者が負担し,同申請者において合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないものと解される。
イ(ア) 原告らは,原告夫がチャクマ族あるいはジュマであることをもって,原告らがバングラデシュに帰国すれば,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,CHTを取り巻く状況は,先住民族であるチャクマ族を始めとするジュマと後発入植者であるベンガル人との間の土地等の利権をめぐる根深い対立が根底にあり,また,先住民族であるジュマ同士でさえ,和平協定をめぐって対立している状況にあるところ,このような状況において,バングラデシュ政府は,和平協定の全面的履行に向けて尽力している上,他にCHTの発展や問題解決に向けて様々な施策を講じることによって一定の成果を上げており,バングラデシュ政府がCHTにおける問題を殊更に放置しているとか,チャクマ族又はジュマを迫害しようとしているような状況にあるとはいえない。
また,CHT内において,今なお相当数の武器や銃弾等を所持する勢力が存在することが推認される上,PCJSSもUPDFも,度々,違法に通行料などの課徴金を住人等から徴収しているほか,違法薬物を大量に所持しているといった報道も見られるところ,これらの事情は,そもそも,その政治的動機の有無にかかわらず,政府による規制の対象となり得る事情であるから,バングラデシュ政府が,これらを敢行している者に対し制裁を加えることは必ずしも不当であるとはいえない。むしろ,PCJSSやUPDF及びその構成員ないし協力者の活動やこれらの者が多く住む地域であるCHTを調査したり,事情に応じてその構成員等を訴追ないし処罰などすることや,予防的措置のため当該地域のパトロールや取締りを強化するといったことは,治安を維持し国民の安全を図るために行った対応であるとも解されるのであって,これを直ちに「迫害」と結びつけることは相当ではなく,近年のCHTにおける具体的状況からすれば,バングラデシュ政府軍や警察の存在は,飽くまで同地帯における治安維持目的の側面が大きく,これらが積極的にチャクマ族やジュマへの襲撃に加担していると断じることはできない。
以上より,原告らがチャクマ族あるいはジュマであることを理由にバングラデシュ政府から迫害を受けるとは認められない。
(イ)a 原告らは,原告夫が,かつてバングラデシュにおいてUPDFで活動していたことを理由に,バングラデシュ政府から迫害を受けたり,PCJSSから危害を加えられたりするおそれがある旨を主張する。
しかし,そもそも,原告夫がUPDFのメンバーであることを裏付ける証拠は何ら提出されていない。
また,原告夫の供述によれば,原告夫は,1999年(平成11年)1月にPCJSSからUPDFに移籍したものの,その具体的な活動内容は,補佐的なものにすぎなかった上,2005年(平成17年)1月には,僧侶になるために出家し,以後,UPDFの活動は行っておらず,また,UPDFに加入後に,政府や警察,PCJSSから迫害を受けたことはなかったと述べている。
さらに,原告夫は,難民異議申立手続における口頭意見陳述及び審尋において,難民審査参与員に対し,原告夫がバングラデシュを出国しなければならないと思った理由について,その当時,どこも信用のおけないような,紛争も絶えないというような状況の中,生活することができないなどという飽くまで漠然とした抽象的な危険性に対して恐怖を抱いていたことを供述するにとどまっている。
その上,原告夫は,カグラチョリ県にいれば,恐怖を感じるようなことはなく,難民異議申立手続における口頭意見陳述及び審尋の時点でも,カグラチョリ県全体がUPDFの支配下にあるため,おおむね安全である旨述べていることからすれば,原告夫がバングラデシュに帰国したとしても,かつて生活したこともあるカグラチョリ県に居住することによって,PCJSSからの危害を回避することは十分に可能なはずである。
以上より,仮に,原告夫がUPDFのメンバーであったとしても,そのことを理由にバングラデシュ政府やPCJSSに殊更注視されるような存在であったとは認められないし,バングラデシュに帰国したとしても,バングラデシュ政府又はPCJSSから迫害等を受ける具体的なおそれがあるとも認められない。
b 原告らは,UPDFにおける活動を理由にPCJSSから危害を加えられるおそれがある事情として,2008年(平成20年)4月3日に原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害された旨を主張する。
しかし,そもそも原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたことを裏付ける証拠は何ら提出されていない。
この点をおくとしても,原告夫は,母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたのは,原告夫がスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)からバングラデシュに帰国した後の2008年(平成20年)4月3日であった旨を供述するところ,2007年(平成19年)2月14日付けでバングラデシュ政府から発給を受けた自己名義の旅券の母の氏名欄には,既に故人であることを示す「LATE」の記載が存在し,原告夫の上記供述は旅券の記載という客観的証拠に明らかに反するものである上,その説明は内容が不自然不合理で,かつ,変遷しており,到底信用することができない。
以上より,原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたとは認められない。
(ウ) 原告らは,原告夫に対して逮捕状が発付されていることをもって,原告夫がUPDFの活動家として国家に対する反逆者に位置付けられているとして,原告夫が難民に該当する旨を主張する。
しかし,原告夫は,何ら合理的な理由なく,逮捕状が発付されたことを認識するに至った経緯等に関する供述を変遷させているところ,このような変遷は不自然かつ不合理である。
また,原告夫は,本件逮捕状が発付されたとする日後に,バングラデシュ政府から自己名義の旅券の発給を受けており,その後,正規の手続を経てバングラデシュを出国した上で,一旦帰国し,再び正規の手続によって出国しているところ,原告夫は,バングラデシュの出入国に際し,何ら問題がなかったことを自認している。さらに,原告夫は,バングラデシュへ帰国した理由について,父親に金の無心をすることが主な理由であった旨,カグラチョリの方に身を置いていたため,恐怖を感じるようなことはなかった旨を述べているところ,このような原告夫の言動自体,およそ政府から逮捕状の発付を受け,身体を拘束されるかもしれないという恐怖を抱いている者の言動として不可解であるというほかない。
以上より,本件逮捕状の発付に関する原告夫の供述は到底信用することができず,仮に,原告らが主張ないし供述するような事情があったとしても,原告夫の実際の言動に照らせば,バングラデシュ政府が原告夫に特別の関心を寄せるほどのものではなく,原告夫について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情や,個別かつ具体的な事情が存するとも認められない。
(エ) 原告らは,ジュマボイスで活動している別のメンバーが国家反逆罪でバングラデシュ政府から逮捕状を発付されており,原告夫も本邦でジュマボイスの活動に参加していることから,原告夫がバングラデシュに帰国すれば,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,原告夫は,難民認定手続において,本件原告夫難民不認定処分時までの間のみならず,原告夫の異議申立てを棄却する旨の決定がされるまでの間でさえも,ジュマボイスにおける活動について何らの申告ないし供述をしていなかった。仮に,原告夫が本邦でジュマボイスの活動に参加していたとしても,原告夫が上記のような事情を自身の難民該当性を基礎付ける重要な事実であると考え,バングラデシュに帰国すると当該事情により自らの命に危険が及ぶと考えていたのであれば,難民認定申請の段階から上記事情について申告してしかるべきであって,原告夫が難民認定申請の段階において本邦でジュマボイスの活動に参加していた事実を何ら申告せず,その後も供述しなかったことは不自然かつ不合理であるといわざるを得ない。したがって,原告夫が本邦でジュマボイスの活動に参加していることをもって,難民該当性を基礎付けることはできない。
(オ) 他方,原告夫は,バングラデシュ政府から正規に自己名義の旅券の発給を受け,何らの問題もなく正規に本国を出国した上,一旦本国に帰国していることからして,本国政府が原告夫を迫害の対象としておらず,原告夫が本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことを示すものである。
また,原告夫は,2度にわたり,スリランカに入国しているが,自身がバングラデシュにおいて迫害を受けるおそれを抱いており,本件逮捕状も発付されていたのであれば,一旦とはいえ,スリランカからバングラデシュに帰国することは迫害のおそれに直面する事態を招きかねないものであるから,スリランカ政府に対して自身が難民であることを申し出て庇護を求めてしかるべきである。さらに,原告夫は,2008年(平成20年)7月6日にタイ王国を出国して大韓民国(以下「韓国」という。)へ渡航した際にも,難民であることを申告しなかったというのである。これらは,迫害を受けるおそれを抱く者の行動として,切迫感及び危機感に欠け,不自然かつ不可解である。
ウ したがって,原告夫には,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ような個別具体的な客観的事情が存するとは認められないから,原告夫は,難民に該当しない。
(2) 争点(2)(本件原告妻不認定処分の適法性(原告妻の難民該当性))について
(原告妻の主張)
世界人権宣言16条3項,市民的及び政治的権利に関する国際規約23条1項,難民条約採択時の最終文書の記載によれば,家族統合は難民保護の重要な一内容を形成しており,原告夫が難民である以上,原告妻も難民として保護されなければならない。
(被告の主張)
上記(1)(被告の主張)のとおり,原告夫は難民に該当しないから,原告夫が難民である以上,原告妻も難民に該当する旨の原告妻の主張は,その前提において理由がない。
この点をおくとしても,難民該当性は,申請者ごとの個々の事情に基づいて判断されるべきものであって,仮に原告夫が難民であるとしても,当然に,その家族が難民に該当するものではない。
(3) 争点(3)(本件各義務付けの訴えの適法性等)について
(原告らの主張)
前記(1)(原告らの主張)及び上記(2)(原告妻の主張)のとおり,本件各不認定処分の取消請求は認容されるべきであり,また,原告らが難民に認定されるべきことは,法令の規定からも明らかであって,原告らに対して難民の認定をすべき旨が命ぜられるべきである。
(被告の主張)
本件各義務付けの訴えは,申請型の義務付けの訴えであり,併合提起された本件各不認定処分の取消請求が認容されることが訴訟要件(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)であるところ,前記(1)及び(2)各(被告の主張)のとおり,本件各不認定処分は適法であって,取り消されるべきものには当たらないから,上記訴訟要件を欠き,不適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件原告夫不認定処分の適法性(原告夫の難民該当性))について
(1) 難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定しているところ,難民条約及び難民議定書の上記規定によれば,入管法にいう「難民」(ただし,無国籍者を除く。以下,単に「難民」という。)とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているとの主観的事情があるのみでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
イ 難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項が,法務大臣は,難民認定申請者が提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨規定しており,難民認定について難民認定申請者が資料を提出することを前提としている。また,難民認定を受けた者は,入管法61条の2の2第1項に基づき定住者の在留資格を取得できるなど,有利な法的地位が与えられることになるから,難民認定は,いわゆる授益処分に当たるものであるところ,一般に,授益処分については,その処分を受ける者が,根拠法令の定める処分要件が充足されていることについて立証責任を負担するものと解される。以上によれば,難民該当性の立証責任は,難民認定申請者にあると解するのが相当である。
(2) バングラデシュの政治情勢
ア バングラデシュの一般情勢
(ア) バングラデシュの独立から民主主義体制の確立まで
東パキスタンとしてパキスタンに属していた東ベンガル地方は,1947年(昭和22年),英領インドから分離独立した後,1971年(昭和46年)3月26日,パキスタンから独立を宣言して内戦に突入し,更にインドの介入を経て,同年12月16日,パキスタン軍の降伏によりバングラデシュとして独立した。パキスタンにおいては,同独立後,1972年(昭和47年)1月,アワミ連盟(以下「AL」という。)が政権を獲得したところ,クーデターが繰り返されながら軍事政権が続いた。
1982年(昭和57年)にクーデターで政権を奪取したエルシャド大統領は,1990年(平成2年)12月,AL及びバングラデシュ民族主義党(以下「BNP」という。)の2大政党並びに国民の退陣要求に応じ,平和裡に民主化へ移行し,1991年(平成3年),総選挙で勝利したBNPが政権を取った上,大統領制から議院内閣制へと体制が変更され,大統領は象徴的地位となった。
(甲B3〔1頁〕,乙21〔197頁〕,23の1〔1頁〕)
(イ) 民主主義体制確立後のバングラデシュの政治体制
バングラデシュの国家元首は,国会議員による間接選挙で選出された大統領であるが,大統領は,象徴的な地位を有するにすぎず,行政の実権は首相に付与されている。議会については一院制が採用され,大統領により議会の多数派指導者が首相に指名され,内閣を組織する。国会議員の任期は5年である。また,主要政党としては,AL及びBNPの二大政党のほか,国民党,イスラム教の宗教政党であるイスラム協会(ジャマティ・イスラミー)などがある(甲B3〔1頁〕,乙21〔197頁〕,23の1〔1頁〕)。
(ウ) 現在までのバングラデシュの政治状況
バングラデシュにおいては,民主主義体制が確立した1991年(平成3年)に,総選挙ではBNPが政権に就いたが,1996年(平成8年),2001年(平成13年)に総選挙が実施され,その度にAL政権とBNP政権が交代してきた(甲B3〔1頁〕,乙23の1〔1頁〕)。
平成18年(2006年)10月,BNP政権が任期満了により退陣し,選挙管理内閣に移行したが,同内閣の人事などをめぐり政党間対立が激化し,国内情勢が悪化した結果,2007年(平成19年)1月11日,政府は非常事態宣言を発表し,選挙管理内閣の首班が辞任して総選挙は延期された。そして,新たに組閣された選挙管理内閣の下,約2年間にわたり選挙人名簿及び選挙人IDの作成,汚職対策などが推進され,2008年(平成20年)12月29日,総選挙が実施された結果,前野党のALが政権に就いた(甲B3〔1頁〕,乙21〔197頁〕,23の1〔1頁〕)。
2014年(平成26年)1月5日,議会の任期満了に伴う総選挙が行われたが,議会が選挙管理内閣設置を定めた条項を撤廃する憲法改正案を可決したことや特別法廷による独立戦争当時の戦犯に対する裁判をめぐり与野党の対立が先鋭化していたことから,BNP率いる野党18党連合は総選挙をボイコットし,その結果,与党であるALが圧勝した。同月12日,新たにAL政権が発足し,野党勢力が弱体化する中で,国内情勢は比較的安定したが,2015年(平成27年)初頭,野党連合がボイコットした総選挙の1周年を機に,野党連合が再び反政府運動を行うなど,与野党間の対立は続いている。(甲B3〔1頁〕,乙21〔197頁〕,23の1〔1頁))
イ CHTの状況
(ア) 概略
CHTは,バングラデシュ南東部のミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)との国境を接する地域に位置し,ランガマティ県,バンドルボン県及びカグラチョリ県(以下「丘陵3県」という。)がある。同地域には従来から11ないし20のモンゴロイド系少数民族(チャクマ族,マルマ族,トリプラ又はトリプリ族等)が居住しており,これらの少数民族は,総じて「ジュマ族」と呼称される。バングラデシュ独立前においては,CHTにおける経済・文化上の独自性が維持されており,総人口も約60万名以上にのぼるとされている。その中で最も多いのがチャクマ族である(甲B2〔15頁〕,7,12〔2ないし3頁〕,乙23の2〔15頁〕,乙25の2,乙26〔459頁〕,33の2)。
これら少数民族の多くは上座部仏教徒であるが,ヒンドゥー教,キリスト教及びアニミズムの信仰者も存在し,ベンガル人イスラム系入植者も多数居住している(乙25の2,乙30〔訳文1枚目〕)。
(イ) 和平協定の締結に至る経緯
a バングラデシュ政府は,1971年(昭和46年)の独立後,チャクマ族を始めとする少数民族が自治権を要求したことから,少数民族側を反政府勢力とみなし,ベンガル・ナショナリズムを掲げて,多数民族であるベンガル人をCHTへ入植させる政策を進めた。その結果,CHTでは,ベンガル人入植者と少数民族間における衝突・紛争にまで発展した(甲B11,乙26〔459頁〕)。
この衝突・紛争を受け,チャクマ族は,1973年(昭和48年),自らの政治組織「PCJSS」の下に軍事組織である「シャンティ・バヒニ(平和の戦士)」を結成し,バングラデシュからの分離独立を主張し,政府軍との武力紛争を開始した。少数民族側は紛争の激化とともに,チャクマ族を中心に約6万名が国境を接するインド・トリプラ州やミゾラム州に避難した(甲B2〔15頁〕,7,12〔18ないし20頁〕乙23の2〔15頁〕,乙26〔459頁〕)。
バングラデシュ政府は,1989年(平成元年),問題の解決に向け,丘陵3県に県評議会を設置するための県評議会選挙を実施し,1992年(平成4年)には,和平に向けてPCJSSとの協議を開始したものの,合意には至らなかった(甲B2〔15頁〕,乙23の2〔15頁〕,乙26〔459頁〕)。
b バングラデシュ政府は,1996年(平成8年)9月30日,アブル・ハシナト国会議長(当時)を委員長として,国家チッタゴン丘陵地帯委員会(以下「NCCHT」という。)を設置し,NCCHTとPCJSSとの間で,同年12月以降,7回にわたる協議が行われた上,1997年(平成9年)12月2日,PCJSSとバングラデシュ政府との間で和平協定が署名され,即日発効した(甲B11,乙26〔459ないし461頁〕)。
(ウ) 和平協定の主な内容
和平協定は,NCCHTとPCJSSの両者が「チッタゴン丘陵地帯を少数民族の居住する地域と考え,その特徴を保護し地域の全体的な発展を達成する必要があることを認識した。」(和平協定の1総則(1),乙26〔479頁〕)とした上,以下のとおり,CHTに居住する少数民族の権利及び自治要求が認められた(甲B12〔38ないし40頁〕,14〔64ないし66頁〕乙26〔479ないし482頁〕)。
a 丘陵3県協議会の議員の中から選出された地域評議会を設置する。なお,全議員の3分の2は少数民族出身者から選出することが定められ,国務大臣と同等の地位を有する評議会議長を議員により選出し,必ず少数民族出身者が就任することが定められた。
b CHT開発庁長官については,少数民族出身者を優先して任命する。CHT問題省を新設し,大臣は,少数民族出身者が就任する。
c 行政,警察(治安),自治(開発,災害救援)等の各種事業を地域評議会が調整する。
d 避難していたチャクマ族の帰還問題の継続及び帰還後の土地所有権等土地に関する全ての係争処理のための土地委員会を設置する。
e PCJSSは,和平協定締結後45日以内に,政府に対し,武装要員,武器リストを提出する。政府は,武器・弾薬を寄託した者に対し,恩赦を付与するほか,PCJSS帰還家族に対して5万タカの社会復帰資金(定住化支援金)を支給し,低利融資の実施,教育振興の継続,雇用促進対策を進める。
f CHTに所在する政府軍は,臨時に設営した野営地から撤収し,既存の軍営地へ移動する。
(エ) 和平協定締結後のCHTの状況
a チッタゴン丘陵問題省の設置
和平協定の締結を受けて,1998年(平成10年)7月15日,チッタゴン丘陵省が設立された(乙30〔訳文2枚目〕)。なお,チッタゴン丘陵省は,BNP政権下において,名称がチッタゴン丘陵問題省に変更されている。
同省は,CHTのための計画立案や開発活動,CHTに居住する少数民族及び非部族の人々の経済,教育,文化,社会活動,言語,土着の宗教活動向上,その他各省庁や各県協議会等との調整・協力をするなど業務を担当している(乙30〔訳文3枚目〕)。
b BNP政権下における状況(2001年(平成13年)から2008年(平成20年)まで)
2001年(平成13年),バングラデシュの政権は,ALから和平協定に反対したBNPに移行した。BNP政権下においては,和平協定に掲げる県評議会,CHT地域評議会選挙は実施されず,軍関係施設の撤退もほとんど進まなかった。また,ベンガル人入植者による少数民族家屋の焼き討ち事件などが発生し,PCJSSと和平協定に反対しているUPDFとの対立も加わり,CHTの状況は複雑化した。(甲B2〔15頁〕,乙23の2〔15頁〕)
c AL政権下における状況(2008年(平成20年)から現在まで)
バングラデシュにおいては,2008年(平成20年)末の総選挙以降,現在に至るまで,AL政権が続いているところ,同政権は,CHT問題について,度々,和平協定の全面的履行は政権としての義務であり,そのための努力を継続することを明言し,AL政権は,「チッタゴン丘陵協定実施のための国会常設委員会」の設立,適切に展開されていなかった農園の賃貸借の取消し,治安部隊の撤退等を進めているなどの報道がされている(乙34〔別紙項番4,5,9,11,12,16及び17〕)。
(オ) 和平協定履行以外のCHTに対する取組み状況
CHTに対する施策として,政府機関において,CHTにおける子供及び母親の死亡数減少,栄養不良の解消,伝染病の削減,初等教育の拡充及び自己雇用の創出などに重点を置いた計画が実行され,教育,医療,衛生等の充実を図る施策が講じられ,また,発展の遅れたCHTの困窮したコミュニティにおける設備を確保することにより,社会的平等を創造することを目的とするプロジェクトが実行されている(乙32,34〔別紙項番7〕)。
ウ チャクマ族について
チャクマ族は,CHTを中心に,ミャンマー西部からインドのトリプラ州,ミゾラム州,アルナーチャル・プラデーシュ州までの丘陵地帯に多く住む民族であって,その多くは,上座部仏教を信奉している。民族起源についてはビルマ出自説が有力で,上ビルマで王国を築いていたが,1418年(応永25年)のビルマ軍との戦いで敗退し,アラカンを経由してCHTに最終的に定着したとされる。CHTでは,人口の規模からも,軍事的・経済的実力からも主要民族として君臨していたが,イギリスの統治下に入り,その後,インド・パキスタン分離の際の外交的取引により東パキスタンに編入された上,バングラデシュ独立を経て現在に至っている。(甲B12〔3,4頁〕,乙25の1)
エ PCJSSについて
PCJSSは,東パキスタン時代以来の少数民族に対する差別や,ベンガル人入植者による経済的圧迫などに加え,バングラデシュ独立後も,政府が少数民族問題に関心を示さず,むしろチャクマ王族の一部が独立戦争の際にパキスタン側に立ったことをもって少数民族団体の活動を全般的に禁止するなどしたことから,1972年(昭和47年),このような少数民族に対する敵視政策に反対したチャクマ族青年らが中心となって,結成された。そして,1973年(昭和48年),PCJSSの武装組織として「シャンティ・バヒニ」が結成され,バングラデシュ政府に対し,ゲリラ闘争で対抗した。(甲B12〔19,20頁〕,乙25の2)。
和平協定は,PCJSSが主体となってバングラデシュ政府と協議を重ねて成立したものであるところ,政府との和平協定を推進していたのは,PCJSS議長のシャントゥ・ラルマを中心とする穏健派であった。一方,「シャンティ・バヒニ」を中心とした強行派は,あくまでも分離独立を獲得するために武装闘争を続けるべき旨を主張し,2派に分裂するなど,PCJSS内部における対立も激しくなった(乙26〔460頁〕)。
PCJSSと和平協定に反対して設立されたUPDFとは度々対立しており,互いを非難しているとの報道も見られる(乙39〔別紙項番4ないし6〕)。
オ UPDFについて
1998年(平成10年)12月28日,和平協定に反対するCHTの3つの団体(丘陵人民評議会(PGP),丘陵学生評議会(以下「PCP」という。)及び丘陵女性連盟(HWF))がUPDFを設立した。UPDFは,CHTにおける完全な自治権の確立を目指している(甲B13〔3頁〕,乙37)。
そして,UPDFは,和平協定に反対しているという点からも,PCJSSとの間で度々対立を起こし,その結果,銃撃戦になることもある(甲B2〔15頁〕,13〔6ないし8頁〕,乙23の2〔15頁〕,乙39〔別紙項番4ないし6〕)。
(3) 原告夫の個別事情について(個別に掲記するほか,全体として甲A5,原告夫本人)
ア 原告夫は,PCPに参加し,その後PCJSSにも参加していたが,バングラデシュ政府とPCJSSとの和平協定に反対していたことから,1999年(平成11年)にUPDFに参加した(乙5〔3,4頁〕,11〔4頁〕)。
イ 原告夫は,2007年(平成19年)2月14日,正規のパスポートを取得し,同年3月2日,原告妻と婚姻したものの,一緒に暮らすことはなく,同年5月26日,バングラデシュを出国し,インドを経由して,同月30日,スリランカに入国し,1年の滞在許可を得て同国に滞在した(乙2の1)。
ウ 原告夫は,スリランカから別の国に渡航することを考えていたところ,資金に窮し,2008年(平成20年)1月8日,再びインドを経由してバングラデシュに帰国した(乙2の1)。
エ 原告夫は,2008年(平成20年)4月9日,正規の手続によりバングラデシュを出国し,インド及びタイを経由して,同月12日,スリランカに入国した(乙2の1)。
オ 原告夫は,2008年(平成20年)7月4日,スリランカを出国し,タイを経由して,同月6日,韓国へ渡航したが,上陸を拒否されて,同月9日,スリランカに戻った(乙2の1)。
カ 原告夫は,平成21年7月2日,本邦に上陸し,同月16日,本件原告夫申請を行った(乙3)。
(4) 検討(原告らの主張について)
ア 原告らは,原告夫が何度も拘束や暴力を受けてきた旨を主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ(ア) 原告らは,原告夫が,かつてバングラデシュにおいてUPDFで活動していたことを理由に,バングラデシュ政府から迫害を受けたり,PCJSSから危害を加えられるおそれがある旨を主張する。
しかし,原告夫は,平成21年10月15日の横浜支局における調査において,原告自身はUPDFのメンバーであることを理由として本国政府から尋問や身柄拘束,暴力等を受けたことはないことを自認する供述をしている(乙4〔9頁〕)。
また,原告夫は,1999年(平成11年)1月にバングラデシュ政府とPCJSSとの和平協定に反対し,UPDFに参加したものであるが,その具体的な活動内容については,村の人々にUPDFをサポートするように話したり,和平協定が実行されていないことを知らせたりするほか,主として会議の事前打合せ及び調整といった程度の補佐的なものにすぎなかった旨供述する上,2005年(平成17年)1月には,僧侶になるために出家し,出家と同時にUPDFの活動は行っていなかった旨を供述する(乙4〔10頁〕,5〔3ないし6頁〕,11〔4頁〕)。
さらに,原告夫は,UPDFに加入後に,警察やPCJSSと衝突したことはなく,UPDFに参加してから僧侶になるまでの6年間に,PCJSSから,UPDFに参加したことを理由に直接に具体的な暴行や迫害を受けたようなこともない旨,僧侶になった後,2007年(平成19年)5月にスリランカに出国しているところ,その間においても,政府や警察,PCJSSのメンバーから迫害を受けたこともなかった旨を供述する(乙11〔5,15頁〕)。
その上,原告夫は,自身がバングラデシュを出国しなければならないと思った理由について,直接,自身の身の上に暴行や迫害を受けたということはなく,その当時,置かれている状況からすれば,政府もPCJSSもUPDFもどこも信用のおけないような,紛争も絶えないというような状況の中,生活することができないなど(乙11〔16頁〕),飽くまで漠然とした抽象的な危険性に対して恐怖を抱いていたことを供述するにとどまっている。
以上のとおり原告夫が供述するところに照らしても,原告夫がUPDFのメンバーであったとしても,原告夫に対する迫害のおそれは,抽象的なものにとどまるというほかない。
(イ) 原告らは,2008年(平成20年)4月3日に原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害された旨を主張する。
しかし,原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたことを認めるに足りる客観的証拠はない。
また,原告夫は,母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたのは,原告夫がスリランカからバングラデシュに帰国した後の2008年(平成20年)4月3日であった旨を供述する(乙4〔7頁〕,5〔14頁〕)ところ,同供述は,2007年(平成19年)2月14日付けでバングラデシュ政府が発給した原告名義旅券の母の氏名欄に,既に故人であることを示す「LATE」の記載がされていること(乙2の1)と整合しない。
この点,原告夫は,旅券が発給された時点では「LATE」の記載はなく,同記載は,母親が殺害された後に,原告夫の師匠である住職に依頼して,訂正の手続をしたものである旨,バングラデシュにおいては,旅券の記載を訂正した後に日付等を明記する習慣がないと思われる旨を供述する(乙5〔15,16頁〕,11〔7頁〕,原告夫本人〔調書11,24頁〕)。また,原告夫は,母親を殺害した者から,「訴えたらお前たちも殺す。」と脅されため,母親が殺害された事実を警察に届け出ておらず,また,死亡したことを届け出る必要もなく,火葬するのみであった旨(乙4〔14頁〕),バングラデシュにおいては,日本におけるのと異なり,人が殺害された場合に警察に通報することはなく,公的に死亡を証明する書類もない旨を供述する(乙11〔6及び7頁〕)。しかし,旅券発給後に「LATE」という文字を単に書き加えたということ自体,旅券が公的な文書であることに照らすと,不自然かつ不合理というべきである。また,原告夫の上記供述を前提とすれば,原告夫の母親が死亡した事実を証する資料がなく,何ら公的な確認がされていないにもかかわらず,旅券に加筆されたこととなるが,このような事態はおよそ考え難い。したがって,旅券の記載に係る原告夫の上記供述は,採用することはできない。
したがって,原告夫の母親がPCJSSのメンバーによって殺害されたとの原告夫の供述は,採用することができず,他に原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
ウ(ア) 原告らは,原告夫に対して本件逮捕状が発付されているところ,その被疑事実は,2006年(平成18年)6月26日に原告夫ほか5名がバングラデシュ政府軍の兵士を銃撃し,1名の氏名不詳の者を死亡させたというものであるところ(甲A12の1,乙10の1),原告夫は,既に2005年(平成17年)に出家してUPDFの活動を行っておらず,本件逮捕状は架空の事実に係るものであって,原告夫がUPDFの活動家として,国家に対する反逆者として位置付けられており,本国に帰国すると逮捕され,身の危険が及ぶなどと主張し,同旨を供述(甲A5,原告夫本人〔調書9,10,18ないし20頁〕)するほか,本件逮捕状の写し(甲A12の4),上記被疑事実に係る告訴状謄本(甲A12の1),調書謄本(甲A12の2),起訴状謄本(甲A12の3)を提出している。
(イ) 上記の本件逮捕状等は,バングラデシュの弁護士による法律専門家意見書(甲A11)の記載や上記各書証の体裁から,一応真正に成立したものと推認されるが,上記の本件逮捕状等の記載によれば,原告夫ほか5名のうち,原告夫も知っているUPDFのメンバーであるBが逮捕され,同人の供述により原告夫ほか4名も被疑者として特定されたことがうかがわれるところ,2006年(平成18年)6月26日当時,原告夫は出家し,UPDFの活動には関与していなかった旨を供述していることに照らすと,原告夫に対する被疑事実は誤りである可能性が否定できない。
しかし,原告夫に対する被疑事実が誤りであるとしても,上記の本件逮捕状等の記載によれば,上記のとおり,UPDFのメンバーの一人が逮捕され,原告夫がリーダーであった旨を供述し,このことを踏まえ,捜査機関が捜査をして起訴されていることがうかがわれることに照らすと,本件逮捕状の発付等の手続がバングラデシュ政府による正当な刑罰権の行使であることが直ちに否定されるものではなく,上記の本件逮捕状等が存在することをもって原告に対する迫害のおそれがあるということはできない。
そして,前記(3)のとおり,原告夫は,2007年(平成19年)2月14日,バングラデシュ政府から自己名義の旅券の発給を受けたこと,同年5月26日に正規の手続を経てバングラデシュを出国した上で,2008年(平成20年)1月5日にバングラデシュに帰国したこと,同年4月9日に再び正規の手続によって出国したことが認められる上,原告夫は,上記バングラデシュの出入国に際し,何ら問題はなかった旨を供述する(乙4〔16頁〕)。このように,原告夫は,本件逮捕状が発付されたとされる時期以降に任意に帰国しており,本国への入国の際には何ら問題はなかった旨を自認しているところ,仮に,バングラデシュ政府又はPCJSSが,UPDFの活動家である原告に注目し,同人を迫害するために,上記被疑事実をねつ造したものであるとすると,何ら問題なくバングラデシュを出国し,また帰国したという原告夫の上記言動と整合せず,不合理というべきである。
エ 原告らは,ジュマボイスで活動しているメンバーが国家反逆罪でバングラデシュ政府から逮捕状を発付されているところ,原告夫も本邦においてジュマボイスの活動に参加しており,そのメンバーである原告夫に対して逮捕状が発付されていることから,原告夫がバングラデシュに帰国すれば,政府から迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
しかし,ジュマボイスで活動しているメンバーに逮捕状を発付されていること等をもって,直ちに原告夫について,本邦においてジュマボイスの活動に参加していることからバングラデシュにおいて政府から迫害を受けるおそれがあると認めるに足りる証拠はなく,他に原告夫がジュマボイスで活動していることをもって帰国すると迫害を受けるおそれがあるとは認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,原告夫が本邦でジュマボイスの活動に参加しているとしても,そのことをもって難民該当性を基礎付けることはできないというべきである。
オ(ア) 前記(3)のとおり,原告夫は,2007年(平成19年)5月30日に,スリランカに入国し,1年の滞在許可を得て同国に滞在し,その後,インドを経由してバングラデシュに一旦帰国した後,2008年(平成20年)4月12日に,インドを経由してスリランカに再び入国している。
しかし,仮に,原告夫が,バングラデシュにおいて迫害を受けるおそれを抱いており,2006年(平成18年)10月15日付けで本件逮捕状も発付されていることを知っていたのであれば(甲A5〔4頁〕,原告夫本人〔調書9頁〕),上記のとおりスリランカからバングラデシュに帰国することで迫害を受けるおそれがあったと考えられるところ,スリランカ政府に対して自身が難民であることを申し出て庇護を求めることもなく,上記の行動に出ているものである(乙3〔項番10〕)。
この点,原告夫は,スリランカは安全ではあるものの,僧侶として滞在する以上,非常に多くの規則を守らなければならず,それでは自分の家庭を築くことができない状況であった旨を供述し(乙11〔17頁〕),僧侶の身であったために,スリランカ政府に対して庇護を求めなかった旨を述べるが,原告夫が僧侶であったとしても,スリランカにおける在留には期限があり,在留許可が打ち切られることも考えられることからすれば,原告夫が真にバングラデシュに帰国することによって迫害を受けるおそれを抱いていたのであれば,スリランカ政府に庇護を求めることが考えられるにもかかわらず,これを求めていない。このような原告夫の態度は,迫害のおそれを抱く者の行動として,不自然というべきである。
(イ) また,前記(3)のとおり,原告夫は,2008年(平成20年)7月6日にタイ王国経由で韓国へ渡航しているが,平成23年3月18日に行われた福岡入国管理局難民調査官による事情聴取においては,韓国に行く目的が大学のプログラムの一環であり,難民に関する認識が全くなかった旨供述し(乙5〔18頁〕),その後においては,韓国に行って難民申請をしようと思っていたものの,入国が認められなかったため,韓国政府に対して自身が難民であることを申し出ることはしなかった旨を供述する(乙11〔17頁〕,原告夫本人〔調書12,25,26頁〕)。
しかし,真に原告夫が本国において迫害を受けるおそれがあるのであれば,たとえ上陸を拒否されたとしても,空港において自身が難民であることを申し出て庇護を求めることができたと考えられるにもかかわらず,庇護を求めなかったというのである。上記(ア)と同様,このような原告夫の態度も,迫害のおそれを抱く者の行動として,不自然というべきである。
(ウ) 以上のとおり,原告夫がスリランカや韓国において庇護を求めていないことからも,現に,原告夫に迫害のおそれがあったとは認められない。
カ 以上によれば,原告夫が本国に帰国すると本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められず,また,通常人が原告夫の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということもできない。したがって,原告夫が難民であるということはできず,原告夫を難民と認めなかった本件原告夫不認定処分に違法な点はないから,本件原告夫不認定処分は,適法である。
2 争点(2)(本件原告妻不認定処分の適法性(原告妻の難民該当性))について
上記1に判示したとおり,原告夫は,難民とは認められず,本国に退去強制されても,迫害を受けるおそれがあるとは認められず,他に,原告妻が難民であると認めるに足りる証拠はない。したがって,原告妻が難民であるということはできず,原告妻を難民と認めなかった本件原告妻不認定処分に違法な点はないから,本件原告妻不認定処分は,適法である。
3 争点(3)(本件各義務付けの訴えの適法性等)について
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の処分の義務付けの訴えであると解されるところ,同訴えは,法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)。
しかるに,上記1及び2のとおり,本件各不認定処分はいずれも適法であるから,本件各義務付けの訴えは,同法37条の3第1項2号の要件を欠き,いずれも不適法である。
第4 結論
よって,その余の点を判断するまでもなく,本件訴えのうち,本件各義務付けの訴えはいずれも不適法であるから却下し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 梶浦義嗣 裁判官 高橋心平)
別紙1
指定代理人目録〈省略〉
別紙2
関係法令の定め
1 入管法2条(定義)
入管法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1ないし3号 〔略〕
(2) 3号の2
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
(3) 4ないし16号 〔略〕
2 難民条約1条(「難民」の定義)
(1) A
この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
ア (1) 〔略〕
イ (2)
1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
〔以下略〕
(2) BないしF 〔略〕
3 難民議定書1条(一般規定)
(1) 1
この議定書の締約国は,2に定義する難民に対し,難民条約第2条から第34条までの規定を適用することを約束する。
(2) 2
この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
(3) 3 〔略〕
以上
*******
政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
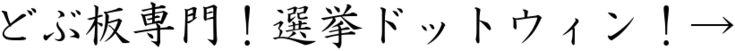




この記事へのコメントはありません。